労働者賃金
フィリピン労働法の下での労働者賃金とは、連続・非連続にかかわらず、1日8時間の労働に対して合法的に雇用された労働者が受け取る金額のことである。
1日とは労働者が仕事を始める時点からその後24時間のことである。労使協定によると、従業員の賃金はあらかじめ決められた期間(時間給、日給、あるいは月給)で支払われる。8時間労働に対する最低報酬は、地域三者賃金生産性委員会(Regional Tripartite Wage and Productivity Boards:RTWPBs)が定めたその地域に適用される最低日給以上となる。雇用者は労働者の同意がなければその賃金を調整することは許されない。ただし保険料、源泉課税、社会保障及び他の法律で定められた控除、例えば組合費などこれに類するものは例外として認められる。
労働者賃金は時間外労働、休日、祭日、夜間労働割増金、13カ月目の給与といった恩典を含んでいる。さらに、雇用者が習慣的に提供する施設、労働者の福祉のためのみに使用する費用、健康保険、生命保険、その他の保険、市場より有利な貸付金利、他の商品やサービスや割引などに「賃金恩典」という言葉が幅広く使われ始めている。
共和国法第6758号の報酬と地位の分類に関する法律では、基本的に同一労働に対する同一賃金支給、義務と責任の大きさの違いによる基本給の差異、各地位の賃金率に十分な配慮をするよう定められている。そのため予算行政管理省(Department of Budget and Managements:DBM)は大統領令985号に規定された統一報酬と地位の格付け制度を設定、管理することが憲法によっても定められている。同法により、すべての職に1から33の給与等級が定められた。
表2‐12 職別給与等級一覧給与等級 職
33 大統領
32 副大統領、上・下院議長、最高裁判所長官
31 上・下院議員、最高裁判所判事、憲法委員会議長
30 憲法委員会議員
~
20 地方保健医師
19 准教授
18 森林監督官
17 郵便局長
16 歯科医
15 行政官
14 法務官
13 獣医
12 技術者
11 社会福祉士、農学士、科学者、主計官
10 教員、出納係、看護士
9 教育研究助手
8 行政助手、簿記係
7 秘書
6 電気工
5 大工
4 速記者、職工
3 運転手、事務員
2 配達係
1 肉体労働者
メイドなどの規定は明確化されていない。
貧困層増加の原因。
◇2007~08年の食品価格の高騰
◇08~09年の世界経済・金融危機
◇09年に相次いでフィリピンを襲った台風16号(アジア名・ケッツァーナ、比名・オンドイ)、同17号(アジア名・パーマァ、比名・ペペン)、同21号(アジア名・ミリネ、比名・サンティ)。
これらの影響を受け、昨年の製造業の成長率はマイナス7.8%と、前年のプラス1.4%から大幅に後退。鉱工業全体の成長率は前年のプラス0.7%からマイナス6.1%に、農業はマイナス0.3%からマイナス6.1%にそれぞれ後退した。
生産分野がマイナス成長した結果、失業率が上昇し、国民の平均所得は2.1%減少。貧困率は1.6%増加した。
世界的金融危機の影響を受けたとはいえ、貧困層が200万人も増えたという事実は容認できない。フィリピンは、世界でも急速に成長を遂げるアジアに属し、資源や技術を保有しているにもかかわらず、なぜ国連のミレニアム開発目標(MDG)を達成できないのか?
フィリピン政府は、貧困削減のため、行政管理やMDGが掲げる社会保障などの基礎的な問題に取り組むべきと。
なぜ出来ないのか?政府内部の者の私物化による賄賂収入が、解決を遅らせている最大の要因です。
労使ともに不満
ECOPのエドガルド・ラクソン代表は、最低賃金の引き上げ実施に対する不満を表明。「フィリピンの最低賃金は、ベトナム、カンボジア、インドネシア、タイよりも高い」と強調し、引き上げ実施を疑問視する姿勢を示した。
フィリピン商工会議所(PCCI)のフランシス・チュア会頭も、「経済界は15ペソの引き上げなら支持するが、22ペソは予想外だった」とコメントしている。
昨年度の賃上げ要求額は全国一律125ペソの最低賃金引き上げ。左派労組(KMU)22ペソの引き上げについて、「最低賃金で働く労働者に対する侮辱だ」と遺憾の意を表し「1キロ当たり約28~32ペソのコメを買うことすらできない」と不満を表明しています。
過去の最低賃金は、アキノ政権下(1986~1992年)で121ペソから203ペソ
ラモス政権下(92~98年)で203ペソから217ペソ
エストラーダ政権下(98~2001年)に217ペソから238ペソ
01年に発足したアロヨ政権下では、238ペソから250ペソ
引き上げ幅はわずか13ペソにとどまっている。
このフィリピンの大きな雇用環境問題。
6ヶ月雇用契約。この雇用契約がある限り、雇用者は結果として正社員を極力少なく雇用する方策をとります。サービス業の例として勤続12年。今でも6ヶ月雇用契約から5ヶ月雇用策へ変更されているものが非常に多く見受けられます。
主な方法は
AおよびBといった企業を設立します。
当初A社にて雇用契約。6ヶ月を経過しない時点で契約を解除する。
その後、当事者の勤務意欲があればB社にて5ヶ月の雇用契約を行う。
B社の5ヶ月の雇用契約は期間満了前4ヶ月と15日くらいで雇用契約を解除し退職させる。本人へ打診、雇用意欲があれば2週間ほど休ませ、再度A社へ5ヶ月契約で勤務させる。勤務するものもこのような事情をよく知っていて、ずるずるとこういった雇用環境に甘んじているのも実情です。
6ヶ月雇用契約。賃金月2回支払い。このような雇用環境が長年続いてきたフィリピン。まだまだ一般雇用者の暮らしがよくなるには程遠いようにも。
政策とは相反し年々貧困者数が増加する。その一方、賄賂等などの摂取が困難になり、結果、かかわる要職者はじめその部下の勤務意欲が衰退してきているように見受けられるこのごろです。

























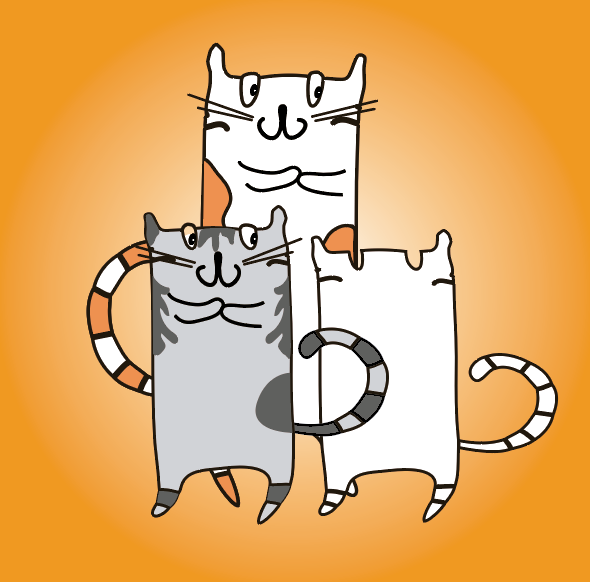

どこにも行く気がしないマニラ。
確かに表面のアキノ政権とは裏腹に、犯罪が多発しています。この国はやはり銃は絶対に持たせるべきではないです。
喜怒哀楽が激しいというよりもともと凶暴なのかも知れません。