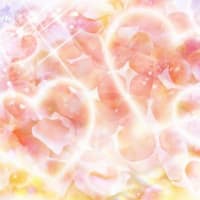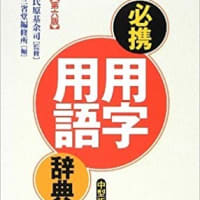◆はじめの一歩
小学1年生になって、ひらがなの学習をすれば、作文を書くことはそれほどむずかしくありません。最初から自分の力だけで文章を書かせるのではなく、子供の話を引き出しながら一文ずつ口述筆記をさせていると、あっという間に自力で文を書くことができるようになります。このときに大切なことは、とにかくほめることです。多少表記の間違いがあっても、一人で文を書くことができたという点を評価してあげてください。
◆文が書けたら
主語述語のある文が書けるようになったら、名前や数字をくわしく書くように指導します。友達の名前、時刻など、名前や数字を使ってくわしく書けるものはなるべく詳細に書いていきます。これは小学1年生でも簡単にできます。簡単にできるということは、それだけほめる機会が増えるということでもあります。名前や数字がくわしく書けたらどんどんほめてあげてください。
◆たとえ表現
小学1年生でもできる表現の工夫の一つとしてたとえが挙げられます。「まるで~みたい」「まるで~のよう」という言葉を使いながらたとえの練習をしていきます。特に小学生の作文では、このたとえが印象的に使われているかどうかが作文の出来を大きく左右します。だからこそ、小学1年生のうちからたとえに慣れておくことが大事です。最初のうちは、「まるでりんごのように赤い」、「まるでお月様のように丸い」など、簡単なたとえで構いません。作文の中に必ず一つはたとえを入れるという指導をします。
◆会話
会話が入ると作文が生き生きとしてきます。誰かが話したことをそのまま書くように指導します。最初のうちは、カギかっこの書き方を手助けしてあげる必要はありますが、会話の内容を思い出して書くこと自体はあまり苦にならないようです。小学1年生だからこそ、飾らずに、ありのままの会話を生き生きと書くことができるのかもしれません。その人らしさが表れた会話は、作文の質を高めます。最初のうちは短い会話で十分ですが、慣れてきたら、長い会話を入れてみましょう。さらに味のある作文になります。
◆思ったこと
出来事だけではなく、そのときの気持ちを書くことは作文の大切なポイントです。小学1年生のうちは、思ったことを自分らしく表現するのはまだむずかしいのですが、「楽しかったです」「おもしろかったです」など、単純な表現にならないよう工夫しましょう。これには、「思いました」という言葉を使って自分の気持ちを書くように指導をすると効果があります。
◆表記
小学1年生の段階では、表記についてはあまり厳しく指導しない方がよいでしょう。読みを重ねていくうちに、表記ミスは必ず直っていくものです。ミスを指摘して正していくよりも、読みの練習をすることによって、自然にミスをなくしていく方が子供も指導する側もストレスが少なく、効果が高いようです。
◆投稿でやる気を
朝日小学生新聞や毎日小学生新聞の投稿欄には、小学1年生の作文が掲載されることも少なくありません。いい作品が書けたら、どんどん投稿してみましょう。言葉の森の生徒の作品は、ほとんど毎週、小学生新聞に掲載されていますが、もちろん、中には小学1年生の作品もあります。
◆音読も欠かさずに
小学1年生から言葉の森の勉強を始めると、自習の習慣がつきやすいという利点があります。音読は、読解力・表現力をつけるためには欠かせません。音読の自習は、時間にすればせいぜい10分程度なのですが、毎日続けることがむずかしいのです。小学校1年生のうちに、この自習の時間を生活の中に組み入れてしまえば高学年になっても、中高生になっても、自習の習慣がずっと続きます。音読によって、普段の読書だけでは補えない語彙力や文のリズムなどを身につけていきましょう。 言葉の森では、読解マラソンを推奨しています。小学1年生の長文はこちらをご覧ください。
http://www.mori7.net/marason/marason_sample.php?yama=a&gakunennjunn=1
小学1年生になって、ひらがなの学習をすれば、作文を書くことはそれほどむずかしくありません。最初から自分の力だけで文章を書かせるのではなく、子供の話を引き出しながら一文ずつ口述筆記をさせていると、あっという間に自力で文を書くことができるようになります。このときに大切なことは、とにかくほめることです。多少表記の間違いがあっても、一人で文を書くことができたという点を評価してあげてください。
◆文が書けたら
主語述語のある文が書けるようになったら、名前や数字をくわしく書くように指導します。友達の名前、時刻など、名前や数字を使ってくわしく書けるものはなるべく詳細に書いていきます。これは小学1年生でも簡単にできます。簡単にできるということは、それだけほめる機会が増えるということでもあります。名前や数字がくわしく書けたらどんどんほめてあげてください。
◆たとえ表現
小学1年生でもできる表現の工夫の一つとしてたとえが挙げられます。「まるで~みたい」「まるで~のよう」という言葉を使いながらたとえの練習をしていきます。特に小学生の作文では、このたとえが印象的に使われているかどうかが作文の出来を大きく左右します。だからこそ、小学1年生のうちからたとえに慣れておくことが大事です。最初のうちは、「まるでりんごのように赤い」、「まるでお月様のように丸い」など、簡単なたとえで構いません。作文の中に必ず一つはたとえを入れるという指導をします。
◆会話
会話が入ると作文が生き生きとしてきます。誰かが話したことをそのまま書くように指導します。最初のうちは、カギかっこの書き方を手助けしてあげる必要はありますが、会話の内容を思い出して書くこと自体はあまり苦にならないようです。小学1年生だからこそ、飾らずに、ありのままの会話を生き生きと書くことができるのかもしれません。その人らしさが表れた会話は、作文の質を高めます。最初のうちは短い会話で十分ですが、慣れてきたら、長い会話を入れてみましょう。さらに味のある作文になります。
◆思ったこと
出来事だけではなく、そのときの気持ちを書くことは作文の大切なポイントです。小学1年生のうちは、思ったことを自分らしく表現するのはまだむずかしいのですが、「楽しかったです」「おもしろかったです」など、単純な表現にならないよう工夫しましょう。これには、「思いました」という言葉を使って自分の気持ちを書くように指導をすると効果があります。
◆表記
小学1年生の段階では、表記についてはあまり厳しく指導しない方がよいでしょう。読みを重ねていくうちに、表記ミスは必ず直っていくものです。ミスを指摘して正していくよりも、読みの練習をすることによって、自然にミスをなくしていく方が子供も指導する側もストレスが少なく、効果が高いようです。
◆投稿でやる気を
朝日小学生新聞や毎日小学生新聞の投稿欄には、小学1年生の作文が掲載されることも少なくありません。いい作品が書けたら、どんどん投稿してみましょう。言葉の森の生徒の作品は、ほとんど毎週、小学生新聞に掲載されていますが、もちろん、中には小学1年生の作品もあります。
◆音読も欠かさずに
小学1年生から言葉の森の勉強を始めると、自習の習慣がつきやすいという利点があります。音読は、読解力・表現力をつけるためには欠かせません。音読の自習は、時間にすればせいぜい10分程度なのですが、毎日続けることがむずかしいのです。小学校1年生のうちに、この自習の時間を生活の中に組み入れてしまえば高学年になっても、中高生になっても、自習の習慣がずっと続きます。音読によって、普段の読書だけでは補えない語彙力や文のリズムなどを身につけていきましょう。 言葉の森では、読解マラソンを推奨しています。小学1年生の長文はこちらをご覧ください。
http://www.mori7.net/marason/marason_sample.php?yama=a&gakunennjunn=1