宮城県の北部、奥羽山脈の東側の麓にある、
細倉鉱山のシリーズです。

˚細倉鉱山の守り神、山神社。Mapion
元々は1800年の初頭に、
山伏達によって建立された神社だそうです。
奉られているのは山の神と鉱山・精錬の神。

前回の記事で触れたように、
細倉鉱山は、当初この辺りから採掘が始まりました。
鬱蒼と茂る林の中に佇む神社は、
修験者達の息遣いも感じる雰囲気を漂わせます。

参道階段の両脇には、
当時の献納物が今でも沢山残っています。
これはその一つの灌盤。
「灌盤」は聞き慣れない単語ですが、
手水(ちょうず)と同じ様なものでしょうか。
側面に「大阪銅御吹屋 鍵屋忠蔵」と掘られています。
吹屋とは銀や銅の精錬をする仕事で、
細倉の鉛が、大阪まで運ばれて、
精錬業者に使われていた証拠だそうです。

高橋勘五郎の狛犬。
ちょっと剽軽な顔の狛犬ですね。

参道階段には草が茂り、
あまり人が訪れていないことを物語っています。
今でも鉱山開きや山神祭の時には祈祷されるそうですが、
それでも訪れる人は少ないのだと思います。

山頂に鎮座する神殿。
屋根や正面の回廊以外は、
1800年初頭の、建立当時のままだそうです。

神殿の横には、小さな祠があります。
細倉山神社のお告げで発見に至った、
大土ケ森鉱山を奉っての祠だという事ですが、
ガンプラがお供えしてある理由は、わかりません。
何百年もの歴史を持つ細倉鉱山の、
栄枯盛衰を見守り続けて来た細倉山神社。
現代の都市部でも、
朝な夕なに神社の入口で拝礼をする方をよく見かけるので、
日本ではまだまだ神道が根強い人気があるのがわかりますが、
命を預ける仕事だった鉱山の守り神は、
ことさら大事にされたことと思います。
<<< ガンバレ!東北 >>>
細倉鉱山のシリーズです。

˚細倉鉱山の守り神、山神社。Mapion
元々は1800年の初頭に、
山伏達によって建立された神社だそうです。
奉られているのは山の神と鉱山・精錬の神。

前回の記事で触れたように、
細倉鉱山は、当初この辺りから採掘が始まりました。
鬱蒼と茂る林の中に佇む神社は、
修験者達の息遣いも感じる雰囲気を漂わせます。

参道階段の両脇には、
当時の献納物が今でも沢山残っています。
これはその一つの灌盤。
「灌盤」は聞き慣れない単語ですが、
手水(ちょうず)と同じ様なものでしょうか。
側面に「大阪銅御吹屋 鍵屋忠蔵」と掘られています。
吹屋とは銀や銅の精錬をする仕事で、
細倉の鉛が、大阪まで運ばれて、
精錬業者に使われていた証拠だそうです。

高橋勘五郎の狛犬。
ちょっと剽軽な顔の狛犬ですね。

参道階段には草が茂り、
あまり人が訪れていないことを物語っています。
今でも鉱山開きや山神祭の時には祈祷されるそうですが、
それでも訪れる人は少ないのだと思います。

山頂に鎮座する神殿。
屋根や正面の回廊以外は、
1800年初頭の、建立当時のままだそうです。

神殿の横には、小さな祠があります。
細倉山神社のお告げで発見に至った、
大土ケ森鉱山を奉っての祠だという事ですが、
ガンプラがお供えしてある理由は、わかりません。
何百年もの歴史を持つ細倉鉱山の、
栄枯盛衰を見守り続けて来た細倉山神社。
現代の都市部でも、
朝な夕なに神社の入口で拝礼をする方をよく見かけるので、
日本ではまだまだ神道が根強い人気があるのがわかりますが、
命を預ける仕事だった鉱山の守り神は、
ことさら大事にされたことと思います。
<<< ガンバレ!東北 >>>













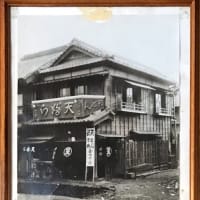




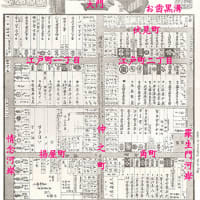
山神社は、元朝参りに毎年行っていましたねぇ。
大晦日の日付が変わる頃から、沢山の人々が山神社を目指して歩きました。
擦れ違う人達と「おめでとうございます」と挨拶しながら、雪の中を歩きました。
一番上の神殿の横では、火を焚き、お神酒(?)を振る舞う役員の方々がいました。
20歳頃、友達5人とお参りに訪れてからは、行った事が有りませんでした。
きっと久々のお参りに、神様も喜んでいたと思いますよ。
ありがとうございました。
いつもご覧になって頂き恐縮です。
山神社の当時のお話も、ありがとうございます。
鉱山が盛んだった頃は、
きっと神社に訪れる方も沢山いらっしゃったんでしょうね。
鉱山施設からかなり離れていたからかもしれませんが、
境内はとても厳かな雰囲気に包まれた感じで、
何百年も鉱山を見守り続けた神社だな~と思いました。
鉱山や炭鉱の山神社の中には、
すでに忘れ去られてしまった神社も沢山ありますが、
細倉の神社はこれからも守られて行くんではないでしょうか。