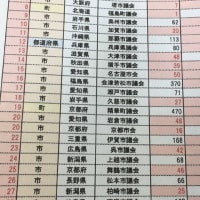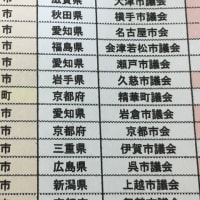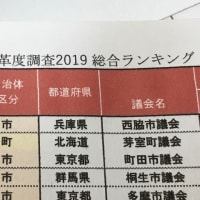5月15日。京都の方は、葵祭りを思い出す。当然かもしれない。もう1つ重要な日でもある。沖縄返還の日なのです。最近はさほど注目されないが、沖縄はアメリカ統治下にあり日本ではなかった時代がある。私が小学6年の時、担任の教師が結婚して新婚旅行が沖縄だった。出発の前に「パスポートがいる」という話を聞いたことを覚えている。その時、改めて沖縄はまだ日本ではないと強く記憶に残っている。当時は。パスポートを取ることすら一般的なことではなかったので、なおさら印象的なのかもしれない。
私も何度か沖縄に行ったことがあるが、観光コース以外で学ぶことも多い。大雑把な言い方かもしれないが、沖縄の方は争いを好まないように感じている。地理的には日本より台湾が近いし、中国など大陸との関係もあった。日本との関係は、島津=薩摩との関係が主だった。それぞれとの関係は、従属しているように見せつつ独自の文化や政治は維持してきた。外部の文化などを拒否もせず、かといってその色に染められもせず、うまく受け入れつつという感じだ。
今の時代、グローバリズムといわれ1つの国で生きていくことは困難だ。お互い影響を受けつつ進んでいる。その反動なのか、日本独自の文化・愛国心などを強調する人たちもいる。それぞれが信じることは自由なので否定できないが、問題はそれを公教育の場などで他人に押し付けるところにある。人を愛すること・郷土を愛すること・祖国を愛することは、他人から教わったり強制されることで生まれるものではない。相手を知る・郷土を知る・祖国の歴史を学ぶなど、自主的・主体的な取り組みから自然発生的に芽生えるものである。
私も何度か沖縄に行ったことがあるが、観光コース以外で学ぶことも多い。大雑把な言い方かもしれないが、沖縄の方は争いを好まないように感じている。地理的には日本より台湾が近いし、中国など大陸との関係もあった。日本との関係は、島津=薩摩との関係が主だった。それぞれとの関係は、従属しているように見せつつ独自の文化や政治は維持してきた。外部の文化などを拒否もせず、かといってその色に染められもせず、うまく受け入れつつという感じだ。
今の時代、グローバリズムといわれ1つの国で生きていくことは困難だ。お互い影響を受けつつ進んでいる。その反動なのか、日本独自の文化・愛国心などを強調する人たちもいる。それぞれが信じることは自由なので否定できないが、問題はそれを公教育の場などで他人に押し付けるところにある。人を愛すること・郷土を愛すること・祖国を愛することは、他人から教わったり強制されることで生まれるものではない。相手を知る・郷土を知る・祖国の歴史を学ぶなど、自主的・主体的な取り組みから自然発生的に芽生えるものである。