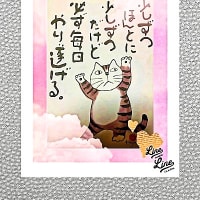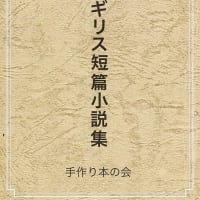入院中の老母の付き添いをしながら、雑誌『文藝春秋』第86巻第2号を読んでいたところ、たまたま「西暦2008年は明治140年」という点で一致するが、全体としては趣旨の全く違う二つの記事に遭遇した。
記事といっても、一つは、「葭の髄から」と題する巻頭の随筆欄の文章で、他の一つは、特別寄稿評論の文章なので、自ずと、硬軟、趣が大きく異なる。
? 此の小文が活字になる頃には、年が改まつて、我々みんな、ともかく平穏裡に平 成二十年の正月を迎へてゐるだらう。平成の世もすでに二十年目か、大正時代より 長くなったんだなと、私など少なからぬ感慨を覚えるのだが、仮にもう一つ前の、 近代日本最初の元号が今尚用ゐられてゐるとしたら、新しき年、西暦二〇〇八年は ちやうど明治百四十年にあたる。(阿川弘之「明治天皇と広島大本営」)
? 戊子(つちのえね)の年が明けた、といっても、十干十二支では何の感興も起こ らない。これを西暦二〇〇八年といいかえると、一八六八年の明治日本のタートか ら百四十年と換算できる。一月七日には昭和天皇ご逝去二十年を迎えた。十年ひと 昔というが、この昔風のいい方からいけば、今年はこの国の節目の年になるのかも しれない。(半藤一利「昭和天皇と明治天皇」)
阿川氏の随筆は、平成12年に司馬遼太郎の後を受け継ぎ、これまで三冊の単行本になっている。三冊目の帯に、「美しい日本語がここにあります」と印刷されているが、その「歴史的仮名づかひ」を用いた文体は、私には、「現代仮名づかい」の司馬遼太郎と比べて、まったりとして締まりがないように感じられる。
上掲の、「現代仮名づかい」で書かれた、半藤氏のメリハリのある評論の文体に接してみると、たとえ誰かが、「歴史的仮名づかひ」が論理的に正しいと主張しても、もはや「現代仮名づかい」の成熟と社会への定着を覆すことはできないと分かる。
<写真は、雑誌『アサヒグラフ』通巻第3470号(朝日新聞社)から転写>
最近の「学芸文化」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事