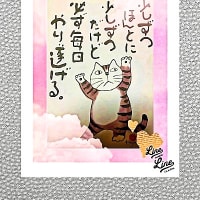二十二年前に、両親と同居するため居宅を新築したとき、基本的には洋風だが、一室だけは八畳の和室にし、框床(幅六尺)・違い棚を備えた床脇(幅六尺)・仏壇(幅三尺)を作りたかった。北海道の普通の民家に縁側はないので、書院は初めから諦めざるを得なかった。
二十二年前に、両親と同居するため居宅を新築したとき、基本的には洋風だが、一室だけは八畳の和室にし、框床(幅六尺)・違い棚を備えた床脇(幅六尺)・仏壇(幅三尺)を作りたかった。北海道の普通の民家に縁側はないので、書院は初めから諦めざるを得なかった。
百坪の土地を購入し、実際に図面で家の構成を考える段になると、様々な制限が重なり、和室は六畳となり、仏壇を外さなければ床の間と床脇に十二尺の幅が取れない。やむを得ず、床の間も床脇も、変則の四尺五寸幅とした。空間の広がりが一尺五寸分少なくなったため床脇の天袋を省いたのはよかったが、採光のために洞口を開けるべきだった。
床脇の地袋上にあまり飾り物を置かず空間に余裕を持たせたいが、布袋も熊も両親が用意してくれた自慢の木彫りなので、しばらくはこの状態が続くだろう。床飾りの作法を知らないわけではないが、この正月は事情があって、床の間に軸を掛けなかった。
 居間の神棚には、暮れの三十日に、厳島神社の新しい御札を入れ、前面に小さなゴボウジメの注連飾りを掛けた。玄関には昭和六十二年の居宅新築以来、おかめの注連飾りが定番になっている。
居間の神棚には、暮れの三十日に、厳島神社の新しい御札を入れ、前面に小さなゴボウジメの注連飾りを掛けた。玄関には昭和六十二年の居宅新築以来、おかめの注連飾りが定番になっている。
なにかで「二十八日に飾るのが本来の仕来りで、三十日も良しとする」と、読んだ気がする。わが家では、二十八日に釧路駅前北大通の〈さくらい生花店〉で購入し、その日か三十日に飾るのが常である。ま、些事にこだわらず気楽に考えたい。
最近の「行住坐臥」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事