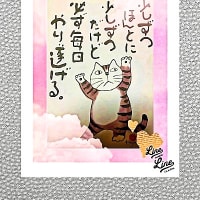小学生の頃から、田舎家の近くを流れる斜里川水系の支流で、オショロコマ・アメマス・ヤマベ・イトウを釣っていたので、知識や技術を別にして、単純に年数だけでいえば、川釣り歴五十五年ということになろうか。イトウは釣れる数が少なかったため、銀色に鱗が光る魚体を手にする喜びは格別だった。
小学生の頃から、田舎家の近くを流れる斜里川水系の支流で、オショロコマ・アメマス・ヤマベ・イトウを釣っていたので、知識や技術を別にして、単純に年数だけでいえば、川釣り歴五十五年ということになろうか。イトウは釣れる数が少なかったため、銀色に鱗が光る魚体を手にする喜びは格別だった。
中学生になると、二里から三里くらいまで行動範囲が広がり、主にヤマベを狙って、支流のさらに支流へと、徒歩で奥山に単独行をした。他人に釣りのペースを乱されるのが嫌だったのである。
昭和40年に就職してからは、春分の日をヤマベの釣り初め(つりぞめ)とし、文化の日が竿納めだった。上の写真は、昭和51年3月20日(土)<春分の日>の記録である。好天で風もなく、申し分のない釣り日和だった。
林道は雪に埋もれているので、ゴム長靴に父の手製のテシマ(父はカンジキとは言わなかった)をはめて田舎家を八時に出発。春の固雪の上を目的の沢まで、三里の距離を二時間半で歩くのは重労働だった。
目的地に着くと、特長に履き替え、テシマとゴム長靴をザックに入れ、川に降りる。ザックには、昼食・非常食・着替え・固形燃料・ザイルなどが入っていて、かなりの重さになる。
さぁ、開始だ。鉛を軽めにして糸をポイントに流すと、三寸くらいのヤマベが雪の下からサッと姿を見せ、餌のイクラに食いつく。まだサビが残っているが、元気いっぱいである。いつまでも釣っていたいが、三時間が限度。好天でも午後は急速に気温が下がるので、川から上がる。両岸はまだ積雪が多く、上がる場所を見つけるのに難儀した。
夕食時は、ヤマベの天麩羅を肴に、熱燗の剣菱が冷え切った体を心地よく温めてくれる。両親がまだ田舎家に住んでいた、三十年も前のことである。
最近の「自 然」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事