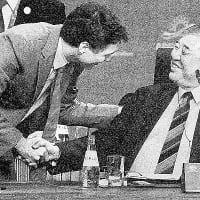いささか旧聞に属さないでもないが、6月28日付『讀賣新聞』第2面〈総合〉に、大きく「世界の人口66億人」と見出しの付いた小記事が掲載されている。国連人口基金による2007年版「世界人口白書」の紹介である。上位三か国は、常連の中国・インド・米国。人口の急激な増加に加えて、その半数以上の約三十三億人が都市部で暮らすようになり、今後ますます増加する見通しを示し、この人口変動がもたらす問題点を指摘している。
いささか旧聞に属さないでもないが、6月28日付『讀賣新聞』第2面〈総合〉に、大きく「世界の人口66億人」と見出しの付いた小記事が掲載されている。国連人口基金による2007年版「世界人口白書」の紹介である。上位三か国は、常連の中国・インド・米国。人口の急激な増加に加えて、その半数以上の約三十三億人が都市部で暮らすようになり、今後ますます増加する見通しを示し、この人口変動がもたらす問題点を指摘している。
私が中学校に入学した昭和30年には、世界の人口は二十六億人だった。社会科の授業で、「世界の自然と地理」を学んだとき、生まれて初めて、郵便振替なるものを利用して、東京の版元に注文した参考書に、「世界の人口は二十六億人」と記されていたのを今でも忘れない。
讀賣新聞社編集局編『20世紀のドラマ・現代史再訪1』(東京書籍)に、「中国の人口爆発」という項があり、昭和四十年に、エドガー・スノーの問いを受けて、毛沢東は、「知らないのだ」と答えた、と記されている。「四半世紀後の九〇年七月、第四回人口調査が行われ、中国の人口は、日本の十倍近い十一億三千三百六十万人と発表された」とあるから、大陸の中国人に限っても、当時の世界人口(約五十億人)のうち、五人に一人は中国人だったことになる。ちなみに、中華人民共和国が成立した昭和24年の人口は、五億四千万人だった。まさしく「人口爆発」という言葉にふさわしい「大増加」であり、私には、毛沢東の「大躍進」政策と、二重写しに見えるのである。
リチャード・G・クライン、ブレイク・エドガー『5万年前に人類に何が起きたか?意識のビッグバン』鈴木淑美訳(新書館)は、二足歩行の人類は、六百万年前、アフリカの類人猿から分かれ、複数のアウストラロピテクスに進化し、その後、生き残った一種、ホモ・サピエンスのみがアフリカを出て、ユーラシアの非現生人類を駆逐して現在に至った、という考えを定説として示している。一人勝ちのホモ・サピエンスも、中生代の大恐竜のように、すでに地球を食いつぶすまでに増殖しすぎたのではないか?
最近の「政治経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事