七尾旅人 "兵士Aくんの歌" (映像作品『兵士A』より)
Fairground Attraction - Clare
優河 with 魔法バンド / fifteen live session at キチム fifteen (live session) by Yuga with Maho Band
六月の詩
"The Longing" - Patty Gurdy (Hurdy Gurdy Music)
(ちんちくりんNo,82)
それから一年後、2004年の春には僕ら一家は山梨に移り住んでいた。自宅は二階家、100坪程の土地に半分は住宅に、残りは庭とした。出来るだけ自然に近いところが良かろうと、「白州・尾白の森公園」に近い町の外れに住んだ。僕の実家からは車で40分かかる。僕はその地に住むために、それまで残っていた自分の貯蓄のほぼ全てを費やした。不安はあったが、私立高校の教員という定職を得たことでかえって心の安寧は保たれた。
教員試験は、最初は応募者多数のようで危ぶまれたが、面接で僕が(あの)作家の神海人だということが判明したことで、決まったようだ。恐らく「客寄せパンダ」になると踏んだのだろう。初めての授業のとき、黒板に文字を書き込むのに一瞬躊躇したが、思い切って白墨を黒板に当ててみると、自分でも意外なほど流暢に手が動いた。勿論小説を書くわけではなし、手が震えることはないだろうと思っていたが、「もしも」のことを考えていたので、それは僕にとってとても喜ばしいことだった。
薫子は地域の子供らと馴染むだろうかと心配したが、それどころかいつのまにか自らが率先してその子らをまとめるような存在になったようだった。喘息の気配は移り住んでからまるで表れていなかった。やはり空気の質が良かったのだろう。
裕子は薫子が小学校に上がるとともに、地元の新聞社に契約社員として雇われ、文芸部へ配属された。仕事は、新聞の文芸欄に載せる本の紹介だとか、作家、評論家とのやり取りだとか、新聞小説の編集だとか、まあそんなところだ。僕が、新聞社なんて、よくそんな仕事の募集があったもんだなと訊くと、苦笑いしながら「分かってるでしょ?」と応えた。ああ、龍生書房のつてか。僕も苦笑いした。
かほるの幻影は薫子の入院以来、見ることも感じることもなくなった。僕は山梨に来てから、゛あの物語″を書く意欲をなくしていた。いや、そもそも作家を続けて行くことさえ、考えなくなっていた。だから、きっとかほるにまた悩まされるに違いないなと心の奥底で構えていたのだが、いつになっても一向にその気配はなかった。それは考えてみれば当たり前のことだった。何故なら小説を書くことは、言わばかほると対峙するための手段なのだったから。その手段を捨てた僕のもとに彼女が現れるはずがなかったのだ。きっと僕はずっと間違っていたのだろう。
Fairground Attraction - Clare
優河 with 魔法バンド / fifteen live session at キチム fifteen (live session) by Yuga with Maho Band
六月の詩
"The Longing" - Patty Gurdy (Hurdy Gurdy Music)
(ちんちくりんNo,82)
それから一年後、2004年の春には僕ら一家は山梨に移り住んでいた。自宅は二階家、100坪程の土地に半分は住宅に、残りは庭とした。出来るだけ自然に近いところが良かろうと、「白州・尾白の森公園」に近い町の外れに住んだ。僕の実家からは車で40分かかる。僕はその地に住むために、それまで残っていた自分の貯蓄のほぼ全てを費やした。不安はあったが、私立高校の教員という定職を得たことでかえって心の安寧は保たれた。
教員試験は、最初は応募者多数のようで危ぶまれたが、面接で僕が(あの)作家の神海人だということが判明したことで、決まったようだ。恐らく「客寄せパンダ」になると踏んだのだろう。初めての授業のとき、黒板に文字を書き込むのに一瞬躊躇したが、思い切って白墨を黒板に当ててみると、自分でも意外なほど流暢に手が動いた。勿論小説を書くわけではなし、手が震えることはないだろうと思っていたが、「もしも」のことを考えていたので、それは僕にとってとても喜ばしいことだった。
薫子は地域の子供らと馴染むだろうかと心配したが、それどころかいつのまにか自らが率先してその子らをまとめるような存在になったようだった。喘息の気配は移り住んでからまるで表れていなかった。やはり空気の質が良かったのだろう。
裕子は薫子が小学校に上がるとともに、地元の新聞社に契約社員として雇われ、文芸部へ配属された。仕事は、新聞の文芸欄に載せる本の紹介だとか、作家、評論家とのやり取りだとか、新聞小説の編集だとか、まあそんなところだ。僕が、新聞社なんて、よくそんな仕事の募集があったもんだなと訊くと、苦笑いしながら「分かってるでしょ?」と応えた。ああ、龍生書房のつてか。僕も苦笑いした。
かほるの幻影は薫子の入院以来、見ることも感じることもなくなった。僕は山梨に来てから、゛あの物語″を書く意欲をなくしていた。いや、そもそも作家を続けて行くことさえ、考えなくなっていた。だから、きっとかほるにまた悩まされるに違いないなと心の奥底で構えていたのだが、いつになっても一向にその気配はなかった。それは考えてみれば当たり前のことだった。何故なら小説を書くことは、言わばかほると対峙するための手段なのだったから。その手段を捨てた僕のもとに彼女が現れるはずがなかったのだ。きっと僕はずっと間違っていたのだろう。

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


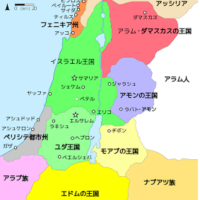






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます