David Bowie - Imagine (Live at the Coliseum, Hong Kong, 8th December 1983) [4K]
かびん (Remaster) 吉田美奈子
ダンスが終わる前に〈Before the dance is through〉/伊豆田洋之
Keane - Everybody's Changing (Live)
U2 - Lemon (Official Music Video)
(ちんちくりんNo,73)
実は、というと何だか告白めいた言い方になるが、僕は初対面から裕子に対してある感情を持った。一目惚れといったような恋心ではない。どう表現をしたらいいか分からないが、既視感を伴うなにものか。「確かに憶えがあるが如何にしても思い出せない」という一種の違和感であるが、もしかしたら"ノスタルジー"といったものに近いのかもしれない。もっとも、「思い出せない」のであるから普通「思い出し考える」"ノスタルジー"とは矛盾することにはなると思うが。
ともかく僕は思い出せないが、失われた何かに対する「懐かしく胸が痛む」ような感情を初対面の裕子に対して抱いたのだった。
裕子は聡明で合理的な面を持ち合わせていた。その癖感性が豊かで時に感情的になることがあった。例えば原稿の依頼にしても端的に分りやすく説明でき、無駄と判断した場合僕の要求は一切受け付けない。しかし、僕が原稿を書き進めている時に突然現れたかと思ったら、僕の処女作を読んだとかで延々とその感想を述べ、終いには「何故このような小説を書かないのですか」と言う。僕としてはそろそろ今までの自分の傲慢さに気づき始め、まずは"龍生"に書く原稿は、そのようなありったけな自分の想いを詰め込んだ小説を書きたいと初めに説明したはずなのにと思い、「だから言っただろ」と声を荒げると途端にむくれるのである。僕は「こいつはAB型なのかしら}と思ったものだ。
ただ、そのような裕子との出会いが契機となり、僕は流行作家という仮面を脱ぎ、テーマを絞って自分が忘れかけていた「何か」を書き続けていこうと決心したのは確かであった。その意味では僕は裕子に感謝しなければならない。
その後、僕の小説は以前ほど売れなくなった。「売れない神海人は価値がない」と思ったのか知らないが、群がっていた出版関係者は嘘のようにひいた。後に残ったのは龍生書房とあと一、二社くらいだった。でも、小説を書くための時間が増えたことは初心に帰ろうと考えた僕にとってはとても喜ばしいことであった。
裕子の国籍がアメリカ合衆国にあると聞いたのは、裕子が僕の一つ下の年齢で、龍生書房の前はニューヨークのファッション雑誌の編集者をしていたという話になった時だった。
「その割にはあか抜けないな」
しまった、と思ったときには時すでに遅く、裕子はむくれ、そこからまったく口をきいてくれなくなった。
服装は確かにあか抜けなかった。けれども彼女は長身で墨のように黒く長い髪の、大きな瞳が妙に輝く持ち主だった。そんなこと言うつもりはなかったのにな。僕は反省した。
それでも変わらず、僕はよく彼女に皮肉めいたジョークを口にした。彼女も当然のごとくそれを逆に良い方に捉えるようになっていった。それはもう作家と編集者という垣根を飛び越えて"友"のような関係性になったことを意味する。その友のような関係性が徐々に変化していき、最終的に彼女を"大人の女"として意識したとき僕は彼女に結婚を申し込んだ。僕が三十六歳、彼女が三十五歳になる年のことだった。
「私も出来たらそうしたい。でもそうすることに一つだけ私には、割り切れない気持ちがあるの」
「それは何らかの壁のようなもの?」
「壁……。そうね、その気持ちの理由を話せば多分あなたも私と同じ気持ちになると思う」
「いいよ、話してくれ。それは何」
それに対する彼女の応えを聞いた僕は愕然とした。そしてあの初対面の時の"既視感"の謎がこんな形で解けるなんて、とその運命のいたずらに恐怖感すら感じた。
彼女、湊裕子は"かほる"の実の姉だったのである。
かびん (Remaster) 吉田美奈子
ダンスが終わる前に〈Before the dance is through〉/伊豆田洋之
Keane - Everybody's Changing (Live)
U2 - Lemon (Official Music Video)
(ちんちくりんNo,73)
実は、というと何だか告白めいた言い方になるが、僕は初対面から裕子に対してある感情を持った。一目惚れといったような恋心ではない。どう表現をしたらいいか分からないが、既視感を伴うなにものか。「確かに憶えがあるが如何にしても思い出せない」という一種の違和感であるが、もしかしたら"ノスタルジー"といったものに近いのかもしれない。もっとも、「思い出せない」のであるから普通「思い出し考える」"ノスタルジー"とは矛盾することにはなると思うが。
ともかく僕は思い出せないが、失われた何かに対する「懐かしく胸が痛む」ような感情を初対面の裕子に対して抱いたのだった。
裕子は聡明で合理的な面を持ち合わせていた。その癖感性が豊かで時に感情的になることがあった。例えば原稿の依頼にしても端的に分りやすく説明でき、無駄と判断した場合僕の要求は一切受け付けない。しかし、僕が原稿を書き進めている時に突然現れたかと思ったら、僕の処女作を読んだとかで延々とその感想を述べ、終いには「何故このような小説を書かないのですか」と言う。僕としてはそろそろ今までの自分の傲慢さに気づき始め、まずは"龍生"に書く原稿は、そのようなありったけな自分の想いを詰め込んだ小説を書きたいと初めに説明したはずなのにと思い、「だから言っただろ」と声を荒げると途端にむくれるのである。僕は「こいつはAB型なのかしら}と思ったものだ。
ただ、そのような裕子との出会いが契機となり、僕は流行作家という仮面を脱ぎ、テーマを絞って自分が忘れかけていた「何か」を書き続けていこうと決心したのは確かであった。その意味では僕は裕子に感謝しなければならない。
その後、僕の小説は以前ほど売れなくなった。「売れない神海人は価値がない」と思ったのか知らないが、群がっていた出版関係者は嘘のようにひいた。後に残ったのは龍生書房とあと一、二社くらいだった。でも、小説を書くための時間が増えたことは初心に帰ろうと考えた僕にとってはとても喜ばしいことであった。
裕子の国籍がアメリカ合衆国にあると聞いたのは、裕子が僕の一つ下の年齢で、龍生書房の前はニューヨークのファッション雑誌の編集者をしていたという話になった時だった。
「その割にはあか抜けないな」
しまった、と思ったときには時すでに遅く、裕子はむくれ、そこからまったく口をきいてくれなくなった。
服装は確かにあか抜けなかった。けれども彼女は長身で墨のように黒く長い髪の、大きな瞳が妙に輝く持ち主だった。そんなこと言うつもりはなかったのにな。僕は反省した。
それでも変わらず、僕はよく彼女に皮肉めいたジョークを口にした。彼女も当然のごとくそれを逆に良い方に捉えるようになっていった。それはもう作家と編集者という垣根を飛び越えて"友"のような関係性になったことを意味する。その友のような関係性が徐々に変化していき、最終的に彼女を"大人の女"として意識したとき僕は彼女に結婚を申し込んだ。僕が三十六歳、彼女が三十五歳になる年のことだった。
「私も出来たらそうしたい。でもそうすることに一つだけ私には、割り切れない気持ちがあるの」
「それは何らかの壁のようなもの?」
「壁……。そうね、その気持ちの理由を話せば多分あなたも私と同じ気持ちになると思う」
「いいよ、話してくれ。それは何」
それに対する彼女の応えを聞いた僕は愕然とした。そしてあの初対面の時の"既視感"の謎がこんな形で解けるなんて、とその運命のいたずらに恐怖感すら感じた。
彼女、湊裕子は"かほる"の実の姉だったのである。

















![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/f5/92393401bdbc0a86905caa6f8f33ec10.jpg)
![アイナ・ジ・エンド - 帆 [Official Music Video]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/35/7c/21f0d773d7635daee13341c7a29e3a9f.jpg)


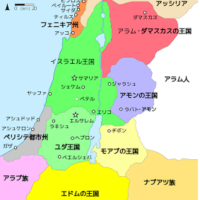






そうなんです。
それ、最終までひっぱって、それとなく示唆をして物語を終えるという形にしようかと思っていたのですが、それだと少し消化不良のまま終わってしまうような気がしました。それで思い切ってここで明かしてしまおうかと。
いつも良い感想をいただきありがたく思っております。(*^_^*)
編集者の裕子さん、かほるのお姉さんだったのですか。
面白い展開ですね。