熱暑がいまだ続き、そしてまたまた大型台風の襲来。
そんな騒ぎのあいまに、持病の悪化だという理由で、首相の突然の辞任があり、それに被さるように、〝かわいそう〟〝よくやってくれた〟といった、どこにも理性的な根拠など見いだせない、砂糖蜜がたっぷりかかった上っ調子の情緒という同情がネットでは飛び交うさまがあって、人はなぜ、こんなときはかったように〝いい人ぶる〟のかなと。いい人ぶる狡猾さは、無自覚ときているから始末におえないのだけども・・・。
そして、辞任後の政界は、〝森・加計・サクラ〟に〝河井〟の腐臭を消すことに躍起で、「暗黒政治」のような隠蔽工作の勝った〝談合〟政治が〝粛々と〟おこなわれ、〝地味〟が売り物という、しんねりとした顔つきのした宰相が登場しそうな勢いです。
いっぽう、コロナ感染接触アプリ「ココア」のひろがりもあるのか、「コロナウイルス禍」の波が、身近にも寄せてきている感じがしてならないここ数日、そしてコロナ禍の対策はもう尽きた感のある倦怠感のなか、そんなさまざまな灰色がかった騒動を横目で見ながら、わたしは、その間、思いかえしたようにずっと中島敦の小説を読み続けていました。 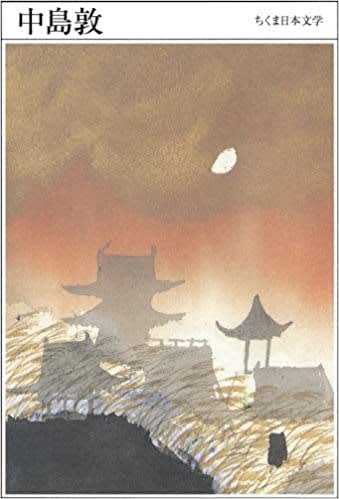
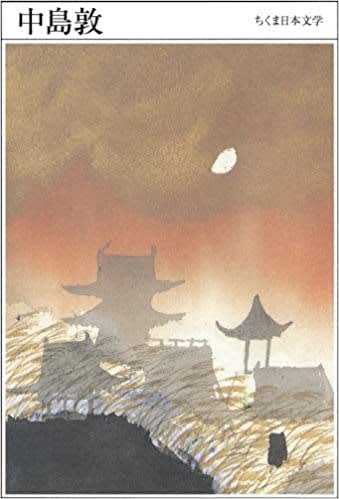
なぜ中島敦か。
よく知られているように中島敦は34歳で夭折した小説家。彼が小説を書き続けていた時代とは、ちょうどカツカツと鳴らす居丈高な軍靴の音が街中に響き渡っていた1930年代から対英米戦の戦時下の時代でした。
いわば「暗い時代」。そして、1942年(昭和17年)12月、重い喘息のために、中島敦は短い生涯を遂げます。
ですからその短い生涯を考えると、そんなに知られた作家であるはずはないのに、にもかかわらず、中島敦は比較的多くの人びとに膾炙した作家と言えるように思います。
その理由は、おそらく戦後の多くの高校の国語教科書などに、彼の『山月記』や『李陵』といった作品が掲載されていて、それがおしなべて退屈である国語教科書のなかで、あたかも雪舟の『秋冬山水図』のように、凜とした風采を醸しだし、じつに厳しく周囲に屹立した印象を与えてくれているからだと思います。
言葉を換えると、中島敦の小説は、定期試験だの受験勉強でいくら点数を取るかなどといったありきたりの〝狡知〟な俗っぽさを一瞬にして叩きのめすばかりか、その特異な小説世界は異次元に吸引されたような感覚を与え、それと同時に、漢文調の格調高い整った文体が、シャンと背筋が伸びるような「精神」の清冽さを、弥が上にも感じさせてくれるものであるからでしょう。
それが、聖俗の狭間に揺れている青春期を迎えた多くの若者に、深くどこまでも、中島敦を記憶させている。
そして、そのありようは、魯迅の小説を読むときにも感じさせてくれるものでもあるようです。
ただし、それは両者に、中国を舞台にする小説があるといったことなどではなく、もっと深くも高くもある意味で、この二人の作家には、一本の「紐帯」があたかも存在しているかのようなのです。
<魯迅>

この文学者たちには、格調高い文体も含めて、凜とした「精神」への真摯な問いかけが鮮烈に屹立している印象があります。
しかもそれが歴史のなかで、「超時代的な文学」として大河のように流れている。それがこの二人の文学者を貫く「紐帯」のように感じられる。あえていえば、孤高である美しさと言ってもいいのかもしれません。
人はつねに日常の凡悪に囲まれているという憂いを抱いているように思います。その凡悪のケガレから逃れたい。青く澄明な世界に住みたい。
ですから、世間の不正に倦んだとき、あるいは怠惰に流れるとき、そして意に染まぬことに嫌悪を感じるとき、どうしても高く澄んだ蒼穹を追い求める自分自身を見いだすことがあります。そんなとき、中島敦と魯迅のいずれかの一書を手にしている。
わたし自身が、中島敦と魯迅を読みたいと思うのは、畢竟そんな心境のときのようです。
ところで、中島敦の小説群には、まだまだ読まれていない多くの多様な作品があります。
中島敦は、子ども時代から少年期を、植民地であった朝鮮半島や日露戦争後の租借地であった中国の大連で過ごしています。そして対英米戦争の戦時下に、当時日本の委任統治領だったパラオ南洋庁に赴任したこともあって、私小説の世界や社会主義リアリズムの閉じこもった世界から出ることのなかったこの時代の日本の小説家とは、まったく異質な文学世界を創生しえた土壌がありました。
しかし、ただいわゆる「外地」経験があるからといって、それで小説を書いても、多くはエキゾチシズムに堕してしまいかねない。中島敦の「文学世界」の驚くべきこととは、この時代にあって、「日本」という箱庭的な次元を越えて、「他者」への眼差しや安易な理解を拒絶する「異者」の不可知性をいかに描き出せるかの問いがつねにあり、それとともにいく時代も貫く人間の意識や思考の〝共時性〟を見いだそうとする「文学思想」が深く内在していることにあるかと思われます。
中島敦の作品には、一見、善意のような顔をしてのさばる差別の悪意とその愚昧な狡猾さ、あるいは優越感に浸る国家や民族が、いかに無辜な人びとに強圧的に「他者」を押し付けているかといった主題のものがいくつかあります。
とくに南洋譚には、そうした作品が多いのですが、中島敦はそれをあからさまに告発するものとして描くのではなく、まずは、つねにそうした「他者」の前にあって、自己自身が「他者」であり「異者」としてあることを問うている姿勢が見られます。むしろ、自己に内在するより根深いところ、黒い闇にじっと息を潜めてあざ笑っている卑怯を見詰める視座から、「他者」である自己を問う。そして、その問いのなかから現れる痛みを痛みとする精神の清冽さを文学として表現する。
とりわけ、日本の朝鮮植民地統治下における若い朝鮮人巡査の懊悩と恨を描いた『巡査の居る風景』は、民族とは何か、国家の意味とは何か。朝鮮半島における支配と差別の鋭い切り傷を描き出した、なかなか衝撃的な作品ですが、そこでも「他者」としての痛みが重く基底低音のように響いています。
しかもなにより驚くべきことは、この作品が、中島敦がまだ20歳のときに書いた作品だということです。
なんという感性なのか。そう思わずにはいられません。それはたしかに早熟といえば早熟なのですが、この小説はじつに落ち付いた筆致で描かれていて、じゅうぶんに練り上げられた構想の存在を感じさせます。そこで比較しても仕方がないことかもしれませんが、若さゆえの感性に居座り、才気走った筆致で風俗を描写することに長けた現代の日本の若手作家の内実の薄っぺらさが、この作品を読み込むと、むしろ浮き出てくる。
言い換えるなら、若かりし中島敦は、つねに〝根柢〟に潜む何かに問いを発し、そこから「文学」を創生しようとしている。それに対して、生きづらさや自傷、性を描くのに熱心な「近ごろ」日本の若手作家には、どこか表層で、流行じみて、〝根柢〟を感知しようとしていないのではないか。そんな気がします。
<1919年三・一独立運動堤岩里事件の碑>

中島敦には、ほかにも、ラテンアメリカの代表的な作家であるホルヘ・ルイス・ボルヘス(Jorge Luis Borges)のまさに迷宮に彷徨い込んだような怪奇で幻想的な作品にまがう『文字禍』や『憑狐』、『木乃伊』といった作品がありますし、自己への疑問と何故に自己が存在するのかを突き詰めようとする妖怪である沙悟浄(『西遊記』)の思惟の動き動揺を描いた『悟浄出世』と『悟浄歎異』など、怪奇や脅威、奇譚といった世界を、ほぼ同じような年齢で早世した芥川龍之介とは違った、世界的な作品や視覚や聴覚をも駆使したじつに「知性的」な作品が多くあります。
思うに、戦時下で中島敦は、その感性をどのようにして身に纏ったのか。そのあたりについては、今後、読み込んでいくなかでわかることもあろうかと思いますが、いずれにしても、中島敦の小説はまだまだ読み込まれていくべき作品が数多くあるというわけです。
そんな中島敦の小説を、ここ数日の灰色がかった憂鬱な日々に、一文一文に目を凝らして読んでいって、なかでもひときわ奥底深くまで入り込んできた作品のなかに『弟子』という小説がありました。
この小説は、これまで何度も読んでいるはずでしたが、なぜか読んだあとに、さまざま思惟をめぐらすことになっていったというわけです。
話しは、孔子の弟子である子路の目から見た師である孔子の「思想対話」という形を取った小説と言っていいでしょう。
小説の話題に行く前に、すこしさかのぼっての話しをします。
わたしが高校生だったころ、そのころ『論語』などの儒教思想は、固陋な王侯哲学であり、その内容は陳腐で、じつに取るに足りない道徳の強制だと、とりわけ早熟なマルクスボーイたちに大いに批判されたことを思い出します。
当時のいわゆる中核派や革マル派、秋田には第四インターというセクトもあって、これがこのころ秋田大学自治会を握っていたらしいのですが、わたしたち高校生は、そんな秋田大学のマルクスボーイ学生から、彼らの属する「新左翼」思想の洗礼を受けさせられ、そんなとき『論語』などを持ち出すと、いっせいにその凡俗な封建思想を自己批判しろと大いに叱られ、罵倒されたりしたものでした。
そんななか、1960から70年代に青春期を迎えていた方々には、覚えもあることかと存じますが、そうした未熟なマルクスボーイたちが憧憬し、おおいに信奉していた作家に高橋和巳がいました。
高橋和巳はこのとき、京都大学の助教授で中国文学の専門家でしたが、高橋和巳は孔子について、こんなふうに語っていたわけです。
孔子とは、・・・要するに日々の生活の知恵みたいなものを与えているだけで、大議論は一つも述べていないのです。世界の極楽を描いているわけでも、人類の救済を夢想しているわけでもない・・・。虎に素手で立ち向かったり、河を歩いて渡ったりして死んでもかまわないなどという男には組みすべきではない・・・そんなことが述べられている・・・(『ふたたび人間を問う』1968年)。
いわば当時の人びとの知恵の蓄積がそこにはあるわけであり、たとえば「中庸」という言葉も、左右のいずれではなく真ん中を採るといった浅薄なものではなくて、いかにそれぞれの主張や固執を解きほぐし、均衡を取るものという思想だとする。
<高橋和巳 京大闘争のなか>

たしかに『論語』は、その後の時代で政治権力によって権威化されていく過程で、その道徳律がきわめて狭隘なものに歪められていきますが、じっさいの『論語』をよく読むとわかると思うのですが、そこには権威も封建道徳もあるわけではなく、せいぜいで「神を媒介とせずに人間同士がうまくやっていこうとすれば、どうしても礼儀なしではしょうがない・・・」(前掲)といった「礼」についても常識的なことが、地中から掘り出したかのように説かれているだけなのです。
それを思うと、秋田にいた性急なマルクスボーイたちは、おそらくハナからバカにして『論語』などは読んでなかったのでしょう。それで一方的に批判していただけだった。
それはいまどきのインテリ崩れの小賢しさを誇る、匿名でしか悪意を示せない「ネットの住人」も同じことなのかもしれません。世の中、いつの時代も結局そんなもんなんだと、思わずあの当時を思い出してしまうというわけです。
中島敦の『弟子』という小説は、その意味でも、じつに『論語』を読み込んだ上で書かれた小説と言っていいでしょう。
孔子や子路の生きた中国春秋戦国時代は、まさに裏切り、不信、憎悪、譎詭 、暴虐の乱世そのものの時代でした。
そのなかで孔子は、為政者に道を諭し、常識に裏打ちされた知恵を語り、乱世の止むをはかるとともに、学の必要を説き、放恣な性情を矯める教えを説いて、しかし、その多くは王侯には受け入れられることなく、そのため不遇を託ち、弟子たちを率いて長い放浪のなかにいた人物でした。
小説のなかで、子路は師である孔子について、つぎのように語っています。
・・・このような人間を・・・見たことがない。力千鈞の鼎を挙げる勇者を・・・見たことがある。明千里の外を察する智者の話も聞いたことがある。しかし、孔子に在るものは、決してそんな怪物めいた異常さではない。ただ最も常識的な完成に過ぎないのである。知情意のおのおのから肉体的の諸能力に至るまで、実に平凡に、しかし実に伸び伸びと発達した見事さである。一つ一つの能力の優秀さが全然目立たないほど、過不及無く均衡のとれた豊かさは・・・初めて見る所のものであった・・・。(『弟子』 ちくま日本文学 2008年)
その孔子の姿は、まさに『論語』に映し出された孔子そのものだと言えます。つねに激化することを避け、極端に傾かず、民衆の生活がそうであるように、貧困や悲哀のなかにあっても「共苦」「共悲」を頼りにしながら、他者とともに暮らしていく。その暮らしに生きる。
中島敦は、作品のなかで、そうした精神の現れたものを孔子は「中庸」と述べているとし、孔子こそは、優れて「いついかなる場合にも夫子の進退を美しいものにする見事な中庸の本能」を持つ人物だとしています。
孔子が子路に説いた言葉。これも『論語』に述べられていることなのですが、「古の君子は忠をもって質となし仁をもって衛となした。不善ある時はすなわち忠をもってこれを化し、侵暴ある時はすなわち仁をもってこれを固うした。腕力の必要を見ぬゆえんである。とかく小人は不遜をもって勇と見做し勝ちだが、君子の勇とは〝義〟を立つることの謂である」(前掲*〝〟は著者の註)
ここで述べられている「義」とは、民族や人種、性別や国家に関わりなく、だれにでもどこでも通用する「通義」のことを意味しています。
いわば理不尽な暴力や金力で相手を黙らせる。事実や真実を虚偽(フェイクfake)で糊塗する。あるいは「全く問題ない」「批判は当たらない」「指摘は当たらない」と問題の本質を隠蔽し不遜にも「通義」を貶める。そしてそれを「勇」と見做して平然としている。
こうしたことは「小人」のありようであり、「君子」のとるべき姿ではないと孔子は述べているわけです。見事なまでの「常識」論というわけです。
繰り返しになりますが、孔子の思想は、いわば人びとの知恵によって形作られてきた「常識」から生み出されたものであり、さまざまな事象のなかで、いかに均衡(balance)をとっていくかというものでした。
中島敦はそれを孔子に備わっていた「超時代的使命」なのだと記して、この小説のラストシーンに話を進めていきます。
このあとの展開は、ぜひこの作品をお読みいただければと思うのですが、たしかに孔子の思想をたどるなら、歴史のなかで、あるいは幾世代もの重なりのなかで、わたしたち人間が培い集積してきた知恵があるはずだ。それを見据えずして、快刀乱麻の力をあてにしていいものか! この作品を読み返してあらためて再認したのは、そのことであった感があります。
さて、いまのこの時代は「コロナ禍」のなかにあって、分断と格差に傷つき、苛まれている時代だと言ってもいいように思います。
いつしか権力者はとてつもなく強大なものとして聳え立ち、富裕者は貧困者を差別こそすれ、彼らの救済に手を差し伸べようとしない。
「民主主義」という20世紀の政治規律は、結局選挙によって権力を握った多数派が少数者を追いやり、分断を生み出す装置でしかなかったと後世語られるのかもしれない。それだけ、いまの「民主主義」は疲弊している感があります。
アメリカ大統領選挙にしても、半数近くの投票とその意思はドブに捨てられ、せいぜいで権力を握った側は、「じゃ取引しようぜ。ディールdealだ!」と圧力をかけてくる。わたしたちの国も、小選挙区制になって、半数近くが死票となり、それが分断と憎悪を倍加させている。結局、権力と利権のたらい回しが、いま現実に行われているわけです。
そもそも政治とは何のためにあるのか? 〝経世済民〟とは、どんな政治道徳なのか。
歴史の事柄を語ると、もはや古いと揶揄され、歴史に根をもたない新奇さばかりが喧伝されていくなかで、わたしたちは21世紀になって、とんでもない混沌にさしかかっているように見えます。
もしかして、いまの分断と差別、格差は、「民主主義」という制度で克服できるのか。このありさまは、悪意に満ちてばかりの衆愚政治の言い直しではないのか。それもまた歴史のなかでいつか見てきた事柄であるかのような既視感がないでもない。
そんななかで中島敦の『弟子』を読んだことは、大きかったように思います。
さて、長々書いてしまったのですが、最後に「新人会講座」についてのお知らせです。
2020年秋学季講座を10月18日(日)午前10時を初講日にして開講いたします。
講座日は、現在のところ会場である「池ビズ」(としま産業プラザ)を、10月18日、11月15日、11月29日、そして12月13日(予定)のそれぞれ日曜日午前10時からほぼ確保しております。
秋季講座も、「コロナ禍」のなか夏学季同様に4講座の予定です。
講座内容は、現代の思想家として寺山修司(詩人)、宇沢弘文(経済学者)、石牟礼道子(思想家)、大島渚(映画監督)の人物とそれぞれの激動の時代について論考しようというものです。
詳しくは、次回のblog(9月15日)でフライヤーを掲載いたします。それまでしばらくお待ちください。
なお、11月8日には「講外講」として、よく知られた歴史上の人物に謂われのある寺院を探訪する予定でいます。夏学季は鎌倉の古刹を訪ねましたが、いわゆる江戸時代から明治にかけての寺院を訪ねます。ぜひご参加ください!
というわけで、まずは今日はここまで。
台風一過。もう秋です。ここ数年の秋は短いのですけど・・・。
秋来ぬと目にはさやかに見えねども
風の音にぞ驚かれぬる
(藤原敏行『古今集』)
























