とても失礼な書き出しになるかもしれませんが、野添憲治という思想家を知っている人はそう多くはないのかもしれません。
野添憲治は、秋田県の北部に位置する能代という町で、自らの少年時代の体験を捉え直して、その後の「この国」のありようを厳しく見詰め、それらを思想の原点としながら活動した思想家でした。
ちょうど、水俣の風土に自らの思想を染め上げていった石牟礼道子のように、あるいは筑豊炭鉱の辛苦を自身の骨を軋ませるかのように描ききった上野英信といった思想家たちと同じように、野添憲治は1945年夏、国民学校生徒であった自らの眼で敗戦の現実を感知して、その子どもながらに感じた理不尽と卑怯さを、自らの問題として受け入れながら、多くの著作を書き記しました。
野添憲治は、「土着の思想」として括って平気でいる中央のインテリの傲りを厳しく打ち据えながら、能代の町を離れず、つねに人びとの心の歪みに問いを発するかのようにものを書き、ひそやかに発言してきた思想家でした。
派手に自らを売ろうという魂胆などなく、むしろそれとは対局にいて、思想の本来の意味を、純粋に追求する姿勢を崩さない人だったと言えます。
もっとも知られる仕事は、『花岡事件の人たち 中国人強制連行の記録 』(評論社1975年)などの一連の日本とその国民によっての戦争犯罪を見据える仕事でした。

アジア太平洋戦争末期、捕虜に仕立てられ過酷な労働者として日本に拉致された中国人が、秋田県大館市にあった花岡鉱山で強制労働の末、虐待され差別され、死に追い込まれた現実をまさに鑿で時代を穿つように記録し、しかし、それをあたかもなかったことにしようとした戦後の「この国」の傲慢と人びとの卑怯さを剔抉する仕事でした。
野添憲治がはじめて世に問うた本は、『出稼ぎ 少年伐採夫の記録』(三省堂新書 1968年)でした。この本は、この時代の東北の山村に住む若者のつねとして、下層労働者として出稼ぎなどして生きて行かねばならなかった現実を記録したものであって、つねに最下層としておかれることの現実と、そのなかでも人間として生きようとする瑞々しさが人びとの心を拍つ一書と言っていいかと思います。
その野添憲治は、一昨年の2018年4月に83歳で永眠しました。
ここからは敬愛を表すために、「さん」づけでその名を記しますが、生前、わたしは野添憲治さんとささやかなつきあいがあり、野添さんの推薦もあって、鶴見俊輔や丸山眞男、武谷三男らが結成した「思想の科学」の会員となったいきさつがあります。
その縁で、野添さんの追悼文を「思想の科学会報」に書くことになり、もう半年ほど経ちますので、このblogで、野添さんのことをご存じない方にもと思い、その追悼文をみなさんに読んでいただきたく、掲載することにしました。

<生前の野添憲治さん>
ちょうどこの日、わたしの故郷である秋田は「お盆」の時期に当たります。そして、15日は敗戦の日、昭和天皇の終戦の詔勅がなされた日でもあります。そんなことを思いながら、少し長めではあるのものの、追悼の一文をお読みいただければ幸いです。
野添憲治さんの〝微笑み〟
~野添さんとわたしが過ごした時代~
八柏龍紀
野添さんは、微笑みの人だった。人なつっこい話し方をする人だった。
野添さんの話は、いつも微笑みに包まれるようにして現れた。ときとして、それが微笑みの向こう側に大きな暗い陰影を映し出すこともあったが、それでも柔らかで控えめな語り口からは、いつも微笑みが溢れていた。
花岡事件などの苛烈な告発をともなう問題のときであっても、能代の町のボスたちのドタバタとした政治抗争の話であったとしても、戦中の自身の子ども時代の思い出を懐かしげに語るときも、それはあまり変わらなかった。いつも野添さんは肉厚の丸い顔のなかに細い眼を埋めるようにして、ニコニコしながら話しをした。
・・・戦争中、憲兵で政治犯などを激しく取り調べなんかやった人たちは、戦後になって村に帰ってくると、篤農家となった人たちが多いんだな・・・。なんでだべなぁ・・・。
加えると、野添さんの話の結末は、〝どうしてだべな〟〝なんと、そうなってしまったもんなぁ・・・〟という終わり方をすることが多かった。つまり、結論といったことはいわない人だった。それは知識人がデレッタントにふるまう韜晦ではなかった。それでいて、こっちに考えさせるという話し方でもなかった。
なにか自分自身に語りかけるように、人間が作り出す暗闇の底にじっと目を凝らすようにして自問自答している。野添さんはそんな感じの話し方をする人だった。それは、いま思うと野添さんの思想に根を張っていた野添さんの精神のありようそのものだったと思われてならない。
*
野添憲治さんと知り合ったのは、わたしが秋田県能代市にある女子高に転勤した翌年の1983年の秋過ぎのことだったと思う。もちろんそれ以前から、たまに読む『思想の科学』を通じて野添憲治という名は知っていたし、また『無名の日本人』を書き、サークル活動である「山脈の会」を主催している白鳥邦夫さんも知っていた。この当時、白鳥さんは能代工業高校の国語教師だったが、能代にはこんな人びとがいるんだという畏敬の念を持って、遠くから眺めているという感じだった。
わたしが高校教師になるころは、ちょうど日本が1970年代の後半に入った時期であった。1970年代は、蔵相だった福田赳夫が命名した〝昭和元禄〟と丸々と肥え太った膨満期から、何となくすでに予兆はあったものの、日本経済はドル=ショックやオイル=ショックの経済的激動が起こり、その不況感を色濃く尾を引いていたころだった。
ちなみに、わたしが北東北の小都市秋田の高校から東京の大学に進んだ時期は、学園闘争の残り火がちょろちょろと燃え残っていた時期であり、その後、浅間山荘立てこもり事件で象徴的な「連赤事件(連合赤軍事件)」の1972年を過ぎ、消費者物価上昇率が25%近くまでおよんだ〝狂乱物価〟、1974の経済成長率がマイナスに転じた「マイナス成長」を経て、完全失業率が100万人を超えた時期に大学を卒業した。
自宅待機、内定取り消しが当たりまえの時代。1993年から2005年を区切りとされるのちの〝就職氷河期〟と比べると、時期は短かったのかも知れないが、わたしが大学を卒業するころは、言うまでもなく「就職難」の時代であった。
東京三田にある大学の法学部を卒業したわたしは、その後、アルバイトを何件も掛け持ちして生活費を稼ぎ、同じ大学の文学部に学士入学した。さてそのあとを考えたとき、当時の学生を取り巻く環境を含めて俸給生活者になるしか仕方がない。それでもやっとなのだという自分自身の漠然とした〝無力〟さを抱え、「就職難」の時代に直面していた。
そうした時代環境で、わたしより年長の〝団塊の世代〟の大量採用で、当時は狭き門となっていた高校教員だけが、なんとか自分を裏切らない方途だと勝手に思い詰めて、首都圏の高校教員の職を探すのと同時に、高校まで過ごした秋田県の教職員採用試験をうけた。
そして1978年春、なんとか秋田県の高校教員に潜りこめた。いま思うと幸運なことだったのかも知れない。
しかし、秋田に帰っての高校教師。哲学や文学の本を読みたくても、地元の書店にはそんな本はないし、都市生活者が受けるような刺激は希薄である環境はやはり気分的に堪(こた)えるものがあった。
あるとき、東京から友人数人が田舎の学校を見たいと秋田に訪ねてきて、数日過ごすうちに、高校の職員室で教師らが煙草を吸いながら仕事をしているのを見て、お前もまだ煙草を吸っているのかと聞かれ、そうだと答えると、「都会のインテリは少なくとも仕事中は煙草は吸わない。いや、人前で煙草を吸うインテリを見たことがない」とシニカルに笑われた。
その真偽はともかく、彼らと話をしていても、時代の流れから取り残されていくような焦り。都会がまぶしく見えてしかたなかった。インターネットなど想像もつかなかったこの時代。そんな隔てられた距離感が、自分の周囲に一日ごとに蓄積されていくような日常がそこにはあった。
父親は、教員を目指すことに賛成ではなかったのだが、昔風にいうと長男が郷里に帰って就職する。それ自体は理にかなっているとして歓迎してくれた。
表向きは、教員という仕事が合っているからと自分を言い聞かし、なぜ秋田に帰ったのかと聞かれるたびに、あたかもそれが唯一の重大事の如く、自分は長男だから、と答える自分がそこにはいた。
思い返すに、そんな自身の羞恥と後悔を相手に気取られぬように、当時のわたしは教員の仕事に没頭した。校内教員研修会や教材研究会を開いたり、陸上部や放送部などの課外クラブで生徒たちの活躍をともに喜んだり、高等学校の教職員組合で執行役員を務めたりすることで、乖離する恐れを埋めていたのかも知れない。
そして能代農業高校(現能代西高)を皮切りに、十和田高校定時制の教員、そして1982年春に能代市の女子校(能代北高、現能代松陽高校)に転勤し、教員生活六年目を迎えていた時期、わたしは野添憲治さんや白鳥邦夫さんと出逢うことになる。
*
親しくなったのは、白鳥さんが早かった。それは学校は違っていたが、同じ能代市内の高校教師同士だったからである。だが二人のことではじめに印象に残っているのは、白鳥さんと知り合いになってのちの教員組合の能代の地区研修会の会場でのことだった。その研修会の講師は野添さんであった。そのなかで白鳥さんは短い挨拶をした。
もとより長野県生まれで、東大倫理学科を卒業された白鳥さんはいつも秋田の方言などに寄りかからない語り口で話をした。それはともすれば地元に迎合して地元化することで親密圏をつくって、それに阿ねることの多いありかたと異なるある一つの態度であると思った。そんな白鳥さんの言葉は、つねに知性的な響きを湛える言葉となってわたしのこころに落ちていった。
「教師とは何か?」。白鳥さんは、たしかタゴールの言葉にある、「教えることの主な目的は、意味を説明することではなく、心の扉をたたくことなのだ」という一文を引いて教育の意味を語った。
そのあとで野添憲治さんの講演があった。もしかするとその順番は逆だったかもしれないが、野添さんは、そこでも丸い顔に朴訥な微笑みを浮かべ、顔の中に眼を埋めるようにして、ニコニコと語りだした。秋田訛りの強い温かみのある言葉で、講演ははじまった。
やわらかい知性。それは白鳥さんと対比的な意味ではない。白鳥さんの思想や知性は、教条主義的な過ちを乗り越えて、自由に闊達に、そして柔軟に思考を積み重ねていくという風情がある。
それに対して、野添さんは、むしろ剛直な根というものが話しの端々に張られている。しかし、語り口は、田舎のじいさんばあさんにも、うんうんと思わせる、親しみのこもった柔らかさがある。
「いやぁ、なんとしたらえしべな?」(どうしたらいいんでしょうね)。そうした言葉のなかに思想が詰まっている。
野添さんの話は、いまどきの子どもを取り巻く家庭のあり方についてのものだった。家庭というものが、経済的に夫婦共稼ぎを余儀なくされている現実では、むしろ子どもを含め家族のなかで、各自がよく話をして、それぞれが自立するように持っていかないと、崩壊を余儀なくされるのではないかという話だったように思う。家族内で、家族だからといってもたれ合わずに、すこしでも話し合うってこと。「そうしたことが大事でねが、と思うわけだす」(そんなことが大事ではないかと思うわけです)。
そのとき、共働きで忙しい家庭では手のかからないように、もはや料理は包丁で行うものではなく、レトルト食品だけでの食事は、はさみですべてが行われる。野菜も刻まない、魚も焼くことがない。肉もはさみで切る。いまとなっては、そんなに不思議ではない現実であるのだが、このときは会場のあちこちで乾いた笑いが起こった。
講演会が終わって懇親会が開かれた。野添さんは、つぎの用事があるということで、不在だった。白鳥さんは、たしかその場にはいなかった。そのなかで、能代市にある能代高校、能代商業、能代工業、能代農業、能代北高(女子校)、二ツ井高校の各先生たちと話をしているうちに、教師たちは、今日の講演会の批評をはじめた。
白鳥さんの話は「毒にも薬にもならねな・・・」、「あんたこと言っても、管理職(校長教頭ら)は、なんもこわぐ(怖く)ねもんな・・・」。「んだな。高尚すぎるものな・・・(笑)」。
「野添のはなしだば、信用ならねな(信用できない)。包丁つかわね(使わない)家がどこにあるってが・・・」「家族で話しせたって、するはずもねねが(するはずもない)・・・」。
「浮世離れしてるもんだ・・・。教育の現場だばそんたもんでね(そんなものではない)・・・」。
わたしは、そのときなにも愕然としたというわけではなかったように思う。教員組合の活動をしていて、いまどきの言葉を使えば、自分たち自身が「意識高い系」だと思っている教員が、白鳥さんの教育の未来へ向かう意味や野添さんの貧困が迫っている家族あり方をどうするかという提言に真摯に耳を貸そうとはしないで、自身の思考の領域を侵犯されたくないとだけ固まっていく現実は、なんとなくわかることであった。
それは酒の勢いというものではなく、秋田に限らず、日本の地方というものが、この時代、そしてそれ以降の時代も固陋にも手放さないありようだったと思えるからである。
知性への抜きがたいコンプレックス。でなければ、知性や社会批評を真っ正面から捉えようとしない、自分らの周り1メートル以内の親密圏での世間・・・。
わたしも組合の執行役員だったこともあり、秋田で何回か講演して廻った。まだ若い教師は、それなりに話を聞いてくれた印象だった。しかし、ある一定の年齢を過ぎると、それは自己のなにがしかの痛点に触れるのか、批判がましい物言いを何度も受けた。
一方でそうでありながら、東京、あるいは「中央」から何らかの肩書きをつけて講師が来て話しをすると、その内容の空疎さは関係なく、彼らは口々に賞賛する。それが、地方というものの抜きがたい痼疾であるように思う。
そこには、自分らと同じ地盤にたっている者への貶めが平然と行われている。しかしその一方で、きらびやかな「中央」からの者への礼賛が野放図に行われ、それに連なっている自分を確認したがる。
そのとき、そしてそれ以降も、わたしは何度も野添さん白鳥さんと付き合っていくうちに、野添さんや白鳥さんが、けっして少なくない冷笑と侮蔑の、目に見えない空気のなかに囲繞され、ときにタフに、ときにはかろうじて自身を矜恃している現実があることを知ることになる。
*
しかし、そんなときがあってから、わたしは野添さんをよく訪ねることになった。当時、野添さんは土蔵を借りて、そこを住居としてご家族とともに住んでいた。そんななかで、高校に進学した野添さんの娘さんに、わたしはいつしか日本史を教えることになっていったが、それはともかく、1984年の10月、「思想の科学研究会」が能代集会を開くということになったといって野添さんから連絡があり、「手伝ってけれ!」という声がかかってきた。
野添さんは、この集会をどう運営するか腐心していた。問題は、いかに人を集めるかであった。そこでまず能代の人たちに声をかけた。当時の能代には、若手の商店主や企業をしている人たちがサークルといってもいい青年会的な集まりを作っていて、能代市の衰退を止めようと活動していた。
能代市は、秋田県県北部の米代川の河口に位置し、上流から伐採された秋田杉の集散地として、かつては東洋一の材木の町として発展した町だった。しかし、東南アジアから輸入される安価な外材に押され、町の産業は長いあいだ停滞し、発展当時の豪勢な料亭や歓楽街も衰退する一方だった。
ただし、1984年のころまでは、町に残り、家業を継ぐなり新規の事業を行おうとするような若い世代は残っていた。野添さんは、彼らの力と動員力のある教員、それに旧国鉄の職員の力を結集して、能代集会を成功させたいと思っていた。
そのころわたしは、能代の若手の高校教師たち、高校の臨時採用である講師たちと「かだってけれ!(語り合おう!仲間に入ろう!の意味)」というサークルを作って、懇親会や勉強会を開いていた。それもあってか、高等学校教職員組合の県の青年部長もしていた。野添さんの「もくろみ」といっては失礼かもしれないが、わたしに実行委員長をしろという意味は、そのあたりにあったのだろう。
まずはタイトル。「『いまを考えるシンポジウム』思想の科学研究会能代集会」とすることにした。そして、基調講演は鶴見俊輔さんがすることになった。
当日は10月13日土曜日。したがって13時30分開演。そこまでは決まった。そのあとは分科会に分かれて討議する。第一分科会「いま教育は」、第二分科会「いまサークル活動は」、第三分科会「いま地域では」として、そのなかに思想の科学研究会側の鶴見さん、大野明男さん、加太こうじさん、渋谷定輔さん、今野聰さん、後藤宏行さんなどが入る。問題提起者と司会、記録には地元能代の人たち。白鳥さんには第二分科会の司会に入ってもらった。
パンフレットの表紙は、わたしの勤めている高校の商業科の若い先生にお願いした。会場は、能代市文化会館中ホール(定員360人)を借りた。
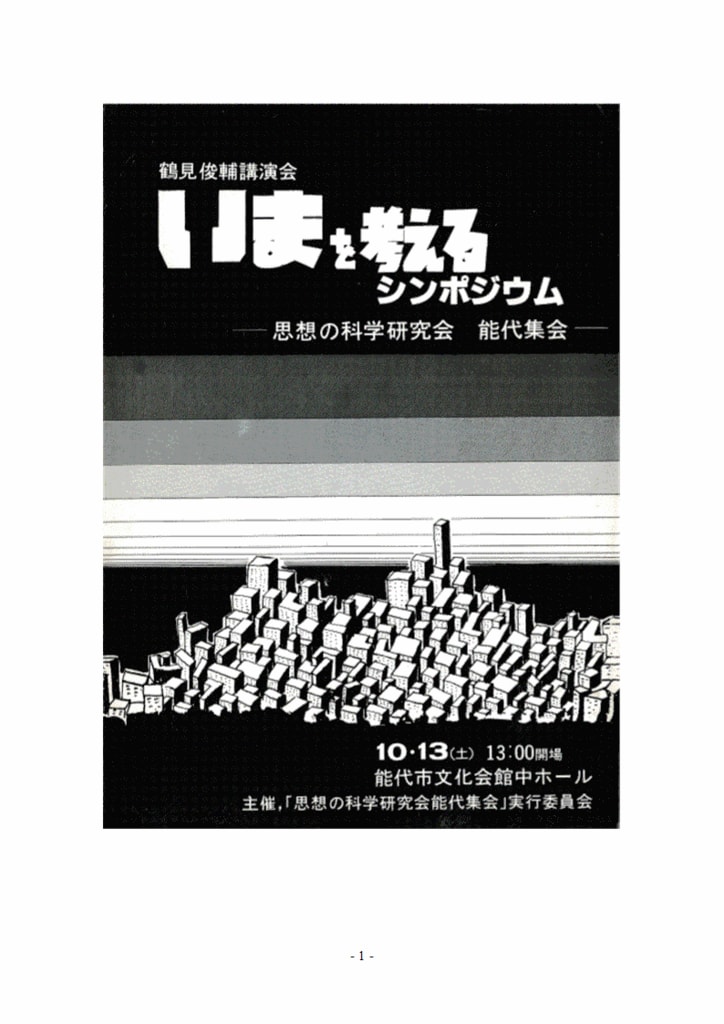
はたしてどれだけ集まるか。問題はそこにあった。教員はせいぜいで50から60人、わたしの教え子たちの能代北高の生徒たちが4~50人といったところ。あとは、能代の市民にどれだけ集まってもらえるか、あるいは全県から、どれだけの教師が関心を持って集まってくれるか。正直に言って、わたしにはまったく自信がなかった。
能代の人に鶴見俊輔さんって知っている? 「思想の科学」って雑誌、あるけど知っている? と言っても返ってくる答えは、芳しいものではなかった。
でも、当日会場は、満杯になった。「思想の科学」の地方集会で、これだけの人数が集まったのを、その後、わたしは「研究会」の会報の担当をした時期があるが、記憶にない。
分科会も盛況だった。それぞれで良質な討議と情報交換がなされた。
なんでこんなに人が集まったのか。能代であっても、人びとにこうした知的欲求は少なからずあることなのか。いまある「時代」を考えようという意識が、触発されたのか?
あるいは鶴見俊輔など「中央」から来た人たちへの信仰か? そのあたりはわからない。
いずれにしても、その夜は懇親会となった。さて宴会場をどこにするか。
シンポジウムの一ヶ月もまえ、その会場探しははじまっていた。わたしは、能代市に唯一、結婚式ができるホテルがあって、その小さいホールを借りればじゅうぶんだと思っていた。しかし野添さんは、「宴会場は金勇でねばダメだ!(金勇でなきゃダメだ)」と主張した。
金勇は、かつて能代が東洋一の木材都市として発展していたころのもっとも格調の高い料亭であった。天上から床材までなにからなにまで秋田杉の柾目の良材を使い、とりわけ天井板は、秋田杉の一本材を惜しげもなく使った作りになっていた。その大宴会場で懇親会をする。
じゃ、その宴会費をどう捻出するか。高額なはずであった。しかし野添さんは、なんとかなると言って、会場を押さえてしまった。
たぶん能代で当時まだそれなりに商売ができていた企業や商店から、賛助金を集めたのだろうと思う。その会計の報告は、わたしにはなかった。おそらく野添さんは、能代の企業や商店主の家を一軒一軒廻っただろう。ニコニコと笑みを浮かべ、なんとか能代のためだといって出し渋る連中のところも廻った。わたしにはなにも気取らせないで、「金の心配ならいらねがら、シンポジウムが盛況になるかどうか、それだけ考えてけれ・・・」。そんな風に野添さんは、わたしには言っていた。
いまも思うが、鶴見さんらを金勇の大広間に坐っていただき、宴会をしたのは、ほんとうによかったと思う。きっと能代という町の誇りが伝えられた。それは、いまになって大切なことだったと理解できる。
*
その能代集会のあと、わたしはやはり教員の生活に限界を感じて職を辞して上京した。
そして身過ぎ世過ぎのため、予備校講師に職を求め、評論の仕事に精力を傾けることにした。そのなかで、大学に進んだ教え子の勧めや援助もあり、なんとか大学で講座を持てるようになった時期もあり、その学生らと、ヴェトナム、韓国、中国、タイ、カンボジアなどの国々に研修旅行に出ることがあり、そのなかでやはり日本を、ということでわたしの生まれ育った秋田に行きたいという学生も多くなった。
2000年の年だったと思う。わたしは野添さんに、花岡事件を学生たちに体験させたいから、講師をお願いできないかと連絡した。そして、八月の暑い盛りに、秋田の大館駅で野添さんを待ち、花岡事件の現場を案内してもらった。夜行列車で大館に到着した学生の総数は20名ぐらいだったと思う。
花岡事件への野添さんの仕事は、なみなみならぬものであった。野添さんの話をするときに、この花岡事件における野添さんの役割を言い落とすわけにはいかない。しかし、それは後日「野添憲治論」といったものを書くときまで、多くをとっておく。
野添さんは、朝から暑いなか、能代から大館まで来てくれた。そして早速、花岡事件のあらましを学生に説明してくれた。いちおう彼らは大学生であることもあって、花岡事件について初めて聞いたというわけではなかった。
だがその事件の内容、中国からの強制連行の実態、奴隷の如く連行され死亡者が出た事実。さらにそれに関与した鹿島組の冷酷さ。じっさいの労働の悲惨さと過酷さ。中国人らの食糧はピンハネされ、満足に食事もあたえられず、粗末な衣服のまま厳寒の秋田で強制労働された現実。人の命が簡単に奪い取られ、極端な差別と偏見が横溢する労働。それらの話しは、学生たちに大きな衝撃となっていた。
そのなかでも、もっとも緊張したのは、華人死没者追善供養塔のある信正寺に行ったときであった。野添さんのあと、学生たちはカメラを片手に信正寺の境内を過ぎ、慰霊塔に行く途中、寺の人に、「まだ、あんただな! よけいな人を連れて来ねでけれ。花岡事件ももういい加減してけれ!」と怒鳴りつけられたときだった。
そのとき、東京から大学生の一行が来るということで、野添さんの連絡で、北羽新報や北鹿新聞など地元の新聞社の記者も同道していたが、野添さんは怒りもせず、いつものように笑顔を絶やさず、「そうだが・・・、でも大切な慰霊塔だものな・・・」と言葉を交わし、ひょうひょうと先頭を切って、わたしたちを先導してくれた。
野添さんは、花岡事件の現実を告発するたびごとに、「寝た子を起こすようなまねはやめろ」「いまさら昔の事件を掘り起こして、金がほしくてやってるんだべ・・・」といった誹謗中傷をずいぶん受けてきたという。
しかし、花岡事件を解明することは、戦犯逃れをはかった会社の無責任も、また直接、強制連行した中国人を死に追いつめ、または殺害した人間が、戦後ものうのうと生きているありようを根幹から突き詰める意味で、きわめて「人間」そのものを問う問題に違いなかった。
野添さんは、そのときも学生たちに語ったが、著書にもつぎのように書いている。
花岡で強制連行された中国人が、暴動を起こし日本人指導員を数名殺害し逃亡した昭和20(1945)年6月30日のとき、野添さんは国民学校(現在の小学校)の五年生だったという。
そのとき野添さんは、中国人捕虜たちが、山菜採りに行った娘を炭焼き小屋で焼いて食ったとか、農家から牛や馬を盗んで食ったという流言飛語(デマ)をまともに信じ、四キロもの山路をこえて本村の小学校に行き、捕らえられた二人の中国人捕虜に向かって、「チャンコロ!」「人殺し!」と叫びながら、なんども周りを回った。
・・・子どもが先生に引率されての行動だったでは許されることではない、とわたしは自分に言い聞かせた。(『聞き書き 花岡事件』御茶の水書房 1990年)
ここからも知れるように、野添さんの思想の根には一種の潔癖ともいうべき根が張っている。それはふだん静かなものであるのだが、ひとたび現実に触れると激しく波動するものになる。その話のとき、学生たちは、野添さんの微笑みつづける風貌からはあまり感じることのないその〝潔癖〟で〝ピュア〟な激しさに、思わず息を呑んで話を聞いていた。
それとともに、その際、学生たちが講師料として準備した謝礼を、野添さんは、頑として受け取らなかった。そのことは学生を困らせた。そんなとき、野添さんは、大きなバックから、花岡事件の二十冊ほどの自著を出してきて、もし良かったらこの本を買ってもらいたい。それでいいと学生に助け船を出してくれた。
花岡事件の衝撃と事実の重さ。本はすぐに完売した。野添さんは、「えがった、えがった、これで重い荷物を持って帰らなくすんだ」とニコニコ笑って、学生に応えてくれた。
不躾な学生の一人は、野添さんのお酒で膨れ上がったと思われるおなかをなでなでして、お酒をどれだけ飲まれます? って聞いた者がいた。
野添さんは、「そうだな、なんぼ呑んだべなぁ・・・」と大笑いをして、学生に別れを告げ、能代に帰っていった。
それから、もうすでに一九年もの時間が経っている。当時の若者たちも、もう四〇を越えるか越えないかの年回りになっている。もちろん、そのあともわたしは野添さんと何度かお会いしている。何回かは、東京での酒席でお付き合いもさせてもらった。すると、野添さんは、きまって満面の微笑みのなかから、こんな風に言った。
「東京に出て行くとずいぶん都会風な顔になっていくもんだな・・・」
それはおそらく褒めた言葉ではなかった。しかし、その言葉は不思議とわたしの背筋を伸ばしてくれる言葉だった。
*
野添さんは、ほんとうに微笑みの人だった。野添さんには、おそらく何冊か本を出したとき、東京で執筆活動をするチャンスがあったかと思う。でも野添さんは、能代を動かなかった。能代での野添さんは、東京で知られているような評価のなかにいたわけではなかった。むしろさまざまな根拠のない悪意に包まれていた時期も少なくなかったと思う。
でも、野添さんは微笑みを消すことはなかった。あったかい抒情と潔癖な思い。そして少年のような純粋さと、ただし、それだけでは生きていくことのかなわない強靱さを、少なくともわたしは垣間見たように思う。
わたしも秋田の地を離れて30数年が経つ。父も母も亡くなり、たまに両親の墓参りに秋田に訪れるだけになった。そもそも秋田県庁に勤めていて、ほぼ二年であちこち転勤して歩いた父親の関係で、わたしは秋田で生まれ、高校までと教員生活八年を過ごしたものの、地元の子ども会にも入ることなく、祭りの行事にも参加させてもらえず、そこで人間関係の濃密なつきあいも築けず、そのため根深い郷土への愛着も希薄なままに過ごした。
でも、遠く離れてみると、異国へ渡った移民たちがもつ「遠隔地ナショナリズム」ではないが、郷土である秋田の風土を懐かしいと感じることはある。そして、それと同時に笑みを絶やさない野添憲治さんと、焼酎に大量のレモンを入れて呑んだときの柔らかな空気を、ふと思い出すことがある。
野添さんは、わたしにとって風土に生きる意味を教えてくれた先生であった。それは必ずしも安楽で牧歌的なものではない。むしろ狭隘な世界が作り出す、数々の棘に満ちたなかでの暮らしであった。
そして、そこから遁走したわたしに、野添憲治さんは、満面に微笑んで、「なんと東京に出ていくと都会的な顔になるもんだなぁ・・・」と笑いながら語りかけてくれた。そのことを深く感謝して、いったんはまずこの稿を閉じる。
ご冥福を祈りたい。 合掌
野添さんは、微笑みの人だった。人なつっこい話し方をする人だった。
野添さんの話は、いつも微笑みに包まれるようにして現れた。ときとして、それが微笑みの向こう側に大きな暗い陰影を映し出すこともあったが、それでも柔らかで控えめな語り口からは、いつも微笑みが溢れていた。
花岡事件などの苛烈な告発をともなう問題のときであっても、能代の町のボスたちのドタバタとした政治抗争の話であったとしても、戦中の自身の子ども時代の思い出を懐かしげに語るときも、それはあまり変わらなかった。いつも野添さんは肉厚の丸い顔のなかに細い眼を埋めるようにして、ニコニコしながら話しをした。
・・・戦争中、憲兵で政治犯などを激しく取り調べなんかやった人たちは、戦後になって村に帰ってくると、篤農家となった人たちが多いんだな・・・。なんでだべなぁ・・・。
加えると、野添さんの話の結末は、〝どうしてだべな〟〝なんと、そうなってしまったもんなぁ・・・〟という終わり方をすることが多かった。つまり、結論といったことはいわない人だった。それは知識人がデレッタントにふるまう韜晦ではなかった。それでいて、こっちに考えさせるという話し方でもなかった。
なにか自分自身に語りかけるように、人間が作り出す暗闇の底にじっと目を凝らすようにして自問自答している。野添さんはそんな感じの話し方をする人だった。それは、いま思うと野添さんの思想に根を張っていた野添さんの精神のありようそのものだったと思われてならない。
*
野添憲治さんと知り合ったのは、わたしが秋田県能代市にある女子高に転勤した翌年の1983年の秋過ぎのことだったと思う。もちろんそれ以前から、たまに読む『思想の科学』を通じて野添憲治という名は知っていたし、また『無名の日本人』を書き、サークル活動である「山脈の会」を主催している白鳥邦夫さんも知っていた。この当時、白鳥さんは能代工業高校の国語教師だったが、能代にはこんな人びとがいるんだという畏敬の念を持って、遠くから眺めているという感じだった。
わたしが高校教師になるころは、ちょうど日本が1970年代の後半に入った時期であった。1970年代は、蔵相だった福田赳夫が命名した〝昭和元禄〟と丸々と肥え太った膨満期から、何となくすでに予兆はあったものの、日本経済はドル=ショックやオイル=ショックの経済的激動が起こり、その不況感を色濃く尾を引いていたころだった。
ちなみに、わたしが北東北の小都市秋田の高校から東京の大学に進んだ時期は、学園闘争の残り火がちょろちょろと燃え残っていた時期であり、その後、浅間山荘立てこもり事件で象徴的な「連赤事件(連合赤軍事件)」の1972年を過ぎ、消費者物価上昇率が25%近くまでおよんだ〝狂乱物価〟、1974の経済成長率がマイナスに転じた「マイナス成長」を経て、完全失業率が100万人を超えた時期に大学を卒業した。
自宅待機、内定取り消しが当たりまえの時代。1993年から2005年を区切りとされるのちの〝就職氷河期〟と比べると、時期は短かったのかも知れないが、わたしが大学を卒業するころは、言うまでもなく「就職難」の時代であった。
東京三田にある大学の法学部を卒業したわたしは、その後、アルバイトを何件も掛け持ちして生活費を稼ぎ、同じ大学の文学部に学士入学した。さてそのあとを考えたとき、当時の学生を取り巻く環境を含めて俸給生活者になるしか仕方がない。それでもやっとなのだという自分自身の漠然とした〝無力〟さを抱え、「就職難」の時代に直面していた。
そうした時代環境で、わたしより年長の〝団塊の世代〟の大量採用で、当時は狭き門となっていた高校教員だけが、なんとか自分を裏切らない方途だと勝手に思い詰めて、首都圏の高校教員の職を探すのと同時に、高校まで過ごした秋田県の教職員採用試験をうけた。
そして1978年春、なんとか秋田県の高校教員に潜りこめた。いま思うと幸運なことだったのかも知れない。
しかし、秋田に帰っての高校教師。哲学や文学の本を読みたくても、地元の書店にはそんな本はないし、都市生活者が受けるような刺激は希薄である環境はやはり気分的に堪(こた)えるものがあった。
あるとき、東京から友人数人が田舎の学校を見たいと秋田に訪ねてきて、数日過ごすうちに、高校の職員室で教師らが煙草を吸いながら仕事をしているのを見て、お前もまだ煙草を吸っているのかと聞かれ、そうだと答えると、「都会のインテリは少なくとも仕事中は煙草は吸わない。いや、人前で煙草を吸うインテリを見たことがない」とシニカルに笑われた。
その真偽はともかく、彼らと話をしていても、時代の流れから取り残されていくような焦り。都会がまぶしく見えてしかたなかった。インターネットなど想像もつかなかったこの時代。そんな隔てられた距離感が、自分の周囲に一日ごとに蓄積されていくような日常がそこにはあった。
父親は、教員を目指すことに賛成ではなかったのだが、昔風にいうと長男が郷里に帰って就職する。それ自体は理にかなっているとして歓迎してくれた。
表向きは、教員という仕事が合っているからと自分を言い聞かし、なぜ秋田に帰ったのかと聞かれるたびに、あたかもそれが唯一の重大事の如く、自分は長男だから、と答える自分がそこにはいた。
思い返すに、そんな自身の羞恥と後悔を相手に気取られぬように、当時のわたしは教員の仕事に没頭した。校内教員研修会や教材研究会を開いたり、陸上部や放送部などの課外クラブで生徒たちの活躍をともに喜んだり、高等学校の教職員組合で執行役員を務めたりすることで、乖離する恐れを埋めていたのかも知れない。
そして能代農業高校(現能代西高)を皮切りに、十和田高校定時制の教員、そして1982年春に能代市の女子校(能代北高、現能代松陽高校)に転勤し、教員生活六年目を迎えていた時期、わたしは野添憲治さんや白鳥邦夫さんと出逢うことになる。
*
親しくなったのは、白鳥さんが早かった。それは学校は違っていたが、同じ能代市内の高校教師同士だったからである。だが二人のことではじめに印象に残っているのは、白鳥さんと知り合いになってのちの教員組合の能代の地区研修会の会場でのことだった。その研修会の講師は野添さんであった。そのなかで白鳥さんは短い挨拶をした。
もとより長野県生まれで、東大倫理学科を卒業された白鳥さんはいつも秋田の方言などに寄りかからない語り口で話をした。それはともすれば地元に迎合して地元化することで親密圏をつくって、それに阿ねることの多いありかたと異なるある一つの態度であると思った。そんな白鳥さんの言葉は、つねに知性的な響きを湛える言葉となってわたしのこころに落ちていった。
「教師とは何か?」。白鳥さんは、たしかタゴールの言葉にある、「教えることの主な目的は、意味を説明することではなく、心の扉をたたくことなのだ」という一文を引いて教育の意味を語った。
そのあとで野添憲治さんの講演があった。もしかするとその順番は逆だったかもしれないが、野添さんは、そこでも丸い顔に朴訥な微笑みを浮かべ、顔の中に眼を埋めるようにして、ニコニコと語りだした。秋田訛りの強い温かみのある言葉で、講演ははじまった。
やわらかい知性。それは白鳥さんと対比的な意味ではない。白鳥さんの思想や知性は、教条主義的な過ちを乗り越えて、自由に闊達に、そして柔軟に思考を積み重ねていくという風情がある。
それに対して、野添さんは、むしろ剛直な根というものが話しの端々に張られている。しかし、語り口は、田舎のじいさんばあさんにも、うんうんと思わせる、親しみのこもった柔らかさがある。
「いやぁ、なんとしたらえしべな?」(どうしたらいいんでしょうね)。そうした言葉のなかに思想が詰まっている。
野添さんの話は、いまどきの子どもを取り巻く家庭のあり方についてのものだった。家庭というものが、経済的に夫婦共稼ぎを余儀なくされている現実では、むしろ子どもを含め家族のなかで、各自がよく話をして、それぞれが自立するように持っていかないと、崩壊を余儀なくされるのではないかという話だったように思う。家族内で、家族だからといってもたれ合わずに、すこしでも話し合うってこと。「そうしたことが大事でねが、と思うわけだす」(そんなことが大事ではないかと思うわけです)。
そのとき、共働きで忙しい家庭では手のかからないように、もはや料理は包丁で行うものではなく、レトルト食品だけでの食事は、はさみですべてが行われる。野菜も刻まない、魚も焼くことがない。肉もはさみで切る。いまとなっては、そんなに不思議ではない現実であるのだが、このときは会場のあちこちで乾いた笑いが起こった。
講演会が終わって懇親会が開かれた。野添さんは、つぎの用事があるということで、不在だった。白鳥さんは、たしかその場にはいなかった。そのなかで、能代市にある能代高校、能代商業、能代工業、能代農業、能代北高(女子校)、二ツ井高校の各先生たちと話をしているうちに、教師たちは、今日の講演会の批評をはじめた。
白鳥さんの話は「毒にも薬にもならねな・・・」、「あんたこと言っても、管理職(校長教頭ら)は、なんもこわぐ(怖く)ねもんな・・・」。「んだな。高尚すぎるものな・・・(笑)」。
「野添のはなしだば、信用ならねな(信用できない)。包丁つかわね(使わない)家がどこにあるってが・・・」「家族で話しせたって、するはずもねねが(するはずもない)・・・」。
「浮世離れしてるもんだ・・・。教育の現場だばそんたもんでね(そんなものではない)・・・」。
わたしは、そのときなにも愕然としたというわけではなかったように思う。教員組合の活動をしていて、いまどきの言葉を使えば、自分たち自身が「意識高い系」だと思っている教員が、白鳥さんの教育の未来へ向かう意味や野添さんの貧困が迫っている家族あり方をどうするかという提言に真摯に耳を貸そうとはしないで、自身の思考の領域を侵犯されたくないとだけ固まっていく現実は、なんとなくわかることであった。
それは酒の勢いというものではなく、秋田に限らず、日本の地方というものが、この時代、そしてそれ以降の時代も固陋にも手放さないありようだったと思えるからである。
知性への抜きがたいコンプレックス。でなければ、知性や社会批評を真っ正面から捉えようとしない、自分らの周り1メートル以内の親密圏での世間・・・。
わたしも組合の執行役員だったこともあり、秋田で何回か講演して廻った。まだ若い教師は、それなりに話を聞いてくれた印象だった。しかし、ある一定の年齢を過ぎると、それは自己のなにがしかの痛点に触れるのか、批判がましい物言いを何度も受けた。
一方でそうでありながら、東京、あるいは「中央」から何らかの肩書きをつけて講師が来て話しをすると、その内容の空疎さは関係なく、彼らは口々に賞賛する。それが、地方というものの抜きがたい痼疾であるように思う。
そこには、自分らと同じ地盤にたっている者への貶めが平然と行われている。しかしその一方で、きらびやかな「中央」からの者への礼賛が野放図に行われ、それに連なっている自分を確認したがる。
そのとき、そしてそれ以降も、わたしは何度も野添さん白鳥さんと付き合っていくうちに、野添さんや白鳥さんが、けっして少なくない冷笑と侮蔑の、目に見えない空気のなかに囲繞され、ときにタフに、ときにはかろうじて自身を矜恃している現実があることを知ることになる。
*
しかし、そんなときがあってから、わたしは野添さんをよく訪ねることになった。当時、野添さんは土蔵を借りて、そこを住居としてご家族とともに住んでいた。そんななかで、高校に進学した野添さんの娘さんに、わたしはいつしか日本史を教えることになっていったが、それはともかく、1984年の10月、「思想の科学研究会」が能代集会を開くということになったといって野添さんから連絡があり、「手伝ってけれ!」という声がかかってきた。
野添さんは、この集会をどう運営するか腐心していた。問題は、いかに人を集めるかであった。そこでまず能代の人たちに声をかけた。当時の能代には、若手の商店主や企業をしている人たちがサークルといってもいい青年会的な集まりを作っていて、能代市の衰退を止めようと活動していた。
能代市は、秋田県県北部の米代川の河口に位置し、上流から伐採された秋田杉の集散地として、かつては東洋一の材木の町として発展した町だった。しかし、東南アジアから輸入される安価な外材に押され、町の産業は長いあいだ停滞し、発展当時の豪勢な料亭や歓楽街も衰退する一方だった。
ただし、1984年のころまでは、町に残り、家業を継ぐなり新規の事業を行おうとするような若い世代は残っていた。野添さんは、彼らの力と動員力のある教員、それに旧国鉄の職員の力を結集して、能代集会を成功させたいと思っていた。
そのころわたしは、能代の若手の高校教師たち、高校の臨時採用である講師たちと「かだってけれ!(語り合おう!仲間に入ろう!の意味)」というサークルを作って、懇親会や勉強会を開いていた。それもあってか、高等学校教職員組合の県の青年部長もしていた。野添さんの「もくろみ」といっては失礼かもしれないが、わたしに実行委員長をしろという意味は、そのあたりにあったのだろう。
まずはタイトル。「『いまを考えるシンポジウム』思想の科学研究会能代集会」とすることにした。そして、基調講演は鶴見俊輔さんがすることになった。
当日は10月13日土曜日。したがって13時30分開演。そこまでは決まった。そのあとは分科会に分かれて討議する。第一分科会「いま教育は」、第二分科会「いまサークル活動は」、第三分科会「いま地域では」として、そのなかに思想の科学研究会側の鶴見さん、大野明男さん、加太こうじさん、渋谷定輔さん、今野聰さん、後藤宏行さんなどが入る。問題提起者と司会、記録には地元能代の人たち。白鳥さんには第二分科会の司会に入ってもらった。
パンフレットの表紙は、わたしの勤めている高校の商業科の若い先生にお願いした。会場は、能代市文化会館中ホール(定員360人)を借りた。
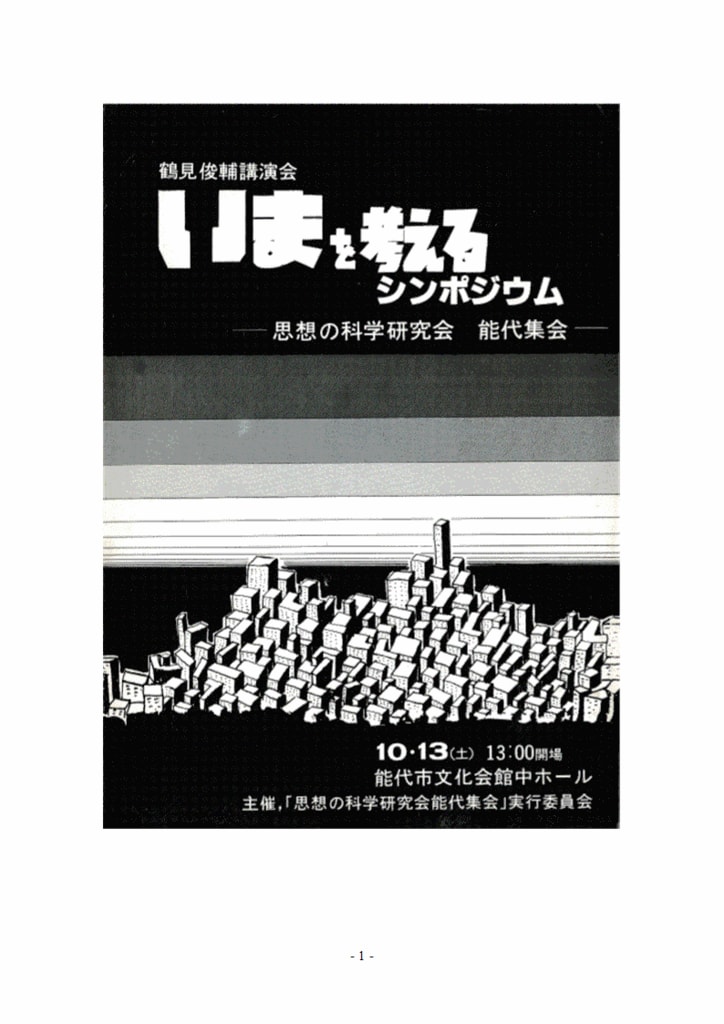
はたしてどれだけ集まるか。問題はそこにあった。教員はせいぜいで50から60人、わたしの教え子たちの能代北高の生徒たちが4~50人といったところ。あとは、能代の市民にどれだけ集まってもらえるか、あるいは全県から、どれだけの教師が関心を持って集まってくれるか。正直に言って、わたしにはまったく自信がなかった。
能代の人に鶴見俊輔さんって知っている? 「思想の科学」って雑誌、あるけど知っている? と言っても返ってくる答えは、芳しいものではなかった。
でも、当日会場は、満杯になった。「思想の科学」の地方集会で、これだけの人数が集まったのを、その後、わたしは「研究会」の会報の担当をした時期があるが、記憶にない。
分科会も盛況だった。それぞれで良質な討議と情報交換がなされた。
なんでこんなに人が集まったのか。能代であっても、人びとにこうした知的欲求は少なからずあることなのか。いまある「時代」を考えようという意識が、触発されたのか?
あるいは鶴見俊輔など「中央」から来た人たちへの信仰か? そのあたりはわからない。
いずれにしても、その夜は懇親会となった。さて宴会場をどこにするか。
シンポジウムの一ヶ月もまえ、その会場探しははじまっていた。わたしは、能代市に唯一、結婚式ができるホテルがあって、その小さいホールを借りればじゅうぶんだと思っていた。しかし野添さんは、「宴会場は金勇でねばダメだ!(金勇でなきゃダメだ)」と主張した。
金勇は、かつて能代が東洋一の木材都市として発展していたころのもっとも格調の高い料亭であった。天上から床材までなにからなにまで秋田杉の柾目の良材を使い、とりわけ天井板は、秋田杉の一本材を惜しげもなく使った作りになっていた。その大宴会場で懇親会をする。
じゃ、その宴会費をどう捻出するか。高額なはずであった。しかし野添さんは、なんとかなると言って、会場を押さえてしまった。
たぶん能代で当時まだそれなりに商売ができていた企業や商店から、賛助金を集めたのだろうと思う。その会計の報告は、わたしにはなかった。おそらく野添さんは、能代の企業や商店主の家を一軒一軒廻っただろう。ニコニコと笑みを浮かべ、なんとか能代のためだといって出し渋る連中のところも廻った。わたしにはなにも気取らせないで、「金の心配ならいらねがら、シンポジウムが盛況になるかどうか、それだけ考えてけれ・・・」。そんな風に野添さんは、わたしには言っていた。
いまも思うが、鶴見さんらを金勇の大広間に坐っていただき、宴会をしたのは、ほんとうによかったと思う。きっと能代という町の誇りが伝えられた。それは、いまになって大切なことだったと理解できる。
*
その能代集会のあと、わたしはやはり教員の生活に限界を感じて職を辞して上京した。
そして身過ぎ世過ぎのため、予備校講師に職を求め、評論の仕事に精力を傾けることにした。そのなかで、大学に進んだ教え子の勧めや援助もあり、なんとか大学で講座を持てるようになった時期もあり、その学生らと、ヴェトナム、韓国、中国、タイ、カンボジアなどの国々に研修旅行に出ることがあり、そのなかでやはり日本を、ということでわたしの生まれ育った秋田に行きたいという学生も多くなった。
2000年の年だったと思う。わたしは野添さんに、花岡事件を学生たちに体験させたいから、講師をお願いできないかと連絡した。そして、八月の暑い盛りに、秋田の大館駅で野添さんを待ち、花岡事件の現場を案内してもらった。夜行列車で大館に到着した学生の総数は20名ぐらいだったと思う。
花岡事件への野添さんの仕事は、なみなみならぬものであった。野添さんの話をするときに、この花岡事件における野添さんの役割を言い落とすわけにはいかない。しかし、それは後日「野添憲治論」といったものを書くときまで、多くをとっておく。
野添さんは、朝から暑いなか、能代から大館まで来てくれた。そして早速、花岡事件のあらましを学生に説明してくれた。いちおう彼らは大学生であることもあって、花岡事件について初めて聞いたというわけではなかった。
だがその事件の内容、中国からの強制連行の実態、奴隷の如く連行され死亡者が出た事実。さらにそれに関与した鹿島組の冷酷さ。じっさいの労働の悲惨さと過酷さ。中国人らの食糧はピンハネされ、満足に食事もあたえられず、粗末な衣服のまま厳寒の秋田で強制労働された現実。人の命が簡単に奪い取られ、極端な差別と偏見が横溢する労働。それらの話しは、学生たちに大きな衝撃となっていた。
そのなかでも、もっとも緊張したのは、華人死没者追善供養塔のある信正寺に行ったときであった。野添さんのあと、学生たちはカメラを片手に信正寺の境内を過ぎ、慰霊塔に行く途中、寺の人に、「まだ、あんただな! よけいな人を連れて来ねでけれ。花岡事件ももういい加減してけれ!」と怒鳴りつけられたときだった。
そのとき、東京から大学生の一行が来るということで、野添さんの連絡で、北羽新報や北鹿新聞など地元の新聞社の記者も同道していたが、野添さんは怒りもせず、いつものように笑顔を絶やさず、「そうだが・・・、でも大切な慰霊塔だものな・・・」と言葉を交わし、ひょうひょうと先頭を切って、わたしたちを先導してくれた。
野添さんは、花岡事件の現実を告発するたびごとに、「寝た子を起こすようなまねはやめろ」「いまさら昔の事件を掘り起こして、金がほしくてやってるんだべ・・・」といった誹謗中傷をずいぶん受けてきたという。
しかし、花岡事件を解明することは、戦犯逃れをはかった会社の無責任も、また直接、強制連行した中国人を死に追いつめ、または殺害した人間が、戦後ものうのうと生きているありようを根幹から突き詰める意味で、きわめて「人間」そのものを問う問題に違いなかった。
野添さんは、そのときも学生たちに語ったが、著書にもつぎのように書いている。
花岡で強制連行された中国人が、暴動を起こし日本人指導員を数名殺害し逃亡した昭和20(1945)年6月30日のとき、野添さんは国民学校(現在の小学校)の五年生だったという。
そのとき野添さんは、中国人捕虜たちが、山菜採りに行った娘を炭焼き小屋で焼いて食ったとか、農家から牛や馬を盗んで食ったという流言飛語(デマ)をまともに信じ、四キロもの山路をこえて本村の小学校に行き、捕らえられた二人の中国人捕虜に向かって、「チャンコロ!」「人殺し!」と叫びながら、なんども周りを回った。
・・・子どもが先生に引率されての行動だったでは許されることではない、とわたしは自分に言い聞かせた。(『聞き書き 花岡事件』御茶の水書房 1990年)
ここからも知れるように、野添さんの思想の根には一種の潔癖ともいうべき根が張っている。それはふだん静かなものであるのだが、ひとたび現実に触れると激しく波動するものになる。その話のとき、学生たちは、野添さんの微笑みつづける風貌からはあまり感じることのないその〝潔癖〟で〝ピュア〟な激しさに、思わず息を呑んで話を聞いていた。
それとともに、その際、学生たちが講師料として準備した謝礼を、野添さんは、頑として受け取らなかった。そのことは学生を困らせた。そんなとき、野添さんは、大きなバックから、花岡事件の二十冊ほどの自著を出してきて、もし良かったらこの本を買ってもらいたい。それでいいと学生に助け船を出してくれた。
花岡事件の衝撃と事実の重さ。本はすぐに完売した。野添さんは、「えがった、えがった、これで重い荷物を持って帰らなくすんだ」とニコニコ笑って、学生に応えてくれた。
不躾な学生の一人は、野添さんのお酒で膨れ上がったと思われるおなかをなでなでして、お酒をどれだけ飲まれます? って聞いた者がいた。
野添さんは、「そうだな、なんぼ呑んだべなぁ・・・」と大笑いをして、学生に別れを告げ、能代に帰っていった。
それから、もうすでに一九年もの時間が経っている。当時の若者たちも、もう四〇を越えるか越えないかの年回りになっている。もちろん、そのあともわたしは野添さんと何度かお会いしている。何回かは、東京での酒席でお付き合いもさせてもらった。すると、野添さんは、きまって満面の微笑みのなかから、こんな風に言った。
「東京に出て行くとずいぶん都会風な顔になっていくもんだな・・・」
それはおそらく褒めた言葉ではなかった。しかし、その言葉は不思議とわたしの背筋を伸ばしてくれる言葉だった。
*
野添さんは、ほんとうに微笑みの人だった。野添さんには、おそらく何冊か本を出したとき、東京で執筆活動をするチャンスがあったかと思う。でも野添さんは、能代を動かなかった。能代での野添さんは、東京で知られているような評価のなかにいたわけではなかった。むしろさまざまな根拠のない悪意に包まれていた時期も少なくなかったと思う。
でも、野添さんは微笑みを消すことはなかった。あったかい抒情と潔癖な思い。そして少年のような純粋さと、ただし、それだけでは生きていくことのかなわない強靱さを、少なくともわたしは垣間見たように思う。
わたしも秋田の地を離れて30数年が経つ。父も母も亡くなり、たまに両親の墓参りに秋田に訪れるだけになった。そもそも秋田県庁に勤めていて、ほぼ二年であちこち転勤して歩いた父親の関係で、わたしは秋田で生まれ、高校までと教員生活八年を過ごしたものの、地元の子ども会にも入ることなく、祭りの行事にも参加させてもらえず、そこで人間関係の濃密なつきあいも築けず、そのため根深い郷土への愛着も希薄なままに過ごした。
でも、遠く離れてみると、異国へ渡った移民たちがもつ「遠隔地ナショナリズム」ではないが、郷土である秋田の風土を懐かしいと感じることはある。そして、それと同時に笑みを絶やさない野添憲治さんと、焼酎に大量のレモンを入れて呑んだときの柔らかな空気を、ふと思い出すことがある。
野添さんは、わたしにとって風土に生きる意味を教えてくれた先生であった。それは必ずしも安楽で牧歌的なものではない。むしろ狭隘な世界が作り出す、数々の棘に満ちたなかでの暮らしであった。
そして、そこから遁走したわたしに、野添憲治さんは、満面に微笑んで、「なんと東京に出ていくと都会的な顔になるもんだなぁ・・・」と笑いながら語りかけてくれた。そのことを深く感謝して、いったんはまずこの稿を閉じる。
ご冥福を祈りたい。 合掌
















