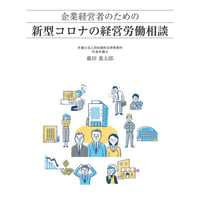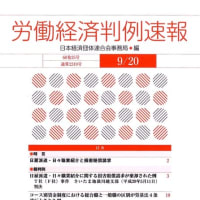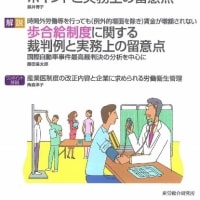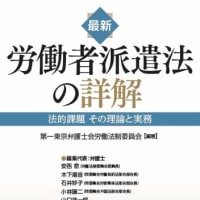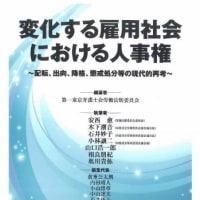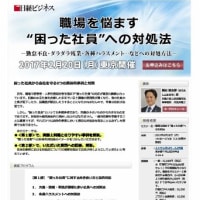Q24 「労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状」や「労働審判手続申立書」などが裁判所から会社に届きました。労働審判を申し立てられた使用者の主な注意事項はどのようなものですか?
労働審判手続においては,申立書及び答弁書の記載内容から一応の心証が形成され,第1回期日でその確認作業が行われて最終的な心証が形成された後は,その心証に基づいて調停が試みられ,調停が成立しない場合は労働審判が出されることになります。
原則として第1回期日終了時までに最終的な心証が形成されてしまい,その後の修正は困難であることから,私は,充実した答弁書の作成が最も重要であり,次に,第1回期日で十分な説明ができることが重要であると考えています。
労働審判手続においては,当事者双方及び裁判所の都合のみならず,忙しい労働審判員2名のスケジュール調整が必要なこともあり,第1回期日の変更は原則として認められないことに十分な注意が必要です。
準備不足のまま第1回期日が間近に迫っているような場合や,依頼した代理人弁護士の都合がつかない場合であっても,第1回期日の変更は原則として認めてもらえません。
第1回期日の変更が例外的に認められるのは,労働審判員の選任が完了していない時期に日程調整したような場合です。
労働審判員の選任は,一般に,裁判所が申立書を相手方(主に使用者側)に発送してから1週間から10日程度で行われていると言われていますから,第1回期日の変更が必要な場合は,申立書が会社に届いてから1週間程度のうちに日程調整の連絡を裁判所に入れる必要があることになります。
第1回期日は,原則として申立てから40日以内の日に指定されます(労働審判規則13条)。
相手方(主に使用者側)としては,答弁書作成の準備をする時間が足りないから第1回期日を変更したい,あるいは,主張立証を第2回期日までさせて欲しいということになりがちですが,上記のとおり,労働審判は第1回期日までが勝負であり,第1回期日の変更は原則として認められませんから,たとえ不十分であっても,第1回期日までに全力を尽くして準備していく必要があります。
事情をよく知る担当者が,第1回期日には出頭できないが,第2回期日なら何とか出頭できそうだという場合は,その旨,答弁書に記載するなどして,労働審判委員会と進行の調整をする必要があり,漫然と放置してしまうと,事情をよく知る担当者不出頭のまま,手続が終了するリスクが生じることになります。
弁護士は随分先までスケジュールが入りますから,答弁書が会社に届いてからのんびりしていると,第1回期日の日時に別の予定が入ってしまいます。
依頼したい弁護士がいるのであれば,申立書が会社に届いたら直ちにその弁護士に電話し,第1回期日の予定を空けておいてもらうなどの対応が必要となります。
会社担当者が私の事務所に労働審判の相談に来た時期が第1回期日まで1週間を切った時期(答弁書提出期限経過後)だったため,即日,急いで作成した答弁書を提出せざるを得ず,第1回期日が指定された日時は私のスケジュールが既に埋まっていたため,第1回期日に私が出頭できなかった事案もありましたが,このような事態が会社にとって望ましくないことは,言うまでもありません。
労働審判手続の当事者は,裁判所(労働審判委員会)に対し,主張書面だけでなく,自己の主張を基礎づける証拠の写しも提出するのが通常ですが,東京地裁の運用では,労働審判委員には,申立書,答弁書等の主張書面のみが事前に送付され,証拠の写しについては送付されない扱いとなっています。
労働審判員は,他の担当事件のために裁判所に来た際などに,証拠を閲覧し,詳細な手控えを取ったりして対応しているようですが,自宅で証拠と照らし合わせながら主張書面を検討することはできません。
また,労働審判官(裁判官)も大量の事件を処理していますので,答弁書を読んだだけで言いたいことが明確に伝わるようにしておかないと,真意が伝わらない恐れがあります。
答弁書作成に当たっては,答弁書が労働審判委員会を「説得」する手段であり,労働審判委員会に会社の主張を理解してもらえずに不当な結論が出てしまった場合は,労働審判委員会が悪いのではなく,労働審判委員会を説得できなかった自分たちに問題があったと受け止めるスタンスが重要となります。
労働審判委員会は,申立書,答弁書の記載内容から,事前に暫定的な心証を形成して第1回期日に臨んでいます。
また,第1回期日は,時間が限られている上,緊張して言いたいことが思ったほど言えないことが多いというのが実情です。
したがって,労働審判手続において相手方とされた使用者側としては,重要な証拠内容は答弁書に引用するなどして,答弁書の記載のみからでも,主張内容が明確に伝わるようにしておくべきことになります。
陳述書を答弁書と別途提出するのは当事者の自由ですが,重要ポイントについては,答弁書に盛り込んでおくことが必要となります。
答弁書の記述で言いたいことが伝わるのであれば,答弁書と同じような内容の陳述書を別途提出する必要はありません。
第1回期日おける審理では,事情をよく知る担当者が事実関係を説明しないことにはリアリティーがありませんから,会社担当者が事実説明をしていくことになります。
解雇した際の言葉のやり取り等の重要な事実関係を,解雇の場にいたわけでもない代理人弁護士が説明したのでは,説得力がありません。
したがって,期日には代理人弁護士が出頭するだけでは足りず,紛争の実情を把握している会社担当者が2名程度,出頭する必要があります。
しかし,会社担当者は裁判所の手続に不慣れなことが多いため,緊張して事実を正確に伝えることができなくなりがちです。
言いたいことが言えないまま終わってしまうことがないようにするためには,事前に提出する答弁書に言いたいことをしっかり盛り込んでおいて当日話さなければならないことをできるだけ減らしておくべきでしょう。
なお,どうしても代理人弁護士だけしか出席できない場合は,代理人弁護士が,労働審判委員会からの質問に答えざるを得ませんが,解雇等の場にいたわけでもない代理人弁護士が質問に対して十分な回答をすることは困難です。
事前の打合せの負担が重くなるのみならず,事情をよく知る担当者が出頭した場合と比較して,会社にとって不利な結果となることを覚悟する必要があります。
労働審判の第1回期日にかかる時間についてですが,2時間程度はかかるものと考えておく必要があります。
私がこれまでに経験した労働審判事件の第1回期日は,1時間20分~2時間30分程度かかっています。
事案の複雑さの程度にもよりますが,同程度の事件であれば,申立書,答弁書において,充実した主張反論がなされているケースの方が,所要時間が短くなる傾向にあります。
第2回以降の期日は,第1回期日で実質的な審理が終了し,労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には,解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり,当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は,期日は30分足らずで終了することになります。
ただし,第2回以降の期日であっても,当事者双方が調停案を直ちに受け入れなかったものの,もう少しで調停が成立しそうな状況だったため,その日のうちに調停を成立させるために交渉が継続され,約2時間30分かかったことがありました。
また,当事者から新たな主張がなされ,それが審理されることになったような場合も,時間がかかる可能性があります。
第2回期日以降についても,2~3時間程度は時間が取られても支障が生じないよう,スケジュールを空けておくべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎
労働審判手続においては,申立書及び答弁書の記載内容から一応の心証が形成され,第1回期日でその確認作業が行われて最終的な心証が形成された後は,その心証に基づいて調停が試みられ,調停が成立しない場合は労働審判が出されることになります。
原則として第1回期日終了時までに最終的な心証が形成されてしまい,その後の修正は困難であることから,私は,充実した答弁書の作成が最も重要であり,次に,第1回期日で十分な説明ができることが重要であると考えています。
労働審判手続においては,当事者双方及び裁判所の都合のみならず,忙しい労働審判員2名のスケジュール調整が必要なこともあり,第1回期日の変更は原則として認められないことに十分な注意が必要です。
準備不足のまま第1回期日が間近に迫っているような場合や,依頼した代理人弁護士の都合がつかない場合であっても,第1回期日の変更は原則として認めてもらえません。
第1回期日の変更が例外的に認められるのは,労働審判員の選任が完了していない時期に日程調整したような場合です。
労働審判員の選任は,一般に,裁判所が申立書を相手方(主に使用者側)に発送してから1週間から10日程度で行われていると言われていますから,第1回期日の変更が必要な場合は,申立書が会社に届いてから1週間程度のうちに日程調整の連絡を裁判所に入れる必要があることになります。
第1回期日は,原則として申立てから40日以内の日に指定されます(労働審判規則13条)。
相手方(主に使用者側)としては,答弁書作成の準備をする時間が足りないから第1回期日を変更したい,あるいは,主張立証を第2回期日までさせて欲しいということになりがちですが,上記のとおり,労働審判は第1回期日までが勝負であり,第1回期日の変更は原則として認められませんから,たとえ不十分であっても,第1回期日までに全力を尽くして準備していく必要があります。
事情をよく知る担当者が,第1回期日には出頭できないが,第2回期日なら何とか出頭できそうだという場合は,その旨,答弁書に記載するなどして,労働審判委員会と進行の調整をする必要があり,漫然と放置してしまうと,事情をよく知る担当者不出頭のまま,手続が終了するリスクが生じることになります。
弁護士は随分先までスケジュールが入りますから,答弁書が会社に届いてからのんびりしていると,第1回期日の日時に別の予定が入ってしまいます。
依頼したい弁護士がいるのであれば,申立書が会社に届いたら直ちにその弁護士に電話し,第1回期日の予定を空けておいてもらうなどの対応が必要となります。
会社担当者が私の事務所に労働審判の相談に来た時期が第1回期日まで1週間を切った時期(答弁書提出期限経過後)だったため,即日,急いで作成した答弁書を提出せざるを得ず,第1回期日が指定された日時は私のスケジュールが既に埋まっていたため,第1回期日に私が出頭できなかった事案もありましたが,このような事態が会社にとって望ましくないことは,言うまでもありません。
労働審判手続の当事者は,裁判所(労働審判委員会)に対し,主張書面だけでなく,自己の主張を基礎づける証拠の写しも提出するのが通常ですが,東京地裁の運用では,労働審判委員には,申立書,答弁書等の主張書面のみが事前に送付され,証拠の写しについては送付されない扱いとなっています。
労働審判員は,他の担当事件のために裁判所に来た際などに,証拠を閲覧し,詳細な手控えを取ったりして対応しているようですが,自宅で証拠と照らし合わせながら主張書面を検討することはできません。
また,労働審判官(裁判官)も大量の事件を処理していますので,答弁書を読んだだけで言いたいことが明確に伝わるようにしておかないと,真意が伝わらない恐れがあります。
答弁書作成に当たっては,答弁書が労働審判委員会を「説得」する手段であり,労働審判委員会に会社の主張を理解してもらえずに不当な結論が出てしまった場合は,労働審判委員会が悪いのではなく,労働審判委員会を説得できなかった自分たちに問題があったと受け止めるスタンスが重要となります。
労働審判委員会は,申立書,答弁書の記載内容から,事前に暫定的な心証を形成して第1回期日に臨んでいます。
また,第1回期日は,時間が限られている上,緊張して言いたいことが思ったほど言えないことが多いというのが実情です。
したがって,労働審判手続において相手方とされた使用者側としては,重要な証拠内容は答弁書に引用するなどして,答弁書の記載のみからでも,主張内容が明確に伝わるようにしておくべきことになります。
陳述書を答弁書と別途提出するのは当事者の自由ですが,重要ポイントについては,答弁書に盛り込んでおくことが必要となります。
答弁書の記述で言いたいことが伝わるのであれば,答弁書と同じような内容の陳述書を別途提出する必要はありません。
第1回期日おける審理では,事情をよく知る担当者が事実関係を説明しないことにはリアリティーがありませんから,会社担当者が事実説明をしていくことになります。
解雇した際の言葉のやり取り等の重要な事実関係を,解雇の場にいたわけでもない代理人弁護士が説明したのでは,説得力がありません。
したがって,期日には代理人弁護士が出頭するだけでは足りず,紛争の実情を把握している会社担当者が2名程度,出頭する必要があります。
しかし,会社担当者は裁判所の手続に不慣れなことが多いため,緊張して事実を正確に伝えることができなくなりがちです。
言いたいことが言えないまま終わってしまうことがないようにするためには,事前に提出する答弁書に言いたいことをしっかり盛り込んでおいて当日話さなければならないことをできるだけ減らしておくべきでしょう。
なお,どうしても代理人弁護士だけしか出席できない場合は,代理人弁護士が,労働審判委員会からの質問に答えざるを得ませんが,解雇等の場にいたわけでもない代理人弁護士が質問に対して十分な回答をすることは困難です。
事前の打合せの負担が重くなるのみならず,事情をよく知る担当者が出頭した場合と比較して,会社にとって不利な結果となることを覚悟する必要があります。
労働審判の第1回期日にかかる時間についてですが,2時間程度はかかるものと考えておく必要があります。
私がこれまでに経験した労働審判事件の第1回期日は,1時間20分~2時間30分程度かかっています。
事案の複雑さの程度にもよりますが,同程度の事件であれば,申立書,答弁書において,充実した主張反論がなされているケースの方が,所要時間が短くなる傾向にあります。
第2回以降の期日は,第1回期日で実質的な審理が終了し,労働審判委員会から調停案が示されていたような場合には,解決金の金額を中心とした調停内容についての調整がなされることになり,当事者双方が調停案を直ちに受け入れたような場合は,期日は30分足らずで終了することになります。
ただし,第2回以降の期日であっても,当事者双方が調停案を直ちに受け入れなかったものの,もう少しで調停が成立しそうな状況だったため,その日のうちに調停を成立させるために交渉が継続され,約2時間30分かかったことがありました。
また,当事者から新たな主張がなされ,それが審理されることになったような場合も,時間がかかる可能性があります。
第2回期日以降についても,2~3時間程度は時間が取られても支障が生じないよう,スケジュールを空けておくべきでしょう。
弁護士 藤田 進太郎