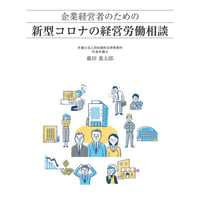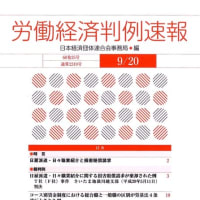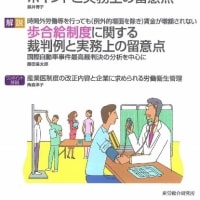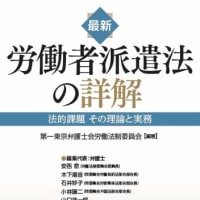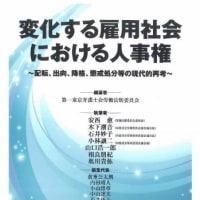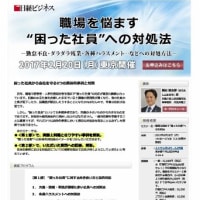36協定を締結する当事者は,どのように選出すればいいですか?
1 36協定の締結者
労基法では,1週40時間または1日8時間を超えて労働させてはならないこととされており(労基法32条),これを超えて労働させることは,原則として禁止されています。
この例外として,労基法36条1項では,労使協定(36協定)の締結および届出を要件として,時間外労働や休日労働を許容しています。
具体的には,使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で書面による協定をして,これを行政官庁に届けることにより,法定時間外労働を適法に行わせることが可能になっています。この労使協定を「36協定」といいます。
2 労働者側当事者
労働者側の当事者は,上記のとおり,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者,のいずれかです。
ただし,どちらでもいいというわけではなく,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は,必ず当該労働組合を締結の当事者とする必要があります。
労働者の過半数で組織する労働組合とは,当該事業場の全労働者のうち,過半数が加入している労働組合のことをいいます。全労働者の過半数が加入している限りは36協定の締結当事者になることができるということは,たとえば,複数の事業場を包括する労働組合や,企業外の労働組合であっても,締結当事者になることができます。
労働者の過半数を代表するものについては,労基法施行規則6条の2において,次の要件が定められています。
①労基法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
②「投票、挙手等の方法」とあるとおり,必ずしも投票,挙手である必要はありません。この点については,通達では,「労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。」(平11.3.31基発169号)と述べられていますので,投票,挙手以外にも様々な方法が考えられ,労働者の意思が反映される民主的な手続である限りは問題ないことになります。
3 使用者側当事者
36協定の使用者側の当事者については,労基法36条1項では「使用者」と定めるのみであり,それ以外の特別な要件は特に定められていません。
「使用者」の意義については,労基法10条及び通達において,それぞれ次のように解釈が示されています。
・労基法10条 この法律で使用者とは,事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう。
・通達(昭22.9.13基発17号) 「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい,その認定は部長,課長等の形式にとらわれることなく各事業において,本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによる。
したがって,使用者側の当事者は,企業の代表者のみに限らず,当該企業において36協定の締結権限を有している者であれば,役職に関わらず,36協定の使用者側当事者になることができます。
――――――――――――