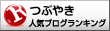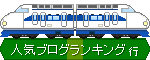今朝の信州は、寒さもちょっぴり緩みましたが氷点下
1度、空は雲が2割位占めていて東と西の空は雲に覆
われています。
今日は、いよいよ「冬至」となりました。私は、この
冬至がいつも待つどおしくいよいよ明日から昼間の時
間が伸びると思うとウキウキしてしまいます。
冬至とは、1年で最も昼の時間が短く、夜が最も長い日
です。二十四節気の1つで、天文学的に毎年12月21日か
22日とされています。今年の冬至は12月21日でした。
冬至は「冬に至る」という言葉の通り、本格的に寒く
なってくる時期になります。冬至以降は徐々に日が長
くなっていくことから、運気上昇、無病息災などを願
って冬至を祝う風習が日本ばかりでなく、世界各国で
見られるようです。日本で冬至といえば、かぼちゃと
ゆず湯! 柚子を入れたお風呂に入るのは風邪をひかな
いため、かぼちゃが冬至の日の食べ物なのは運盛りの
語呂合せ??とはよく知られる由来ですが、なぜ??
がぼちゃ・柚子・。なのかと検索してみました。
かぼちゃは別名「なんきん」で運盛りのひとつですが
漢字では「南瓜」と書きます。冬至は陰が極まり
再び陽にかえる日なので、陰(北)から陽(南)へ
向かうことを意味しており、冬至に最もふさわしい食
べものになったようです。
又、かぼちゃはビタミンAやカロチンが豊富なため、
又、かぼちゃはビタミンAやカロチンが豊富なため、
風邪や中風(脳血管疾患)予防に効果的があるようです
本来かぼちゃの旬は夏ですが、長期保存が効くことから
冬に栄養をとるための賢人の知恵でもあるようです。
また、冬至といえば柚子湯が欠かせません。どうせ単
なる語呂合わせでしょ、なんて思っていたら大間違い。
ゆず湯の由来とやり方について紹介します。
冬至の日、柚子湯に入ると風邪をひかずに冬を越せる
冬至の日、柚子湯に入ると風邪をひかずに冬を越せる
と言われています。柚子(ゆず)=「融通」がきく、
冬至=「湯治」。こうした語呂合せから、冬至の日に
ゆず湯に入ると思われていますが、もともとは運を呼
びこむ前に厄払いするための「禊」(みそぎ)だと考え
られています。昔は毎日入浴しませんから一陽来復の
ために身を清めるのも道理で、現代でも新年や大切な
儀式に際して入浴する風習があります。冬が旬の柚子
は香りも強く、強い香りのもとには邪気がおこらない
という考えもありました。端午の節句の菖蒲湯も同様
のようです。更に、柚子は実るまでに長い年月がかか
るので、長年の苦労が実りますようにとの願いも込め
られています。もちろん、ゆず湯(柚子湯)には血行
を促進して冷え性を緩和したり、体を温めて風邪を予防
したり、果皮に含まれるクエン酸やビタミンCによる
美肌効果があります。さらに、芳香によるリラックス
効果もありますから、元気に冬を越すためにも大いに
役立つとのことです。
我が家でも昨日、本家の姉さんからカボチャ団子が届
き今日は近くのスーパーで柚子を買って風呂に浮かべ
て今日の「冬至」を迎えたい。
写真は愛知県の豊田市からの帰りの道中です










コメント欄はお休みさせて頂いております