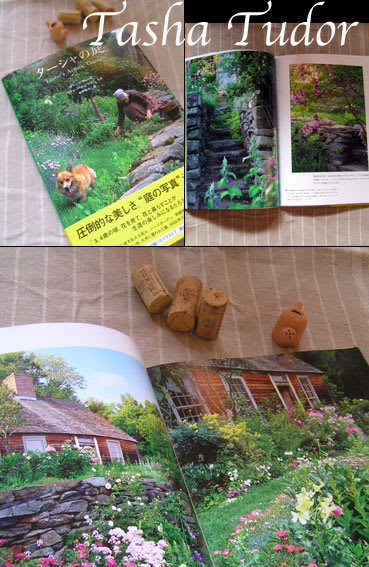「マコ、甘えてばかりでごめんね。ミコはとってもしあわせなの。」
私が幼き頃、母がこの歌をよく口ずさんでいたことを覚えています。
なんとも淋しく、悲しくなるようなメロディーで、
私はあまり好きではありませんでした。
これはその当時放映されたドラマ「愛と死をみつめて」の主題歌だったそうで、
私は最近まで、その時流行ったフィクションの恋愛ドラマだと思っていました。
しかし、これはれっきとしたノンフィクションです。
阪大病院で、軟骨肉腫と呼ばれる難病のために、左半分の顔を失い、
短き命を生きようとする大島みち子さんと、
そういう彼女を受け止め、愛し、心から支えた河野実さんの
文通を通しての3年余りの間の純愛の記録です。
今、何十年という時を経て、
リメークされた「愛と死をみつめて」(広末涼子&草なぎ剛がミコ&マコ役)
がドラマ化された事に大いに興味を持ち、
是非本書を読んでみたいという欲求にかられた次第です。
母から聞いた話ですが、
マコさん(河野実さん)がみち子さんの死後、
数ヶ月でこの本を出版し、まもなく結婚までしてしまった・・
ということから、マスコミからの非難が絶えなかったそうです。
また、当時この本がベストセラーとなったために、
「2人の清い交際を売り物にして、印税でお金儲けをしている」とか、
「結婚は、亡くなったみち子さんへのうらぎり行為である」とされ、
世間のマコさんへの風当たりはとても厳しいものだったようです。
しかし、実際この手記を読んで、
それは大いに間違いであることに私は気づきました。
みち子さんは、マコさんへの手紙の中でこう語っています。
結婚に関しては、
「マコ、万一の場合、男らしくあきらめて、
また新しい人生の幸せを探して下さい。
マコを幸せにしてくれる人を一生懸命さがして
うんと幸せな家庭を築いて下さい。」
と書かれています。
そして、ドラマの中でマコさんと結婚した奥さん(小雪)がマスコミに語ったように、
「私も、実さんも、そしてみち子さんも、
誰かの支えがなければ、生きてはいけない弱い人間なんです。」
というセリフにも主張があるように思います。
残された者は、生きていかなければならない。
どんなに辛くても、生き抜かなければならない。
マスコミは、一生マコさんに、みち子さんの思い出だけを背負って
独身を貫けとでも言うのでしょうか?
人間は弱い者です。
弱いが故に、誰かを愛し、
お互いを支え合いながら生きていくのではないでしょうか。
そんな事もわからない、当時のマスコミに憤りを感じます。
本の出版に対しては
「(中略)こんな愛情も存在し得るのですと証明するのに、
本にすることは役立つかもしれません。
(中略)私は~マコのようなすばらしい愛を持った男性がいることを
世に知らせたい~」
とあるように、本を出版することは生前のみち子さんの希望でもあったことが
伺われます。
また、本を出版することによって、希望を与えられ、
力づけられる人もいるであろうことも述べられています。
ベストセラー云々は、あとからついてきた、あくまでも結果でした。
人はマスコミの報道や人のうわさに惑わされやすい傾向があります。
そして憶測や思いこみで、人を判断したり中傷したりします。
それはとても罪深いことであるし、悲しいことだと思います。
物事を鵜呑みにするのではなく、
真実を知ること、知ろうとすることが大切だと思いました。
「生活については、常に満足せよ。
しかし、自分自身については、満足するな」(G.J.ネーサン)
これは、みち子さんが自らの日記に記したG.J.ネーサンの言葉です。
変えられない環境や生活に対しては、感謝の気持ちを持ち、
自分自身に対しては、いつも満足することなく向上していく努力をする。
とても深く心に残るメッセージでした。
また以下のようにも記されています。
「マコ、こまったときこそ、じぶんがいきていることにかんしゃし
じっくりかまえましょう。」
「苦しみのない人は喜びも小さいと思うのです。
健康な人が健康がありがたいと思わないのと同じように、
いつも幸せな人は幸せというものをかんがえないでしょう。
私はどんなちっぽけな幸せや喜びでも大事にしたいと思うのです。」
「私たちは身近にあるものを、あまりに遠くかけはなれたところでさがしている。」
長い年月を経て、みち子さんから受け取ったメッセージの数々・・
深く心に刻んで、人生を歩んでいく上での指針としたいです。



 今日のお弁当♪
今日のお弁当♪












 今日は、シブイ渋い本のお話です。
今日は、シブイ渋い本のお話です。



 )
)






 「生ジュース・ダイエット健康法」
「生ジュース・ダイエット健康法」 「フルーツで野菜で!生ジュースダイエット」
「フルーツで野菜で!生ジュースダイエット」 上記のナターシャ・スタルヒン著作の書籍、
上記のナターシャ・スタルヒン著作の書籍、