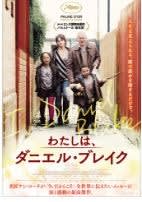「われに撃つ用意あり READY TO SHOOT」 1990年 日本

監督 若松孝二
出演 原田芳雄 桃井かおり ルー・シュウリン
蟹江敬三 松田ケイジ 室田日出男
石橋蓮司 山口美也子 小倉一郎
佐野史郎 麿赤兒 山谷初男
ストーリー
新宿・歌舞伎町。スナック“カシュカシュ”のマスター郷田克彦の前に、ヤクザに追われている女が現れる。
女の名はヤン・メイラン、台湾人である。
その頃、外では桜道会系戸井田組々長が銃殺される事件が発生し、新宿署のマル暴刑事・軍司が捜査を開始していた。
殺人現場にはVHS-Cビデオのアダプターが残されていたが中身のテープはなかった。
一方“カシュカシュ”では20年間続いたこの店の閉店パーティが行われており、克彦のかつての全共闘の同志である季律子、秋川、三宅らが集っていた。
中にはメイランの姿も見え、実は彼女がベトナム難民であり、偽造パスポートを持つ密国入者であることが判明する。
逃走のためのパスポートを取りに店を出たメイランは、戸井田組に追われるが克彦はそんな彼女を救出する。
一方、事件を追う軍司は、戸井田組がタイの女にパスポートをネタに売春させ、その女に組長が殺されたらしいことと、女がビデオテープを持っていることをつきとめた。
時を同じくして香港ヤクザが戸井田組々員を殺害する事件が起り、そこで軍司はビデオテープを発見する。
それは桜道会桜田のフィリピン女の殺人シーンだった。
メイランは克彦と仲間に戸井田に脅され、犯されそうになった時、銃が暴発して戸井田を殺してしまったことを打ち明ける。
そして対策を練っていた時、秋川が香港ヤクザに殺されてしまい、メイランもさらわれてしまう。
克彦は一人でメイランを救出することを決意、季律子は克彦と行動を共にして、二人はリボルバーを手に香港ヤクザのいるフィリピンパブへ向った。
寸評
郷田(原田芳雄)の店が閉店することになり、最後の日はなじみ客が集まって無料招待の閉店パーティを楽しむのだが、集まったのは郷田と同じ元全共闘のメンバー達がほとんどである。
そこで交わされる会話は僕たちの全共闘世代にはピタリとはまる。
僕はゲバ棒などを振り回した闘争派ではなく、いわゆるノンポリの日和見的な学生であったが、それでも1968年10月21日に東京都新宿区で発生した暴動事件は記憶にあり当時の熱気を思い起こす。
中核派などが明治公園及び日比谷野外音楽堂で集会を行った後、角材等で武装しながら続々と約2000人が新宿駅に集結して各所で機動隊と衝突したというものである。
郷田たちはその生き残りである。
今や彼等はいろんな職業に就いていて、スナックのマスターである郷田をはじめ、雑誌記者や都議会議員、予備校の講師などさまざまである。
彼等が当時の状況を語るシーンを今の僕が見ると、まさに僕自身でもあるように感じさせる。
学生運動でなくても、あらゆることに熱気をはらんでいた当時の世相とその中にいた僕自身を回顧する姿だ。
そしてその姿を見るとかつての情熱がどこかへ消え去ってしまったようで淋しさを感じる自分である。
そんなところへベトナム戦争の被害者と言ってもいいヤン・メイラン(呂?菱ルー・シュウリン)が逃げ込んでくる。
映画の構成的にベトナム戦争反対も当時の学生運動のスローガンの一つであった事と無縁ではない。
彼女とヤクザ組織のもめ事が原因で、これまた全共闘仲間で今はジャイアンツ狂いの秋川(石橋蓮司)が殺されてしまう。
その場面になって一番慌てふためくのが都議会議員となっている今井江里子(山口美也子)であるのは、社会的立場を重んじてきていることを伺わせて面白い。
郷田と李津子(桃井かおり)はかつて肉体関係があったようが、李津子は雑誌記者となって別の男性と所帯を持っていそうだ。
しかし李津子は郷田と共にヤン・メイランの救出に向かう。
深い絆で結びついているような郷田と李津子の雰囲気は何かしら暖かいものを感じさせられる。
なぜにそこまでヤン・メイランに肩入れするのかはよくわからないが、彼女がタイ国籍ながら元はベトナム人であることがその動機となっていると思うし、ベトナム反戦運動にかかわっていたことと無縁ではないだろう。
この二人が醸し出す雰囲気はすごくいい。
二人とも独特のセリフ回しを持っていて、特にけだるい話し方をする桃井かおりは面白い。
銃撃戦で腹部を撃たれて「撃たれたことがないからわかんなかったわよ」なんて最高だ。
再見すると、二人が寄り添うラストシーンは僕たちの者には郷愁をそそるたまらないシーンで、原田芳雄の渋い歌が流れると青春時代を思い出してしまう。
若松孝二はピンク映画の旗手というイメージのあった監督だが、やがて一般映画と呼んでいいジャンルの作品を撮るようになった。
社会性のあるテーマを持った作品を世に出したが、それらは難解なものではない骨太の作品だったように思う。
本作は僕にとってそれらの走りとなった作品である。

監督 若松孝二
出演 原田芳雄 桃井かおり ルー・シュウリン
蟹江敬三 松田ケイジ 室田日出男
石橋蓮司 山口美也子 小倉一郎
佐野史郎 麿赤兒 山谷初男
ストーリー
新宿・歌舞伎町。スナック“カシュカシュ”のマスター郷田克彦の前に、ヤクザに追われている女が現れる。
女の名はヤン・メイラン、台湾人である。
その頃、外では桜道会系戸井田組々長が銃殺される事件が発生し、新宿署のマル暴刑事・軍司が捜査を開始していた。
殺人現場にはVHS-Cビデオのアダプターが残されていたが中身のテープはなかった。
一方“カシュカシュ”では20年間続いたこの店の閉店パーティが行われており、克彦のかつての全共闘の同志である季律子、秋川、三宅らが集っていた。
中にはメイランの姿も見え、実は彼女がベトナム難民であり、偽造パスポートを持つ密国入者であることが判明する。
逃走のためのパスポートを取りに店を出たメイランは、戸井田組に追われるが克彦はそんな彼女を救出する。
一方、事件を追う軍司は、戸井田組がタイの女にパスポートをネタに売春させ、その女に組長が殺されたらしいことと、女がビデオテープを持っていることをつきとめた。
時を同じくして香港ヤクザが戸井田組々員を殺害する事件が起り、そこで軍司はビデオテープを発見する。
それは桜道会桜田のフィリピン女の殺人シーンだった。
メイランは克彦と仲間に戸井田に脅され、犯されそうになった時、銃が暴発して戸井田を殺してしまったことを打ち明ける。
そして対策を練っていた時、秋川が香港ヤクザに殺されてしまい、メイランもさらわれてしまう。
克彦は一人でメイランを救出することを決意、季律子は克彦と行動を共にして、二人はリボルバーを手に香港ヤクザのいるフィリピンパブへ向った。
寸評
郷田(原田芳雄)の店が閉店することになり、最後の日はなじみ客が集まって無料招待の閉店パーティを楽しむのだが、集まったのは郷田と同じ元全共闘のメンバー達がほとんどである。
そこで交わされる会話は僕たちの全共闘世代にはピタリとはまる。
僕はゲバ棒などを振り回した闘争派ではなく、いわゆるノンポリの日和見的な学生であったが、それでも1968年10月21日に東京都新宿区で発生した暴動事件は記憶にあり当時の熱気を思い起こす。
中核派などが明治公園及び日比谷野外音楽堂で集会を行った後、角材等で武装しながら続々と約2000人が新宿駅に集結して各所で機動隊と衝突したというものである。
郷田たちはその生き残りである。
今や彼等はいろんな職業に就いていて、スナックのマスターである郷田をはじめ、雑誌記者や都議会議員、予備校の講師などさまざまである。
彼等が当時の状況を語るシーンを今の僕が見ると、まさに僕自身でもあるように感じさせる。
学生運動でなくても、あらゆることに熱気をはらんでいた当時の世相とその中にいた僕自身を回顧する姿だ。
そしてその姿を見るとかつての情熱がどこかへ消え去ってしまったようで淋しさを感じる自分である。
そんなところへベトナム戦争の被害者と言ってもいいヤン・メイラン(呂?菱ルー・シュウリン)が逃げ込んでくる。
映画の構成的にベトナム戦争反対も当時の学生運動のスローガンの一つであった事と無縁ではない。
彼女とヤクザ組織のもめ事が原因で、これまた全共闘仲間で今はジャイアンツ狂いの秋川(石橋蓮司)が殺されてしまう。
その場面になって一番慌てふためくのが都議会議員となっている今井江里子(山口美也子)であるのは、社会的立場を重んじてきていることを伺わせて面白い。
郷田と李津子(桃井かおり)はかつて肉体関係があったようが、李津子は雑誌記者となって別の男性と所帯を持っていそうだ。
しかし李津子は郷田と共にヤン・メイランの救出に向かう。
深い絆で結びついているような郷田と李津子の雰囲気は何かしら暖かいものを感じさせられる。
なぜにそこまでヤン・メイランに肩入れするのかはよくわからないが、彼女がタイ国籍ながら元はベトナム人であることがその動機となっていると思うし、ベトナム反戦運動にかかわっていたことと無縁ではないだろう。
この二人が醸し出す雰囲気はすごくいい。
二人とも独特のセリフ回しを持っていて、特にけだるい話し方をする桃井かおりは面白い。
銃撃戦で腹部を撃たれて「撃たれたことがないからわかんなかったわよ」なんて最高だ。
再見すると、二人が寄り添うラストシーンは僕たちの者には郷愁をそそるたまらないシーンで、原田芳雄の渋い歌が流れると青春時代を思い出してしまう。
若松孝二はピンク映画の旗手というイメージのあった監督だが、やがて一般映画と呼んでいいジャンルの作品を撮るようになった。
社会性のあるテーマを持った作品を世に出したが、それらは難解なものではない骨太の作品だったように思う。
本作は僕にとってそれらの走りとなった作品である。