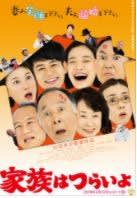「火宅の人」 1986年 日本

監督 深作欣二
出演 緒形拳 いしだあゆみ 原田美枝子
松坂慶子 利根川龍二 一柳信之
大熊敏志 谷本小代子 檀ふみ
石橋蓮司 蟹江敬三 井川比佐志
宮内順子 真田広之 岡田裕介
ストーリー
作家、桂一雄(緒形拳)は、最初の妻リツ子に死なれ、後妻としてヨリ子(いしだあゆみ)をもらった。
ヨリ子は腹ちがいの一郎(利根川龍二)をはじめ、次郎(一柳信之)、弥太(大熊敏志)、フミ子(米沢由香)、サト子(岡村真美)と5人の子供を育ててきた。
昭和31年、夏、一雄は新劇女優、矢島恵子(原田美枝子)と事をおこした。
8年前の秋、彼女が知人の紹介状を持って訪ねて来て以来、その率直さに心魅かれていたのだ。
そんな時、一雄の身辺に凶事が重なった。
一昨年の夏は、奥秩父で落石に遭い助骨3本を骨折し、昨年の夏は、次郎が日本脳炎にかかって言葉も手足も麻痺してしまい、そして今年の夏、一雄は太宰治(岡田裕介)の文学碑の除幕式に参列するための青森行に恵子を誘ってしまった。
ヨリ子は次郎の事があってから、怪しげな宗教の力にすがるようになっていた。
青森から帰った一雄から、全てを打ち明けられたヨリ子は翌日家出し、一週間すぎても連絡はない。
ある嵐の夜、ヨリ子は覚悟を決めたと戻ってきたが、一雄は家を出て恵子と新しい生活をはじめる。
一雄は若々しい恵子との情事のとりこになっていった。
恵子が妊娠するが二人は派手な喧嘩をし、東京を離れた一雄は、五島列島行の連絡船にとび乗った。
彼はそこで、京都で怪我をした時介抱してくれた女性、葉子(松坂慶子)に再会した。
義父に犯された暗い過去を持つ彼女は、10年ぶりに里帰りしたのだ。
葉子は、あてのない一雄の旅の道連れとなったが、クリスマスの夜一人で旅立って行った。
東京へ戻り、久々に正月を家族と過ごすことになった一雄のもとに、次郎の死が知らされる。
次郎の葬儀の日、恵子から一雄の荷物が届けられた。
寸評
原作の同名小説は、愛人関係にあった舞台女優・入江杏子との生活、そして破局を描いたものとのことなのだが、未読なので私小説として事実との相違点や、原作と映画の違いなどは知る由もない。
僕は緒形拳が演じる桂一雄は最後の無頼派と言われた檀一雄その人だろうと思って見ている。
劇中でも「長恨歌」で直木賞がとれたと仲間が報告しているのだから、なぜ主人公を壇一雄としなかったのかと思ってしまうのだが、登場人物はそれとわかる名前ながら全員仮名となっている。
冒頭で檀一雄の長女である檀ふみさんが大学生と駆け落ちする一雄の母親役で出演している。
ドキュメンタリーではないので、まあ名前の件は大した問題ではない。
映画は女がいないと生きていけないぐうたらな男の物語である。
一雄は女に対して正直で優しいのだが、愛人と関係を持っても悪びれたところを見せない不道徳な男でもある。
日本脳炎にかかり麻痺が生じた二男を含め、5人の子供の面倒を妻に押し付け、放蕩を繰り返している。
若い原田美枝子や松坂慶子の脱ぎっぷりもいいが、取り乱すことなく怒りや悲しみを秘めた妻ヨリ子を演じたいしだあゆみが居てこその作品である。
恵子宅に泥棒に入った一郎が検挙され、一雄と恵子が警察を訪れたところへ本妻のヨリ子がやって来る。
恵子と大立ち回りになっても良いところなのだが、ヨリ子は恵子のおでこをピシャリと叩いて治まっている。
ヨリ子の恵子に対する思いが表現された上手い演出だ。
一雄が持って帰ってきたブリをさばく時の包丁使いにも秘めた感情が出ていたように思う。
ふと浮かべるわずかな微笑でこの女性のしたたかさを感じさせたのだが、そんな表情を見せるいしだあゆみは演技者として上手い。
知人の紹介状を持って訪ねて来た舞台女優の矢島恵子は愛人として一雄の子供を身ごもる。
一雄は産みたければ産めばいいし、その時は責任を取って認知すると言うのだが、恵子は舞台でいい役がもらえる大事な時だからと堕胎を選択する。
一方の一雄は原稿の締め切りが迫っていると病院に付き添うこともしないのだが、肉体だけの関係ではなくお互いに愛し合っているようでもある不思議な関係である。
しかし一雄は母親がとったように家庭を捨て去るようなことはしないし、太宰の様に情死することもない。
一雄も恵子も自分の気持ちのままに都合よく生きているように見え、普通の人には出来ない生き方である。
妻のヨリ子は「あなたのすることは何でも分かっています」と言い、一雄の行動を黙認している。
一雄は太宰治の記念碑の除幕式に恵子を連れていくが、妻のヨリ子はその事を察知しながら止めない。
一雄を子供たちの父親として迎えるが、夫としては迎えないと言う関係で一緒に暮らすという不思議な精神を持った女性なのだが、最後に見せる笑顔に僕は彼女の心の奥底を見いだせなかった。
偶然出会った葉子とも関係を結ぶが、彼女との放浪の旅の映像は美しい日本の景色を切り取ったものだ。
童心に帰ったような二人の姿は実に楽しそうだ。
この美しさの中で、一雄は自分の生き方にあらがうことも出来ず、ただ思いのままに快楽を求め続ける。
羨ましい限りの生き方だが、そんな生き方は誰もが出来るわけではないし、背徳の生き方だ。
それを貫いた檀一雄に感心してしまう。

監督 深作欣二
出演 緒形拳 いしだあゆみ 原田美枝子
松坂慶子 利根川龍二 一柳信之
大熊敏志 谷本小代子 檀ふみ
石橋蓮司 蟹江敬三 井川比佐志
宮内順子 真田広之 岡田裕介
ストーリー
作家、桂一雄(緒形拳)は、最初の妻リツ子に死なれ、後妻としてヨリ子(いしだあゆみ)をもらった。
ヨリ子は腹ちがいの一郎(利根川龍二)をはじめ、次郎(一柳信之)、弥太(大熊敏志)、フミ子(米沢由香)、サト子(岡村真美)と5人の子供を育ててきた。
昭和31年、夏、一雄は新劇女優、矢島恵子(原田美枝子)と事をおこした。
8年前の秋、彼女が知人の紹介状を持って訪ねて来て以来、その率直さに心魅かれていたのだ。
そんな時、一雄の身辺に凶事が重なった。
一昨年の夏は、奥秩父で落石に遭い助骨3本を骨折し、昨年の夏は、次郎が日本脳炎にかかって言葉も手足も麻痺してしまい、そして今年の夏、一雄は太宰治(岡田裕介)の文学碑の除幕式に参列するための青森行に恵子を誘ってしまった。
ヨリ子は次郎の事があってから、怪しげな宗教の力にすがるようになっていた。
青森から帰った一雄から、全てを打ち明けられたヨリ子は翌日家出し、一週間すぎても連絡はない。
ある嵐の夜、ヨリ子は覚悟を決めたと戻ってきたが、一雄は家を出て恵子と新しい生活をはじめる。
一雄は若々しい恵子との情事のとりこになっていった。
恵子が妊娠するが二人は派手な喧嘩をし、東京を離れた一雄は、五島列島行の連絡船にとび乗った。
彼はそこで、京都で怪我をした時介抱してくれた女性、葉子(松坂慶子)に再会した。
義父に犯された暗い過去を持つ彼女は、10年ぶりに里帰りしたのだ。
葉子は、あてのない一雄の旅の道連れとなったが、クリスマスの夜一人で旅立って行った。
東京へ戻り、久々に正月を家族と過ごすことになった一雄のもとに、次郎の死が知らされる。
次郎の葬儀の日、恵子から一雄の荷物が届けられた。
寸評
原作の同名小説は、愛人関係にあった舞台女優・入江杏子との生活、そして破局を描いたものとのことなのだが、未読なので私小説として事実との相違点や、原作と映画の違いなどは知る由もない。
僕は緒形拳が演じる桂一雄は最後の無頼派と言われた檀一雄その人だろうと思って見ている。
劇中でも「長恨歌」で直木賞がとれたと仲間が報告しているのだから、なぜ主人公を壇一雄としなかったのかと思ってしまうのだが、登場人物はそれとわかる名前ながら全員仮名となっている。
冒頭で檀一雄の長女である檀ふみさんが大学生と駆け落ちする一雄の母親役で出演している。
ドキュメンタリーではないので、まあ名前の件は大した問題ではない。
映画は女がいないと生きていけないぐうたらな男の物語である。
一雄は女に対して正直で優しいのだが、愛人と関係を持っても悪びれたところを見せない不道徳な男でもある。
日本脳炎にかかり麻痺が生じた二男を含め、5人の子供の面倒を妻に押し付け、放蕩を繰り返している。
若い原田美枝子や松坂慶子の脱ぎっぷりもいいが、取り乱すことなく怒りや悲しみを秘めた妻ヨリ子を演じたいしだあゆみが居てこその作品である。
恵子宅に泥棒に入った一郎が検挙され、一雄と恵子が警察を訪れたところへ本妻のヨリ子がやって来る。
恵子と大立ち回りになっても良いところなのだが、ヨリ子は恵子のおでこをピシャリと叩いて治まっている。
ヨリ子の恵子に対する思いが表現された上手い演出だ。
一雄が持って帰ってきたブリをさばく時の包丁使いにも秘めた感情が出ていたように思う。
ふと浮かべるわずかな微笑でこの女性のしたたかさを感じさせたのだが、そんな表情を見せるいしだあゆみは演技者として上手い。
知人の紹介状を持って訪ねて来た舞台女優の矢島恵子は愛人として一雄の子供を身ごもる。
一雄は産みたければ産めばいいし、その時は責任を取って認知すると言うのだが、恵子は舞台でいい役がもらえる大事な時だからと堕胎を選択する。
一方の一雄は原稿の締め切りが迫っていると病院に付き添うこともしないのだが、肉体だけの関係ではなくお互いに愛し合っているようでもある不思議な関係である。
しかし一雄は母親がとったように家庭を捨て去るようなことはしないし、太宰の様に情死することもない。
一雄も恵子も自分の気持ちのままに都合よく生きているように見え、普通の人には出来ない生き方である。
妻のヨリ子は「あなたのすることは何でも分かっています」と言い、一雄の行動を黙認している。
一雄は太宰治の記念碑の除幕式に恵子を連れていくが、妻のヨリ子はその事を察知しながら止めない。
一雄を子供たちの父親として迎えるが、夫としては迎えないと言う関係で一緒に暮らすという不思議な精神を持った女性なのだが、最後に見せる笑顔に僕は彼女の心の奥底を見いだせなかった。
偶然出会った葉子とも関係を結ぶが、彼女との放浪の旅の映像は美しい日本の景色を切り取ったものだ。
童心に帰ったような二人の姿は実に楽しそうだ。
この美しさの中で、一雄は自分の生き方にあらがうことも出来ず、ただ思いのままに快楽を求め続ける。
羨ましい限りの生き方だが、そんな生き方は誰もが出来るわけではないし、背徳の生き方だ。
それを貫いた檀一雄に感心してしまう。