

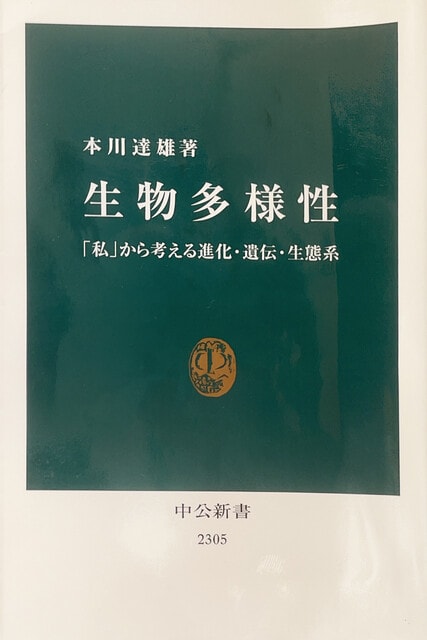
三冊を読んだ。3冊とも共通しているものを持つ。
『農は輝ける』(山下惣一 星寛治 対談集)
『北の農民 南の農民』の発刊後、約30年たって企画された対談。
2011年、東日本大震災直前とその年の暮れと2回行われた対談の収録。
司会進行は新潟県阿賀野市笹神地域で有機農業をやっている石塚美津夫さん。
・TPP問題だけでなく一連の制度改革を「民(企業)へ」の構造改革としてとらえ、その是非から論じていく。
また、話は脱原発や生き方論へと広範に発展していく。
農業も漁業も(企業がのっとってもかまわないが、)
我々はそこに住んで暮らしと生産が一体だから大事に守り続けるが、
企業はどうか? 生産だけしかしない人が、守るわけないじゃないか。
(私としては、よく砂川議員が言っていたことを思い出す)
・若い人にも魅力がある、収入も高い農業にするためにどうしたらよいか?! という会場からの問いに
山下さん、
「今のままでいいじゃないか、堆肥をつくって循環農業をやっているではないか。変えなければ、という発想に立つのが間違え。親が死ねば子は戻ってくる。」
星さん
「人間のつながり、自然と人間のつながり、生産者と市民のつながりの豊かさに焦点を絞る。経済成長しないと幸せは得られないという先入観から抜け出してみること。フランスやイギリスでは脱成長「経済成長無き発展とは何か」に向けて探求が始まっている。オバマの提唱するグリーンニューディールも、前提としては経済成長しないと幸せではない、からきている。それを追求したら結局は環境破壊に行きつく。もっと別のライフスタイルを考えていくことが大事。」
『はじめて学ぶ 環境倫理」吉永明弘著
環境倫理とは、自分は日々の生活で個人がどう工夫するか、というような類のものではなく、
もっと国や世界に問うものだ。つまり、「システム」「制度」をどうすべきかと考えるものである。
環境倫理には次の3つの考え方がある。
1、自然の生存権 人間も動物も植物も…生態系も景観も生存権を持っている。
2,世代間倫理 今の世代は未来の世代に責任を持つ
3,地球全体主義 地球の生態系は互いに影響しあい、閉じていている。
これらを、わかりやすく紐解いて問うた本がこの本ともいえよう。
・世代間倫理においては、資源よりごみの方が影響がある。
「耐用期間 > 使用期間」
ごみは使われる時間より、使える時間が長い。レジ袋は1時間くらい使われるだけだが、何十年と分解されずにもつ。
だから、長く使うものをつくる、という発想も環境倫理に叶う。100年住宅も一例。
1軒の家を解体すると1人の一生分の量と同じごみがでる、らしい。それまでいくら努力してても、それで元の木阿弥。長く保つ家を。
最悪が核のゴミ。核廃棄物はサ終始末10万年間影響が残る。フィンランドではオンカロという施設で地中深くに埋設したが、文字とともに記号などで「掘るな」と記しているという。文字は永久ではない。だが、後世の人が発掘したら終わりだし、隕石が当たっても終わりだ。
・CO2削減ももっと生産側の責任を負うべき。個人消費とは規模が違う。企業もグリーンウォッシュしがち。
昔、衆議院環境委員会に呼ばれた時、2人の識者が 投資と税制に切り込むべき、と主張していたのを思い出す。
お二人の主張は、世界の投資家は環境への貢献度合い(効果)を見て投資先を決めるのが今の主流だから、
その客観的指標をはやく日本でも作って投資家に示さないと資本が逃げる。環境税なども早く導入すべき。
というものだった。
・「保全」と「保存」の違いは、前者は人間が手を入れながらも守っていくことを含むが、後者は人間が手を付けないままを意味する。アメリカの環境主義者は「保存」派が多い。日本は「保全」。
・「都市」は地球の持続可能性に貢献できる。だって、「都市」こそ資源、エネルギーが節約できるからだ。
そのカギは「集住」と「公共交通」にある。豊かな住環境(アメニティ)を実感しつつ住み続けるために「アメニティマップ」を作ることも効果ある。良いところと改善したいところを町を歩いてみんなで地図上に掲げ、みなでより善いマチを作っていく。参加して創る。きっと緑も増える、魅力も増す。
市で行ってきた「音楽のあるマチづくり」「農のあるマチづくり」「まちなかみどり保全制度」そして、所沢グランドデザインからTDW(所沢 デザイン ウォーク)への試みがそれであろう。
・『アメリカ大都市の死と生』を著したジェイン・ジェイコブズにも話が及ぶ。
ジェイコブズ(彼女)は
当時主流の「輝く都市」コルビュジエと「田園都市」ハワードの2つの思想を批判する。都市には都市の魅力がある、それは「多様性」である。魅力ある街にはどうも4つの原則があって、1,混在、2、小さな街区、3.密集、4、古い建物 だという。たとえば道は「効果的にT字路を設けよ」とも彼女は主張した。街を分断する広い街路には、彼女は猛反対した。
それはクルマのための街・道づくりであり、マチを分断し人を分断するからだ。
また、著者(吉永先生)は、古い建物が善いのは、ノスタルジーだけでなく、若い人が住めるから、と説く。
賃料が安ければ若い人が店を出せ、変化が起き、魅力が増すからだ。
市が進めてきた「人を中心にしたマチづくり」の心もそこにある。
職住混在もあえて作るべきで、そうしないと今の世の中、昼間は老人だけになる。幼児は保育園、子どもは学校という施設に収容され、大人は東京で働いている。市の市道認定も「通り抜け」が大前提だが、これも再考の時期。それはクルマのための発想だ。
プロぺより一本はずれの通り、また、最近の西所界隈の隆盛は、古い建物=若い人々の進出による。
人は狭い小路があれば吸い寄せられる。クルマが来なければ道を花畑にしても機能は保てる。人が出逢い、憩う場ができる。エミテラスで大渋滞を恐れたが、実際は、人々がクルマで来るのを控えたので渋滞しないで済んだ。
32m都市計画道路も時代遅れ。今後はこれが街づくりを捻じ曲げる原因になる。不作為の罪にならねばよいが・・・。
自然から街づくりまで、すべてが環境であり、生態系を成し、多様性は維持すべきであり、その生態系は今だけでなく遠い未来まで続いている、という考え方を教えてくれる本でした。
参考となる映画 ・「100000年後の安全」 ・「ジェイン・ジェイコブズ ニューヨーク都市計画革命」
例にとられた町 鞆の浦(確かに風光明媚で道が狭く=人しか通れない幅=曲がりくねっていたことを思い出す)
福祉医療保健常任委員会視察開始 - ガッツ藤本(藤本正人)のきょうのつぶやき
(もっと詳しい視察報告などは市議、県議時代のホームページに掲載していましたが、
維持費がきついので昨年廃止してしまい、今は見られません。悔しい)
真鶴町「真鶴町まちづくり条例(美の条例)」美は変わらない、真鶴の良さを変えない
『生物多様性』本川達雄著
たとえば、自分の名前はもちろんのこと、生きてきた証や歴史も無視され、衣服もはがれ、人間の尊厳をはく奪された人間は、
崩壊してしまうという。アウシュビッツの人々の例は『夜と霧』に描かれている。
そう考えると「私」とは、単なる個体として確立しているものではなく、それを成り立たしめる多くの存在、関係性、つながりによって成り立っているものなのではないか。それはすなわち取り巻くもの=SURRAUNDINGS(環境)ともいえる。生物多様性とは「私」を成り立たしめるもの。私の一部である。
父と母の遺伝子を組み合わせて子ができるが、そもそも父と母の遺伝子も遺伝子の塩基配列はほとんど同じ。チンパンジーと人間だって遺伝子で15%、塩基配列レベルでは1%の違いしかない。子も「私」孫も「私」、親も「私」だし祖父母も「私」なのだ。生物は「私」を渡していくものなのだ。
私は、時間的にも空間的にも周りと切れてはおらず、次世代や環境という時間空間的周りを取り込んだ「私」観を持とう。
子どもや「孫」も「私」だとは誰もが感じるが、実は、「友」も私だし、家も私、ペットも私、近所も私、街も私・・・と空間の広がりも持つものだ。そう考えたとき、生物多様性は時間的にも空間的にも私を成り立たしめるすべてのものであり、必要なものなのだ。


























