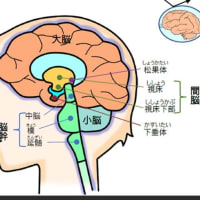『脳みそ』の話が出始めて、無論これは僕がそれなりの脳梗塞の兆候で入院したからなのだが、といっても病状は、多少、右手と右足にツッパリ感があるものの全く変わらず動いている。という訳で、脳の本を引っ張り出したついでに関連する本も引き出して、この当時は、養老猛司先生の『唯脳論』という本も結構売れて脳みそのブームになった感があった時期だった。
『脳みそ』の話が出始めて、無論これは僕がそれなりの脳梗塞の兆候で入院したからなのだが、といっても病状は、多少、右手と右足にツッパリ感があるものの全く変わらず動いている。という訳で、脳の本を引っ張り出したついでに関連する本も引き出して、この当時は、養老猛司先生の『唯脳論』という本も結構売れて脳みそのブームになった感があった時期だった。
前回に続いて引っ張り出して再読した立花隆の掲題写真の本は、『東大講義 人間の現在① 脳を鍛える』 これは、彼は勉強のために2回も東大に入ったので(確か)、卒業した彼は学生に講師として呼ばれて行った連続講義である。いや~、若かりし頃を思い出して面白いなぁ。これは2000年4月30日第3刷である。(以下p○○と書いているのは、この本に書かれていること、そうでないのは僕の意見)
知の巨人と言われた彼の住処は、猫屋敷と呼ばれた地下から3階までの本だらけに埋まった三角エリアに建てられたところだった(確か)。読むと博覧強記、知識満載で面白い。
いろいろ刺激を受けた歴史上の知識人も当初分からなかった内容も、歳をとればそれ相応に生身に体験して考え、悩んで読んだものも、改めて著者の時代は、彼らはこう考えた、思想の走りとなった、それを土台に今、我々は生きている、などと総監すれば、人として生きることの魂の流れの通奏低音のような響きを今もありありと感ずるのであった。
***********
p24「僕らの学生時代は、実存主義全盛時代で、実存主義といってもいろいろありますが、いろんな実存主義についてそのかけらくらいはかじっておかないと、友達と話が出来ませんでした。それで、みんな、サルトル、カミュ、ハイデッカー、ヤスパース、キエルケゴール、なんかをかじってみて、わかってもわからなくても、知ってるふりの議論を盛んにしたものです。」
***********
僕は、ブログで過去にカミュの「異邦人」、「ペスト」のことを書いた。サルトルも少し。論争があったけど、サルトルは、無神論の実存主義を唱えていたからカミュですね、僕は。それに実存主義では、その開祖と言われるやはりキリスト者のキエルケゴールです。(ここでキリスト者と書くことに制限がある。ひとつのイメージができあがってしまうからねぇ。キリスト者でない限り、人は言葉にするとこの流布されている先イメージの束縛から逃れることができないと僕には思われる。したがって、立花隆彼自身は、宗教に嵌っていると絶体の真理と思い込むが、絶対不可侵の神聖な起源なんてものは何もないのだときっぱり言い切っている。)
************
p26「『はじめて体験』を前にしたきみたち
実存主義の主体性論の立場からするとき、世界と自分との関係の上に捉え直すということは、是非とも必要なことですが、それだけでは皮相な主体性論に終わります。もう一段考えを深めるためにさらに大切なのは、今世界を見ている自分自身をどうとらえるかというもう一つ深いレベルの主体性論です。(キエルケゴール『死にいたる病』斎藤信治訳[岩波文庫])」
************
キエルケゴールはキリスト者であった。当時のキリスト教界(会)と闘ったのだった。今も多くの神学を学ぶキリスト者は、実存主義開祖の彼を知らない人は一人もいないだろうと思う。それは、先の言葉、「もう一段考えを深めるためにさらに大切なのは、今世界を見ている自分自身をどうとらえるかというもう一つ深いレベルの主体性論です。」の中に、人の「罪」といものを考えざるを得ない事柄が示されるからである。正統なキリスト者は(と僕は思っているが)実存主義は避けて通れない。
立花隆は、ジャーナリストでもあるし、一転、宗教を認めることにおいて既にその中に、真の追及する精神を気付かづ阻害するものが、多くあることを感知しているので、一般的な宗教を否定する。これは僕にはよく分かる。偏った考えをしてしまうものだからと思われる。・・・世の終わりになるとキリスト者は迫害を受けるという。それは、デリケートな問題ではあるけれど、実はこの辺のところで大きな誤解を受けるからであると僕には思われる。・・・そこはどこにあるのかは、人という生き物にとっていつの時代も付きまとう課題であるようだ。
ところが、宗教を信ずるも否定するも、西欧の思考の底辺には抜きがたくキリスト教思想が流れて形成されているのは疑いない。
******************
p29「宗教に溺れた人が言うように、いかなるものにも、絶対不可侵の神聖な起源なんて何もないんです。要するに宗教とか思想というものは、ある時代の誰かが頭の中でこしらえて、頭の中からひねり出した一連の命題です。・・・」(これから彼が脳についての話を少しし、僕が入院時に持っていった『精神身体医学』に関係する話をしだす。)・・・p30「認知科学や精神医学を学んでみると、人間の頭がどれほど狂いやすくできているかが分かります。どれほど真実でないものを真実と思い込みやすくできているかが分かります。僕は認知科学や精神医学の初歩は義務教育の中である程度教えるべきだと思っています。・・・
いろんな思想を味わってみるという経験をある程度積まないと、新しい思想に出会ったときに、それを正しく評価できません。経験なしには、思想を評価する座標軸ができないからです。思想の世界の幅と奥行きが分からないと、正しい定位づけが出来ないんです。」
(僕:これは大いに賛成です。)
*****立花隆の『死に至る病』の説明に第一編の冒頭を書く。『死に至る病』とは『絶望』のことなのである、と。
p26「この本の最初のページを開くと、いきなりこうあります。『人間とは精神である。精神とはなんであるか? 精神とは自己である。自己とは何であるか? 自己とは自己自身に関係するところの関係である」・・・
*****************
ここからくだくだと細かに当時のキエルケゴールは事を思索しはじめるのだが、この仕事上のジャーナリストの言葉を無視して、何をこの著作(『死に至る病』)が語ろうとしているかと言えば、答えはキエルケゴールがその『答え』を冒頭の『序』と『緒論』の中に既に書いているのである。
『死に至る病』から******
p12,13「序ーキリスト教的な英雄的精神(おそらくこれはごく稀にしか見出されないものであるが)とは、人間が全く彼自身であろうとあえてすること、ひとりの個体的人間、この特定の個体的な人間であろうとあえてすることである。-かかる巨大な努力をひとりでなし、またかかる巨大な責任を一人で担いながら、神の前にただひとりで立つことである。・・・『死』もまたキリスト教の用語では精神的な悲惨の絶頂を示す言葉なのであるが、しかも救済はまさに死ぬことにおいて、往生において、成立するのである。1848年。」
(※キリスト者は次の緒論の数行を読んだだけで、『死に至る病』が何を語ろうとしたのかすぐに理解されるはずである。ここで『陰府(よみ)』のことが思い出されるだろう。)
p15「緒論(冒頭)ー『この病は死に至らず」(ヨハネ伝11・4)。それにもかかわらずラザロは死んだ。キリストの弟子たちが、「われらの友ラザロ眠れり、されど我よび起こさんために行くなり」というキリストのその後の言葉の真意を理解しなかった時に、キリストは弟子たちに直截にこう語った。ー 「ラザロ死にたり」(11・14)かくて、ラザロは死んだ、にもかかわらずこの病は死に至らなかったのである。ラザロは死んでしまった。にもかかわらずこの病は死に至っていない。・・・」