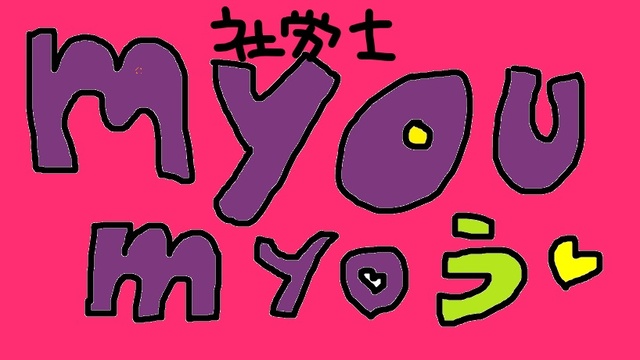浜口桂一郎さんがhamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)で
「あまりのレベルの低さに涙が出てきました」
と嘆いています。
労働法制をわかっていない政府やマスコミが言うならまだしも、
法律家の代表であるはずの日弁連がこのレベルですか…と
そうとうがっかりされていました。
安倍さんは年収1000万以上の労働者を対象に、労働時間とは関係なく、成果に応じて賃金を支払う制度を導入しようとしています。(前にもチャレンジして頓挫してます)
日弁連はこれに対し
・これは労働時間と賃金とを切り離し、実際に働いた時間と関係なく成果に応じた賃金のみを支払えばよいとする制度である
・このような制度が立法化されれば、適用対象者においては長時間労働を抑制する法律上の歯止めがなくなる
と、反対派を代表するような声明を発表しました。
これがなぜ浜口さんを嘆かせるのでしょうか?
浜口さんがいたるところで、くどいほど言い続けているのが次のことです。
・”労働時間と賃金を切り離し、実際に働いた時間と関係なく成果に応じた賃金のみ支払えばよいとする制度”は、”法定労働時間内”においては、そもそもなんら禁止されていない。
・法定労働時間を超えて働かせることは違反であり、懲役刑すら規定されている。それでもあえて働かせなければならないような例外的な状況であれば、手続きを踏んだうえで、割増賃金を支払わなければならない。「割増した」賃金でなければならないのは、本来はダメな労働をあえてやらせることに対する罰金だからである。決して、「時間に比例した賃金を支払え」と命じているのではない。
・労働法の基本をわきまえていればすぐにわかることが、まったく理解されていないのは、そもそも法律上は法定労働時間を超えた労働に対し、懲役刑まで用意して禁止しているということが、現実の労働社会では空想科学小説以上の幻想か妄想と思われていることである。そこにこの問題のコアがある。
私は時間外労働というといつも思い出す裁判があります。
6年ほど前、某ファーストフードチェーン店の店長が、未払い残業代の支払いを求めて訴訟を起こしました。「名ばかり管理職」という言葉が流行語になりました。
時間外賃金を出したくないばかりに、「役職」につかせて、無制限に働かせるという手法がいたるところで横行していたので、この裁判で「監督・管理の地位にあるもの」がはっきりと定義されたのは成果だと思います。(つまり、そもそも時間など関係ない労働者がいるわけです)
一方で「お金を払えばそれでいい」という認識が広まってしまったのは残念なことです。訴訟を起こした店長は、賃金もさることながら、労働時間が相当長く、このままでは命が危ないと思っていたのです。勤務と勤務の間にも規制はなく、会社規程のみです。深夜業務の後、数時間の仮眠でまた現場に戻らなければならいことが多かったことと思います。お金の問題だけではないのです。
それともうひとつ、名ばかり管理職が有名になったおかげで、あたかも、管理職じゃない人は残業代が支払われているかのような既成事実ができてしまいました。管理職じゃない人はもちろんのこと、パートやアルバイト、派遣社員までがただ働きしているのが日本の現状です。