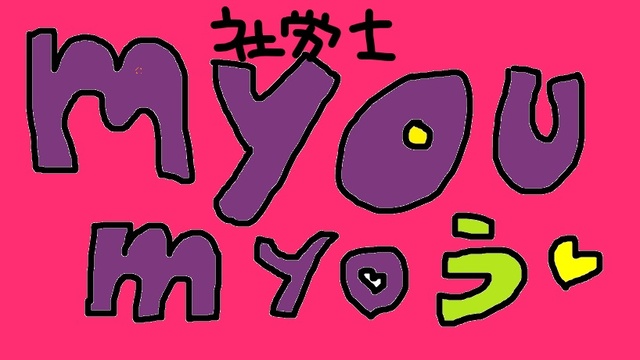月刊社労士6月号で香川県の社労士・林哲也さんが
「介護事業所における労務管理と社労士としての支援策」
というテーマで2015年度の介護保険制度改正について書いています。
著書に「実例で見る介護事業所の経営と労務管理」(日本法令)などがある、介護・医療周辺に詳しい方です。
在宅サービスでの主な改正点として
⑴ 要支援者の訪問介護・通所介護サービスを介護保険給付から外し、地域支援事業に移行
⑵ 総合事業の生活支援・介護予防サービス事業のみ利用する場合、「基本チェックリスト」に回答し、該当すれば介護認定を受けなくても利用できる制度の導入
⑶ 小規模デイは、市町村の許認可制となる予定
⑷ デイサービスは、サービス内容によって、類型化さて、これに応じた報酬額となる
⑸ 一定以上の所得のある人は、2割の自己負担
⑹ 介護職員の処遇改善加算制度は、2015年4月までに、「財源の確保も含め検討を加え、必要のあると認めるときは必要な措置を講ずる」との内容で、処遇改善法案が成立予定。とりあえずなくなるってことか…
の6点をふまえ、事業所に与える影響として、
量的には、利用抑制の強化による収益構造の変化、
質的には、中重度者対応に力点が置かれるため、
介護職員の専門性と人間性の高さが求められるとして
職員の質の強化をあげています。
基本的な労務管理の解決策として3つの問題点があげられています。
1 採用方針の問題
「とにかく有資格者」とばかりに、人柄を見ないで採用
面接で人柄がわかるのか…とも思うが、林さんが言っているのは
「採用するべきではない」と知りつつ、採用してしまい、後に職員間のトラブルを頻発させ、大量退職となるケースだとか…
2 管理者の資質の問題
「とりあえず管理者」問題。力量を見極めず、「有資格だから」の理由で登用し、人間関係の不調の原因になっているとか…
とりあえず起業した人などは、どうすればいいのだろうか?
なんか林さんは難しいことを言っているな…
3 処遇改善加算の終了・減額への対応
最後に社労士としての支援策をあげています
⑴ 介護職員の処遇とキャリア確立を支援
⑵ 元気な高齢者の介護事業への就労を支援
(元気な高齢者が元気をなくすような目に合わないように監視する必要もあるぞ)
⑶ ボランティア活用の知識と技術を支援
ときて、最後が
介護は感謝、感激、感動の仕事と理解し、介護への誇りと憧れを広げる支援も大切と締めくくっておられました。
残念!(いつの流行りや!!)
最後の最後、これですかい。
「キツイ」「キタナイ」「クルシイ」は本質ではないそうです。確かに。
仕事がキツイかって言ったら、キツクないでしょ。私は特養勤務経験ありますが、「仕事はキツクないんです」キツイのは他のもろもろです。特養時代の同僚がグループホームに職場を変え、「信じらんないくらいラク」と言ってました。ラクな特養よりもっとラクらしいです。キタナイが排泄物とかだったら、排泄物を排出しない人いないでしょうし、人様のこと言うのは…でもキタナイのは排泄物ではないのです。クルシイならいろんな意味で本当に苦しい。私は、小さいころから祖父母に、現世での行いによって、死んだら地獄に堕ちると聞いていたので、特養での体験は今でも恐ろしい。天罰が下るかもしれないという恐怖の苦しみがある。
以前、介護労働安定センター主催のセミナーに参加したのだが、そこでもある社労士が林さんのようなことを言っていた。そういうことを言わないとダメな業界なんだとつくづく思った。
ちなみに、社会学者の古市憲寿が『だから日本はヅレている』のなかで、このままでは2040年の日本はこうなる、と予測している。絶望の国という言葉が真実味を帯びるようになり、階級社会は固定化され、ゆえに「まあ、こんなもんだろう」と、幸福度が逆に上がった社会。アジア諸国の経済水準が上昇し、日本へ移住するメリットもなく、AEAN諸国は極東の没落国に興味をなくしてしまう。なので、低賃金労働を移民に任せるという選択は取れず、貧困層の日本人が移民担当職に従事することになるのだが、それがファーストフード店員や介護職である。
外国人が賃金低下をもたらすとか、人手不足だからって安易に外国人に頼るなとか、移民の就労にはみんな正論で抗議していますが、古市バージョンが笑い話であってほしいと心の底から願う。