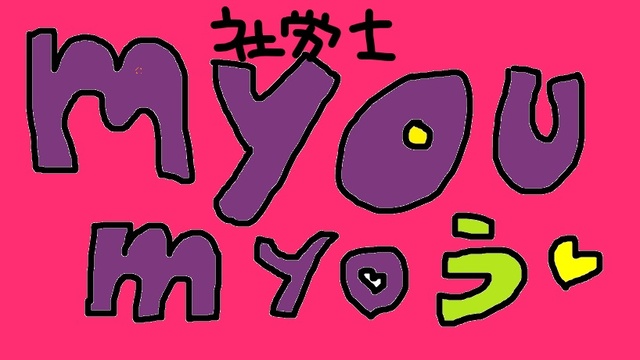京都大学大学院教授の諸富徹(もろとみ・とおる)さんによるEUの「金融取引税」についての話を紹介します。
「金融取引税」とは聞きなれない言葉ですが、通貨・株式・債権・デリバティブなど、ありとあらゆる金融資産の取引への課税のことで、デメリットが大きいため金融業界や経済界からの反対が強く、導入は難しいとされていたそうです。
しかし、2009年のリーマンショックに伴う金融危機で、苦境に陥った金融機関救済のためEUは、加盟国全体のGDPの39%に相当する金額を投入せざるを得なかったのです。そのため、費用の一定額を金融機関に負担させ、課税上の公平性を回復させようと、フランスやドイツなど11か国が昨年2月に、金融取引税を共同導入することを決定しました。導入目的のひとつです。
もうひとつの目的は、投機的な取引の抑制です。現在投機的な取引は想像を超えるスピードで増加しており、アメリカでは金融市場の売買の7割、ヨーロッパや日本では3割を高頻度取引が占めているそうです。高頻度で売買を行えば行うほど税負担が重くなり、その結果として、投機目的の売買が抑制されるということです。また、高頻度取引を用いる金融機関の顧客は、所得や資産の多い人なので、税負担の累進化の効果もあるといいます。
金融機関やEU以外の地域では、金融取引税についての関心は低く、導入にも積極的とはいえないようです。
経済システムの究極の目的は単なる効率性の向上ではなく、人々の福祉水準を高めること、つまり人々を幸せにすることにある。ならば、この金融取引税も検討に値するのではないだろうか。
金融「取引税」のついでに消費税について少しばかり。消費税が「公平なもの」「社会福祉の向上には不可欠なもの」として、北欧を手本に導入されていますが、(アメリカには消費税がありませんが、なぜか手本にしていませんね)この機会にちょっと考えてみたいです。
消費税はその名称から、商品やサービスにかかるもので、その商品やサービスを消費する消費者が公平に負担するもの、というかんじがします。消費者としてしょうがないことか、とやや無関心でいましたが、自分がお客様から消費税をいただく立場になり、はじめて「あれ?消費税って誰が支払うのか?国に納める義務は誰にあるのか?間接税といわれるのはなぜか?」と疑問に思ったのです。消費税を納めなければならないのは売上1千万以上の事業者です。なので私には納税義務はありません。私は消費税をネコババしたことになるのか?納税しないのにお客さんから徴収するのは違法なのか?消費税の納税を促すポスターなどでは、納税しないのはずるく悪辣で、善良な国民をだましているかのように書いているが…法人税や所得税にもこのようなポスターが存在するのか?消費税は身近でありながら謎が多い…
消費者が「1回消費」したからって「1回だけ消費税」を支払うってもんでもなく、問屋から仕入れたり、問屋がメーカーから仕入れたってかかります。消費してなくてもかかってます。なんで消費税なんて名前にしてるんでしょうか?取引ごとにかかるから、取引税なんじゃないか?ということで、金融取引税ついでに消費税でした。公平といわれているけれども、赤ちゃんからお年寄りまで生きている限り(何も消費しないなんてありえないもの)、払わなければならないという点ではおそろしく公平なのが、消費税です。
金融取引税といっしょに、この商品・サービス取引税についても再考すべきですよー