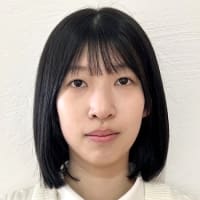.
囲碁経験の浅い人が棋譜並べを実践した、その時にぶつかる壁の1つがコチラ。
「プロの碁は難しい。なので全然覚えられない、全然理解出来ない。
これは自分の努力が足りないせい? それとも自分に才能が無いせいなのか?」
プロの碁が理解出来ない、覚えられない__と言う壁にぶつかる理由は、努力や才能の有無では無い。実はこれこそが、棋譜並べから得られる大事な収穫の1つなのかも知れません。
.
A≫理解出来ない碁は後回しにする__と言う選択肢
2015年末。
「世界中で有名なインターネットの会社Googleが、これまでに無い強い囲碁AIの開発に成功した。
囲碁AIの名称は『Alfer Go(アルファ・碁)』」
と言うニュースがありました。
その翌年、世界最強の囲碁棋士、韓国のプロのイ・セドルがアルファ碁に挑戦。結果は、イ・セドルさんの1勝4敗。後日行われたカ・ケツ(世界大会で優勝した中国の囲碁のプロ)プロも、アルファー碁には為す術無く全敗。囲碁の世界2トップがアルファー碁に敗けたニュースは、「人間の碁の歴史の終わり」と評されました。
それから数年後の2019年。日本の囲碁では、ちょっとした異変が。
「日本のプロが世界で勝つには、強い囲碁AIを使って勉強すべき」
と、若手棋士もベテラン棋士もAI流の打ち方を勉強していた中、AI的な打ち方を採用していなかった羽根直樹プロがタイトル戦で優勝した。それについて羽根直樹プロは、次の様に証言。
◎囲碁雑誌の特集より
「AIの打ち方は、たしかに強く納得は出来ます。
ですが、AIの打ち方は人間のプロの打ち方とは違う点も多く、私には使いこなせる自信がありません」
◎愛知県のローカルメディアの取材より
「(今はAIの研究が主流ですが)昔の先生方の打ち方にも、学べる事はたくさんある。
私は、昔の先生方の打ち方から学んでいきたい」
◎ファンへのアドバイスより
「世界のトッププロやAIの打ち方はおすすめ出来ません。囲碁ファンの皆さんが真似するには難しすぎます」
「ファンの皆さんが勉強されるなら、昭和の碁、特に木谷道場の先生方の碁。
木谷道場の先生方の打ち方は多彩なので、自分の好みに合った打ち方が見付かりやすいと思います」
プロの大会で優勝された羽根直樹プロは、
「どんなに強いAIの打ち方でも、自分には真似出来ない」
と言う事に気付いた。そこで、
「AI以外の方法でも強くなる方法はあるはず」と模索し、その手がかりを見付けた。
そうした事から、棋譜並べをやってみて「これは覚えられない、理解出来ない打ち方だな」と思ったら、その碁の勉強は後回しにして、自分が理解出来るプロの碁を探してみる。それも立派な棋譜並べの勉強法の1つなのだから。
.
B≫見た事ないから分からない__を減らす
碁の経験が少ない人の場合。相手に見た事無い打ち方をされてしまうと、悩み過ぎて次に打つ手が分からなくなってしまう__と言う問題。
【1図】
「中国流と言う布石を勉強したので、
中国流布石を使ってみました」

【2図】
ところが対局相手の人は、白1カカリを打ってきました。
この時、どうしたら良いんだろう?

.
【3図】
考えられる有効手段には、黒2~のツケノビ定石があります。

.
【4図】
あるいは、黒2と別の場所に打つ作戦も有効。4図の場合、
「白1and白3の高目定石作戦に、黒4と打ってみた」と考えてみる事も可能。

【今回の結論】
囲碁の棋譜並べの経験が少ない人や苦手な人が棋譜並べをする場合には、下記4つを意識されるのが良いと思います。
◎難しそうだと思う打ち方をしている棋譜は、後回しにする。
◎この打ち方は知ってる。自分も何度も使った事ある。
━━そんな棋譜を重点的に並べて勉強する。
◎この打ち方は見た事はない。だけど覚え易そう。
━━そんな打ち方を見付けたら、定石書や雑誌解説等を読んで調べてみる。
◎それらを踏まえた上で、
「自分が知っている打ち方or知らないけど覚えやすそうな打ち方を、プロはどんな風に使っているのか?」
に着目する。
.