リチウムバッテリーを組むときに使うバスバー。
バスバーとはバッテリーのセルどうしを接続したりバッテリーからの取出しを普通バスバーと呼んでいる。
アリババやアリエクからLiFePO4を購入するとバスバーが一緒に付いて来る。
バッテリーによってバスバーの大きさは色々だが、今回はバッテリーから取出す場合についての目安について。
これが意外によく聞かれるので、簡単にボクのやり方をご紹介。
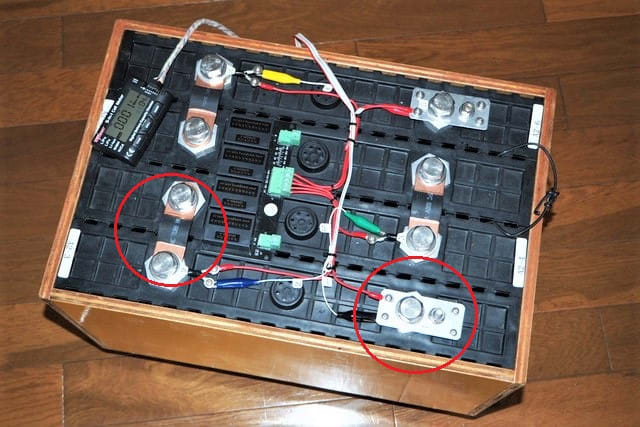
左側は400AhのLiFePO4に一緒について来たもので、右側は280Ahのもの。

400Ah用のものは厚さが3.0mmで幅が30mmとごついやつを14mmのボルトで締上げる。
規格ではMAX400A流せるというものだが断面積は30×3t=90㎟

こちらは280Ahのものは厚さが2.6mmで幅が20mmを6mmのボルトで締める。
バッテリーの規格ではMAX280A流せるというもので断面積は20×2.6t= 52㎟

上記を簡単に検証してみる。
日本のバスバーの規格はJIS-C8480にあるが、それに準じるとバカでかくなって現実的ではない。
あまり難しい事を言わずに、銅線に通せる電流を20㎟ あたりピークで100Aとする。
それで先ほどのバスバーを計算してみると、
400Ah 90㎟/20㎟ × 100A = 450A
280Ah 52㎟/20㎟ × 100A = 260A
大体ほぼ似たような数字になっている。
バッテリーから電流の取出しのバスバーを作る場合、アルミ板のほうが加工しやすい。
でも銅に比べアルミは約1.6倍電気を通しにくいので、仮に200A通せるようにするには
200A / 100A×20㎟ × 1.6倍 = 64㎟
幅30mmのアルミ板であれば 2.2mmの厚さがあればいい。
こんな事ばかり書いているとまたまたブログ読者が減りそうだが、次に聞かれたらネットを見ろと言える。 
快適化やトラブル事例はこちらに沢山あります。
↓ ランキングに参加していますのでどちらか一つクリックして応援、お願いします。 

















