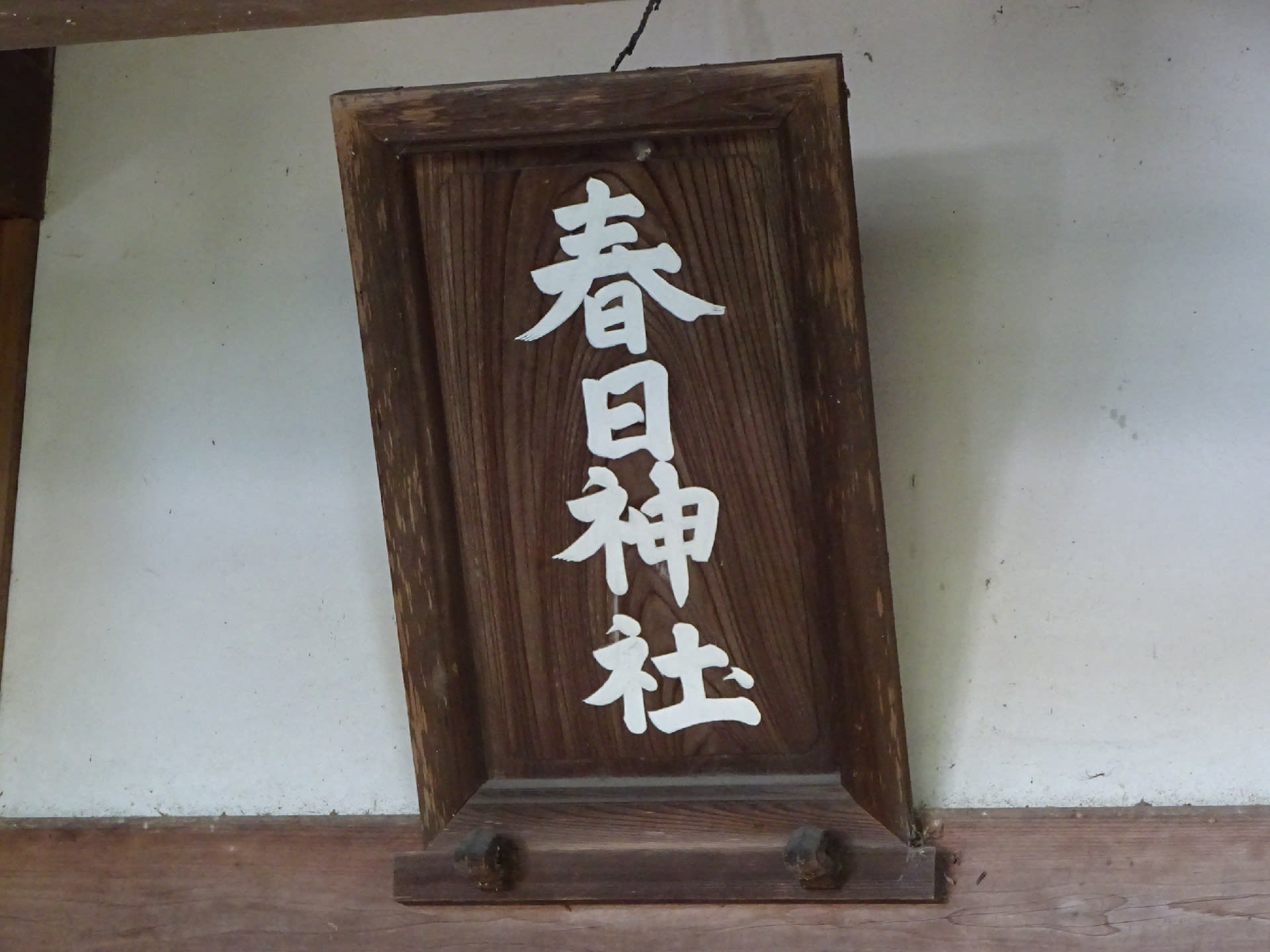よろしくお願いします。












しまなみの旅2日目は生口島からフェリーで岩城島洲江港へとやって来ました、フェリー航行は昼間でも割と本数はあるのですが、ゆめしま巡りのサイクリストや帰省の家族連れ、商店に商品を運搬する車やバイクで甲板は結構埋まっていました。岩城島に下り立つのはこれが3度目、これまでは因島からフェリーで長江港へと下り立ち、そこから島の外周道路を右回りで巡って洲江港まで走りました、今回はそのコースを逆向きに走ります。まずはまっすぐに伸びる上り坂、T字の交差点を右へと曲がり外周道路を左回りで進んで行く。田園風景、集落、海沿いと次々に変わる風景、やがて海沿いの道を外れて住宅地の急な上り坂を越えるとこの島の中心地となる岩城の町並へと差し掛かって来ます。















今治への高速船が到着する港へとたどり着きました、いわばここが岩城島の玄関口となる所でしょう。港の手前にある観光センターはたくさんの人で賑わっているかのよう、車やバスが駐車場にたくさん停まっていたので結構観光目当てでこの島に訪れている人も多いみたい。でもやはり観光のメインになっているのはサイクリングの方、町役場の垂れ幕にもあるように岩城橋が開通して・・・この日が5月3日だからほんの1か月少し前のこと・・・4つの島がひとつにつながった。それに合わせてしまなみ海道のオプションと言った感じでサイクリングコースも整備された、自転車でやって来た人も自分(一人称)もその目論見に見事に乗せられてこの島にやって来たわけか。後は岩城島と生口島、因島と弓削島がつながって1本の道になってくれたらもっと世界が広がるんやけどなあ~、ただ橋がつながるとフェリーがなくなってしまう、それはそれで寂しい話なのですが・・・。













岩城の中心部から町中の狭い道を抜けて行くといよいよ新しい橋へと至る上り坂に差し掛かってくる。これくらいの上りならまあ余裕ですわ、途中で悪戦苦闘している女の子の二人組を追い抜いて、いよいよ岩城橋へと立ち向かうがこれがまたまたゼットン並みの難敵。昨日生口島大橋から見た感じでは簡単に渡れそうやな~、という感じだったが、橋は真ん中が高くなっていてそこまでの上りが結構きつそう、道幅が狭く後ろから車で煽られたら怖いな~、と思いながら一番最高部へとたどり着く。ここからの眺めはもちろん最高、ただその高さにはちょっと足がすくんでしまう、写真を3枚ほど撮って一気の下りへと向かう。橋を渡り終えると生名島、難敵は終わったかと思ったらまたまたきつい上り坂が待ち構えている、これは骨が折れるわ~、と思っているとさっき上り坂で追い抜いた女の子の二人組がやって来た、彼女たちもなかなかの猛者みたいだ。その辺りの下りについては次回、ゆめしま後編でお送りするとしましょうか、今回もご覧いただきましてありがとうございました。・・・・・・・・・・まちみち












しまなみの旅2日目は生口島からフェリーで岩城島洲江港へとやって来ました、フェリー航行は昼間でも割と本数はあるのですが、ゆめしま巡りのサイクリストや帰省の家族連れ、商店に商品を運搬する車やバイクで甲板は結構埋まっていました。岩城島に下り立つのはこれが3度目、これまでは因島からフェリーで長江港へと下り立ち、そこから島の外周道路を右回りで巡って洲江港まで走りました、今回はそのコースを逆向きに走ります。まずはまっすぐに伸びる上り坂、T字の交差点を右へと曲がり外周道路を左回りで進んで行く。田園風景、集落、海沿いと次々に変わる風景、やがて海沿いの道を外れて住宅地の急な上り坂を越えるとこの島の中心地となる岩城の町並へと差し掛かって来ます。















今治への高速船が到着する港へとたどり着きました、いわばここが岩城島の玄関口となる所でしょう。港の手前にある観光センターはたくさんの人で賑わっているかのよう、車やバスが駐車場にたくさん停まっていたので結構観光目当てでこの島に訪れている人も多いみたい。でもやはり観光のメインになっているのはサイクリングの方、町役場の垂れ幕にもあるように岩城橋が開通して・・・この日が5月3日だからほんの1か月少し前のこと・・・4つの島がひとつにつながった。それに合わせてしまなみ海道のオプションと言った感じでサイクリングコースも整備された、自転車でやって来た人も自分(一人称)もその目論見に見事に乗せられてこの島にやって来たわけか。後は岩城島と生口島、因島と弓削島がつながって1本の道になってくれたらもっと世界が広がるんやけどなあ~、ただ橋がつながるとフェリーがなくなってしまう、それはそれで寂しい話なのですが・・・。













岩城の中心部から町中の狭い道を抜けて行くといよいよ新しい橋へと至る上り坂に差し掛かってくる。これくらいの上りならまあ余裕ですわ、途中で悪戦苦闘している女の子の二人組を追い抜いて、いよいよ岩城橋へと立ち向かうがこれがまたまたゼットン並みの難敵。昨日生口島大橋から見た感じでは簡単に渡れそうやな~、という感じだったが、橋は真ん中が高くなっていてそこまでの上りが結構きつそう、道幅が狭く後ろから車で煽られたら怖いな~、と思いながら一番最高部へとたどり着く。ここからの眺めはもちろん最高、ただその高さにはちょっと足がすくんでしまう、写真を3枚ほど撮って一気の下りへと向かう。橋を渡り終えると生名島、難敵は終わったかと思ったらまたまたきつい上り坂が待ち構えている、これは骨が折れるわ~、と思っているとさっき上り坂で追い抜いた女の子の二人組がやって来た、彼女たちもなかなかの猛者みたいだ。その辺りの下りについては次回、ゆめしま後編でお送りするとしましょうか、今回もご覧いただきましてありがとうございました。・・・・・・・・・・まちみち