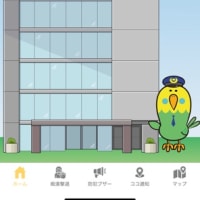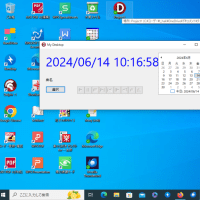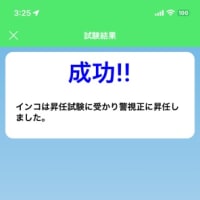さて、私が前にも書いたとおり、
生産者、運搬者、消費者。
そして受注業者と決済業者。
こんなビジネスモデルができあがった。
このビジネスモデルにおいて、加入する余地があるのは、保険会社と裁定機関であろう。
なぜならこの五者のいずれかがエラーを起こしても、損害賠償の交渉と支払いの任に当たる保険機関、そしてその調停作業に当たる裁定機関が必要だからだ。
某食品運搬請負会社は、運搬員は個人事業主だとうそぶき、エラー発生時のリカバリーについて知らぬの半兵衛を決め込んでいるが、少なくともこの国では通らない。
そんな会社がこの国でやっていけるほど、まだ、我が国民の法意識は熟成していないのだ。
日本も欧米諸国のように、訴訟国家になることが予想される。
そんなときに損害賠償の交渉と支払いの任に当たる機関が必要であり、さらにそれを公的に裁定する機関が必要であることが予想される。
まあ、運搬手段を自動運転自動車や自動運転ドローンに運ばせれば、最近メディアやネットを賑わせる運搬員の問題も減少することであろう。
ただそれが、社会不安を抑える政策上、有効かどうかは甚だ疑問があるが。
自転車保険もできたことだし、また、資本家一味をもうけさせるために、某巨大食品運搬請負会社の運搬員は、自転車保険に入らないと雇わないように持っていくであろう。
こんなふざけた会社が、自前で自転車保険の銭を持つとは思えないからだ。
それに、団体割引をかけるより、個々の運搬員に保険に入らせたほうが、金も実績も儲かって、立案公務員も、保険会社も、運搬請負業者もウマ~だからだ。
実に悪辣極まりないことだ。
さて、若者に仕事を与えない社会ほど、無慈悲な社会はないとは、社会政策の任に当たった行政官が痛感することの一つであるからである。
だったら、政策立案公務員、保険会社勤務員、運搬業者事務員、そして運搬員に仕事を与えたほうが、無駄は増えるが失業者の数は減る。
こんなことを考えるいけもとてつこう自体が、悪辣な人間なのかもしれないが(笑い)。
寝ぼけた頭で、そんなことを考えたИКМТであった。