
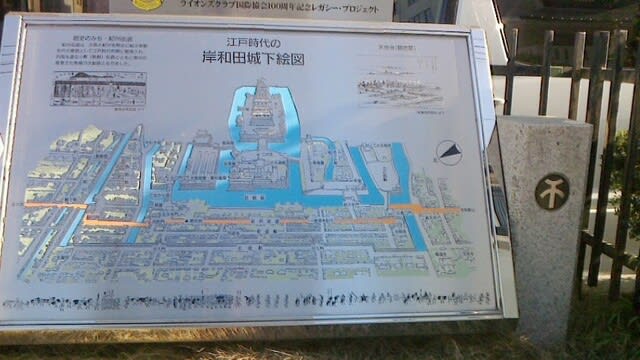









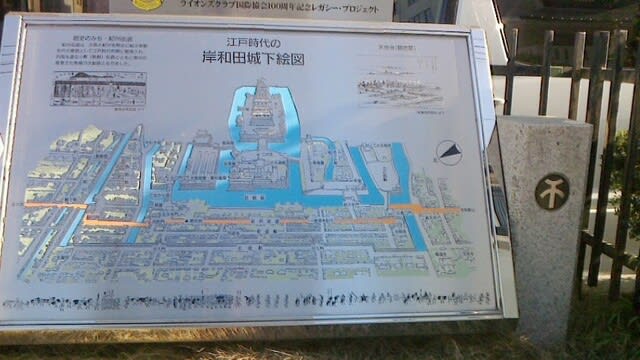






































★関西ネタです
【2018年12月某日】
社宅で過ごす週末、しかも雨も降っていないとなると、もう体がウズウズしてくるのさ。
昨日、紀州街道(1)を終えたばかりなのにね。
でもそのまま紀州街道の続きという気にもなれないからね。
まるで昨日のテープレコーダーのごとく、朝から朝食と洗濯をさっさと済ませれば、やっぱりもう一つの走破中の街道、高野街道に足が向かってしまうのさ。
最寄りの北浜駅から大阪メトロ堺筋線、天下茶屋駅で南海電鉄高野線の急行に乗換。
やってきました、林間田園都市駅。(冒頭写真)
時計はすでに11時をわずかに過ぎている。
名前から想像される通り、駅の西側には大規模団地が広がるものの、周辺は売店すら見当たらない。
東口に出て、早々にトレーニングを再開する。
駅前のヘアピンカーブを下り、国371に出て、道なりにしばらく走れば、前回のコースアウト地点だ。

斜めの道を下りてきたところだったよね。
資料によれば、ここからそのまま国道を走るようだ。
500m弱走れば、道路の右側にすり減ってしまった感がある「高野街道五里道標石」。
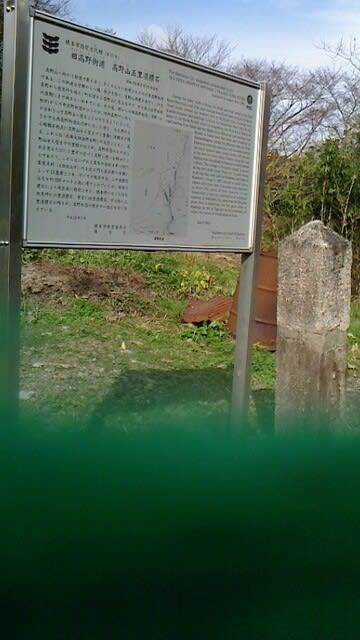
そうそう、高野街道お馴染みの道標石で、東海道や中山道の一里塚に該当するわけで、これがあると安心だね。
さらに国道を進む。
300mぐらいかな?
右へ分岐する道がある。
緩やかなカーブには旧街道らしい匂いがいっぱい(笑)

ということで、迷うことなくこの道ね。
いかにも旧街道らしいカーブが続くが、しばらくはシャメスポットもなさそうで、しかも緩やかな下りということで足は快調に進む。
左手にひっそりと橋谷地蔵尊なんてものがあって、ここが街道であることをこっそり教えてくれているようだ。
しばらくして左右に分岐。
ここは左の方が正解らしい。
もっともどっちを行っても150mほどで一緒になるんだけどね。
御幸辻なんて地名がいかにも旧街道らしい。
辻は十字路のことであり、その名前の交差点が、左手やや離れたところを走る国道にある。
右手離れたところには、その名の南海電鉄の駅もある。
「御幸辻南」の信号で、旧高野街道は国道371に合流。
国道を横断した先の、私道のような道が旧街道らしい。
でもすぐに右へ折れ、また国道に引き戻される。
200mほど走れば左手にひっそりと常夜灯。

そしてここで国道の反対側、左折する道があって、どうやらここを行くのが正解のようだ。
しばらくは古いお屋敷の間を縫うように走る。
再び国道に吸収され、そのまま走り続ける。
右側には橋本川が寄り添う。
しばらくして右手に「下小原田」というバス停がある。
資料ではこのまま国道を案内しているが、恐らくこのバス停から出ている小道が正解だろうな。
で、小道を少し先で左へ分岐していたものと思われるが、現代は消失しているんだろうと推測される。
というわけで、国道をそのまま走るが、この辺りは歩道もないから別の意味でちょっとした難所ではある。
50mほどで左へカーブするのが旧街道ね。
そのままさっきから視界に入っている高架(京奈和)自動車道)を潜り、そのまま道なりに。
しばらくはこのゆるやかな曲線道路に従って走るのみ。
こういう道は飽きないからなぁ、快調に足は進む。
少しづつ高度を下げ、家並みも増えてきた。
橋本市街地に入ってきたらしい。
久しぶりに信号を見たな。
その先、左斜めに分岐する狭路が高野街道であることは容易に想像できるが、そこに古い道標が建つ。

どうやらさっきの信号のところが追分になっていて(東屋四辻というらしい)、交わる道はこの辺りでは伊勢街道と呼ばれているようだ。
当時の慣例で、街道の名前は、ゴール地点を指す。
伊勢に向かう道はみな伊勢街道だから、同じ名前の街道が複数あっても不思議ではない。
今のように全国規模でその日のうちに移動できたり、情報が瞬時に入る時代ではなかったから、それでも問題がなかったんだろうね。

目の前は紀ノ川のため、現代では道が大きく右に折れ、川沿いに進んでいる。


