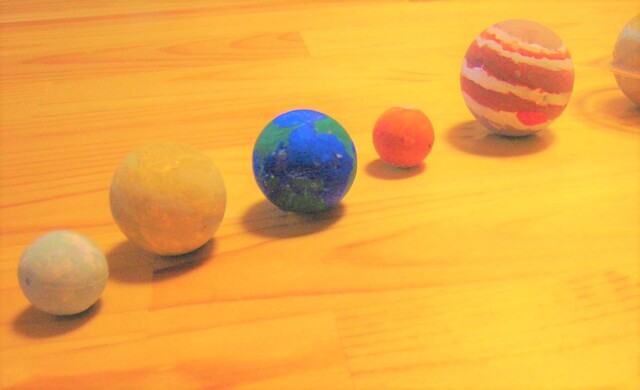報告が遅くなりましたが、
1月の日本モンテッソーリ協会中部支部の定例研究会に、深津高子先生が来てくださいました。
深津先生のことは、ご存じの方が多いと思いますが、
一般社会法人「国際モンテッソーリ協会(AMI)友の会 NIPPON」副代表
AMI教師養成コースで、ジュディ・オライオン先生の通訳をされていらっしゃいます。
月刊クーヨン増刊 モンテッソーリの子育て 2010年 03月号 [雑誌]
では、敏感期の特集をされていらっしゃいます。
0~6歳の「伸びる! 」環境づくり おうちでできるモンテッソーリの子育て (クーヨンの本)も敏感期や発達の4段階、大人のふるまい方を執筆されています。
↓こちらも監修されています。
デチタ でチた できた!
さて。
テーマは、「家庭でできるモンテッソーリ」でした。
最近は、ご家庭で、「教具は、どれを買ったらいいですか?」という質問が多いそうで、
家庭でできることは、教具ではなく、もっとあるということをお話されました。
※教具とは、感覚教育以降で使用する感覚教具、算数教具などのことであり、
日常生活の練習で使用するものは、用具と言います。
お母さんは、教師ではなく、「おかあさん」であること。
家庭でのインテリアの工夫。
身辺自立、精神的自立ができた上で、知的自立が成り立つということ。
自由と制限。選択肢の与え方。褒めるのではなく認める。
ここでは、詳しくは書けませんが、
とても分かりやすく、家庭で大事なことは何かをお話していただきました。
アイアイからは、2人のお母様がご参加してくださいましたが、
ご参加できなかった方には、私からの報告をさせていただいています。
また、気になる話も。
今はテレビで学んでしまう子が多く、五感による原体験がなく、イメージから入ってしまう
ということでした。
最近の私の経験です。
見知らぬお母さんたちが、盛り上がっているのが聞こえてきました。
「○○先生(TVによく出ている有名な先生)が、言ってたけど、
iPadがいいらしいよー。うちの子にもやらせようかなぁ!」と。
(良さげな理由をたくさん言ってましたが、忘れました )
)
何歳のお子さんの話かは分かりませんが、今やテレビだけではないですね。
私たち大人は、小さな子どもたちが五感を感じられるように、
また、子どもが自分で考えられるような環境を意識していないといけないのでは…
と思います。
また、他の園の先生がおっしゃっていましたが、
子どもが砂場に入るのを靴が汚れるからダメだと言ったりする親御さんもいらっしゃるそうです。
靴が汚れて困るなら、はだしで入って、あとで洗えばいいのよと。
確かに、息子の園でも、砂場にはだしで入って、
教室に入る前は、洗面器に水を張って洗っていました。
(公園ですと、危険物やフンがあったり、抵抗がある場合もあるかもしれません。
わが家では、庭でも遊べるように大きな容器に砂を入れてました。)
例えば、ザラザラだと思う感覚は、触覚板(感覚教具)で培われるのではなく、
日常生活の中で培われるのだと。
こういったものは、テレビ画面では、絶対に感じ取れないものですよね。
日常生活で何をどれだけ経験したかということが本当に大事ですね。
また、お知らせもありました。
深津先生は、ピースボート子どもの家のアドバイザーでもいらっしゃいます。
子どもと一緒に世界一周できたら、素敵ですよねー。
参加者はもちろん、保育士さんやボランティアも募集中だそうですよ。
先週は、「3~6歳ブラッシュアップセミナー」算数教育もありました。
モンテッソーリ瑞穂子どもの家facebookで案内がご覧いただけます。
2014年2月1日(土)午後は、公開講座「モンテッソーリ教育の実践研究と発展・言語教育」です。
公開講座では、今夏の世界大会の報告や小学校の言語教育もあるとのことですので、
興味ある方は、お申込みください。
 ぜひ、こちらもお読みください。
ぜひ、こちらもお読みください。
モンテッソーリ教育を初めて知る方へ
マリア・モンテッソーリ
モンテッソーリに関する書籍