<(注1)、(注2)欧州拠点候補政経分離方式セルビア工場人件費は中国工場の人件費の70% 固定費削減狙いか>
<EVモータは労働集約組み立て産業か>
<政経分離方式中国工場の人件費4倍の日本国内工場回帰自動無人化技術集約生産性4倍~6倍のEVモータ工場は不可能か>
2020/11/07 11:15
----------
真壁 昭夫(まかべ・あきお)
法政大学大学院 教授
1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授などを経て、2017年4月から現職。
----------
真壁 昭夫(まかべ・あきお)
法政大学大学院 教授
1953年神奈川県生まれ。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授などを経て、2017年4月から現職。
----------
:::::
■四半期売上高は過去最高、日本電産の成長を支える2つの源泉
■“合議制”から“トップダウン体制”に戻した理由
■“すぐやる、必ずやる、出来るまでやる”人を増やす
■長期存続に不可欠な個人の力
特に、EVモーターを中心に「一帯一路・海外遠征・戦狼外交、国家安全維持法=国内・域外・事後遡上適用・法=施行、「海警法」施行共産党一党独裁政府」
【(注ア)焦点:一帯一路・海外遠征・戦狼外交、国家安全維持法=国内・域外・事後遡上適用・法=施行、「海警法」施行共産党一党独裁政府、中国依存のドイツが味わう「ゆでガエル」の恐怖
https://jp.reuters.com/article/germany-china-idJPKBN1HO07I
「武器使用」「防衛作戦への参加」を明記 中国が海警法案全文発表https://www.sankei.com/world/news/201105/wor2011050019-n1.html
https://jp.reuters.com/article/germany-china-idJPKBN1HO07I
「武器使用」「防衛作戦への参加」を明記 中国が海警法案全文発表https://www.sankei.com/world/news/201105/wor2011050019-n1.html
】中国の企業とのシェア争いは激化するだろう。国営・国有をはじめとする中国企業は優秀な人材を確保してソフトウエア面での競争力を発揮し、技術開発に関しても急ピッチで力をつけている。共産党政権は有力企業に土地を提供し、産業補助金も支給している。優秀な人材と固定費の低さが中国(注ア)企業の低価格戦略を支えている。(注1)

国際的な競争激化に備え、日本電産はセルビア(注1)、(注2)に工場を建設して欧州でのEVモーター供給能力を引き上げる方針だ。シェア獲得のために追加的な設備投資や企業買収も必要だろう。

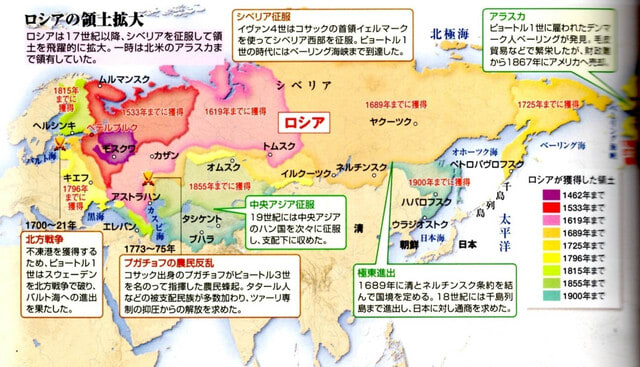
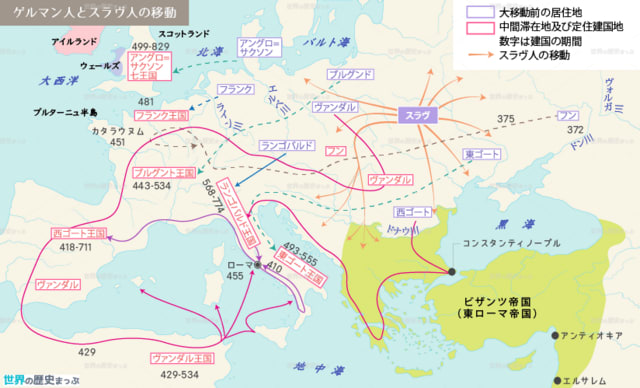

(注1)世界の一人当たりのGDPランキング
順位 国名 単位: USドル 、25位日本 40,255.94 、67位中国10,522.34、85位セルビア7,382.39
(注2)現代[編集]
1991年のユーゴスラビア崩壊の際に日本はユーゴスラビアに対する経済協力を停止するがコソボ紛争終結後の2000年に再開され[6]、2003年に日本の無償資金協力によりベオグラードに93台のバスの整備が行われる[7]などの経済支援が行われた。2004年には在大阪セルビア・モンテネグロ名誉総領事館が開設された[3]。2011年の東日本大震災の際には支援を表明し、セルビア政府は5,000万ディナール(約4,525万円)の義捐金をセルビア赤十字社経由で提供した[8]。セルビアは日本をアジア最大の貿易相手国とみなす[9]など両国関係は良好であるが、日本はコソボを国家承認している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%A8%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%93%E3%82%A2%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82
■モーター分野で世界トップの地位を確立する日
長期の視点で考えると、永守氏が注力する教育と実務の連携に注目したい。
実務家を大学に派遣してモーター開発の実践的知識やビジネスの現場で何が起きているかを教授することは、若者のやる気を刺激する。その上で、日本電産で就業を希望するやる気にあふれた若者が増えれば、同社は人を育て、新しい技術を生み出すサイクルを加速化し、成長の持続性を高めることができるだろう。先駆者のスピリットや理念を後世に伝え、さらなる高みを目指してもらうことは教育の醍醐味だ。経営者の強いリーダーシップ発揮と教育の強化によって、日本電産がモーター分野で世界トップの地位を確立することを期待したい。










