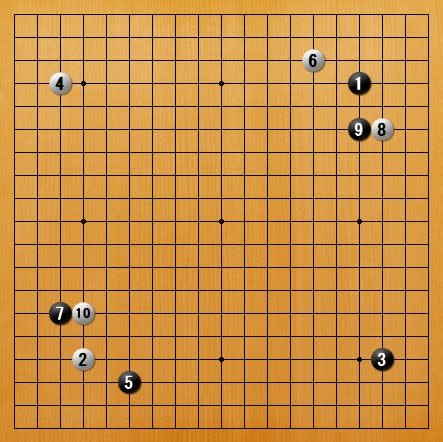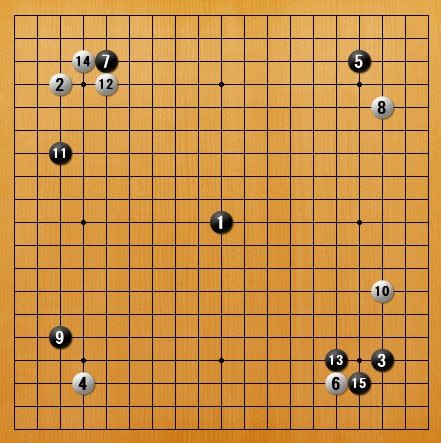皆様こんばんは。
第41回高校選手権個人戦は、男子の部が栗田佳樹さん(港北・神奈川)、女子の部は岩井温子さん(洛北・京都)がそれぞれ優勝しました。
おめでとうございます。
両者共に安定感のある内容で、実力の高さを感じました。
さて、本日私は有楽町囲碁センターで指導碁を行いました。
お越し頂いた方々、ありがとうございました。
今回はいつもと趣向を変えて、指導碁の意義についてお話ししましょう。
過去にも似たようなことをお話ししている気もしますが、重要なことなので・・・。
指導碁は、基本的には文字通り指導を目的としています。
ですから、単に自分より強い人に打って貰うだけなら指導碁とは呼べません。
対局を通して、その人が上達するために役立つ、適切なアドバイスを差し上げなければいけません。
局後の手直しの時間は対局時間に比べれば非常に短いですが、この時間が非常に重要なのです。
手直しはプロ同士の局後検討とは全く違うものです。
例えばプロ同士であれば、ある場面で勝つためにはどうすれば良かったか、といったことを議論することはよくあります。
しかし、手直しにおいては、敗着探しや勝ち筋探しにはあまり意味がありません。
同じ局面は二度と現れないからです。
では何を重視するかといえば、それはその人の進むべき道を示して差し上げることです。
実際に対局することにより、指導者は生徒さんがどういう分野が得意で、どういう分野が苦手なのかを知ることができます。
その上で、生徒さんが何をすれば強くなれるのかをお伝えするのです。
例えば、指導碁で大きなミスを10回した方がいらっしゃったとします。
それらを1つ1つ指摘して、正しい打ち方を示したとしても、そこで終わってしまっては意味がありません。
どうしてミスしてしまうのか、またどうすればミスしなくなるのかをお伝えする方が遥かに重要です。
ほとんどの方には、ミスのパターンがあります。
10回ミスをする方も、そのうち5回ぐらいは同じパターンのミスだったりします。
具体的に例を挙げれば、「石の強弱を意識していない」「相手の地にヤキモチを焼く」などがありますね。
ということは、そこを改善することができれば、1局に出るミスの数を大きく減らすことも可能です。
そのために対局の際の考え方や、あるいは基礎力の向上が必要であれば何をやれば良いのか、といったことをお伝えします。
棋力は指導者が引っ張り上げられるものではなく、結局は本人の意識や努力次第です。
しかし、正しい努力や、正しい碁の考え方をするかどうかで、上達スピードは何倍も変わってきます。
指導碁を受ける際にはそういったことも意識して頂くと、より効果が得やすくなるでしょう。
第41回高校選手権個人戦は、男子の部が栗田佳樹さん(港北・神奈川)、女子の部は岩井温子さん(洛北・京都)がそれぞれ優勝しました。
おめでとうございます。
両者共に安定感のある内容で、実力の高さを感じました。
さて、本日私は有楽町囲碁センターで指導碁を行いました。
お越し頂いた方々、ありがとうございました。
今回はいつもと趣向を変えて、指導碁の意義についてお話ししましょう。
過去にも似たようなことをお話ししている気もしますが、重要なことなので・・・。
指導碁は、基本的には文字通り指導を目的としています。
ですから、単に自分より強い人に打って貰うだけなら指導碁とは呼べません。
対局を通して、その人が上達するために役立つ、適切なアドバイスを差し上げなければいけません。
局後の手直しの時間は対局時間に比べれば非常に短いですが、この時間が非常に重要なのです。
手直しはプロ同士の局後検討とは全く違うものです。
例えばプロ同士であれば、ある場面で勝つためにはどうすれば良かったか、といったことを議論することはよくあります。
しかし、手直しにおいては、敗着探しや勝ち筋探しにはあまり意味がありません。
同じ局面は二度と現れないからです。
では何を重視するかといえば、それはその人の進むべき道を示して差し上げることです。
実際に対局することにより、指導者は生徒さんがどういう分野が得意で、どういう分野が苦手なのかを知ることができます。
その上で、生徒さんが何をすれば強くなれるのかをお伝えするのです。
例えば、指導碁で大きなミスを10回した方がいらっしゃったとします。
それらを1つ1つ指摘して、正しい打ち方を示したとしても、そこで終わってしまっては意味がありません。
どうしてミスしてしまうのか、またどうすればミスしなくなるのかをお伝えする方が遥かに重要です。
ほとんどの方には、ミスのパターンがあります。
10回ミスをする方も、そのうち5回ぐらいは同じパターンのミスだったりします。
具体的に例を挙げれば、「石の強弱を意識していない」「相手の地にヤキモチを焼く」などがありますね。
ということは、そこを改善することができれば、1局に出るミスの数を大きく減らすことも可能です。
そのために対局の際の考え方や、あるいは基礎力の向上が必要であれば何をやれば良いのか、といったことをお伝えします。
棋力は指導者が引っ張り上げられるものではなく、結局は本人の意識や努力次第です。
しかし、正しい努力や、正しい碁の考え方をするかどうかで、上達スピードは何倍も変わってきます。
指導碁を受ける際にはそういったことも意識して頂くと、より効果が得やすくなるでしょう。










 がランチ営業を始めたとのことで、早速お邪魔して来ました。
がランチ営業を始めたとのことで、早速お邪魔して来ました。