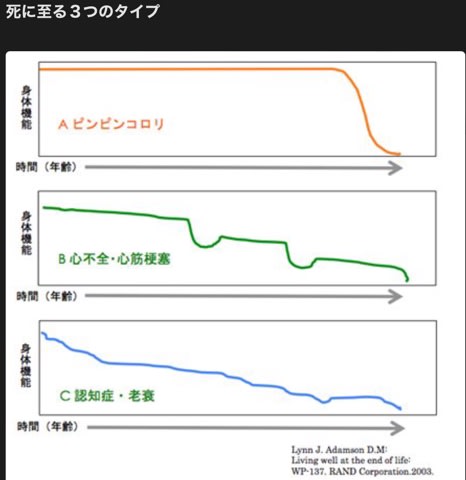「バス」から「鉄道」に変身、「世界初」DMVの運行開始へ…10年越しの構想実る
読売新聞 onlain より 211224
線路と道路を走れる「デュアル・モード・ビークル(DMV)」が徳島、高知県境の第3セクター・阿佐海岸鉄道で走り出す。運行開始は25日。本格的な営業運行は世界初とされ、人口減などで鉄道路線の維持が困難となる地方もある中、維持コストを抑えた存続策として注目される。(新谷諒真、松久高広)
⚫︎モードチェンジ

試乗会で地元住民らを乗せて走る「DMV」(10日、海陽町で)=新谷諒真撮影
営業開始を前に行われた10日の試乗会。地元住民らを乗せ、下りの起点・阿波海南文化村から道路を走ってきたDMVは、阿波海南駅(徳島県海陽町)で車両の底に収納した金属製の車輪を下ろし、「バスモード」から「鉄道モード」にチェンジ。運転士がアクセルペダルを踏み込むと、線路の上を滑るように進み出した。
試乗した阿南市の公務員の女性(59)は「鉄道より揺れが少なくて快適。DMVが話題になって、世界中の人が来てくれたら」と話した。
車両(全長8メートル、幅2メートル)は、トヨタ自動車のマイクロバスを改造。鉄道用の車輪のほか、車両の位置を知らせるシステムや自動列車停止装置(ATS)に相当するブレーキも備える。
主なルートは徳島、高知県境の約15キロ。うち10キロは線路だ。平日は上下26本、土日祝日は30本運行し、土日祝日の1往復のみ、高知・室戸岬まで約50キロを走る。
阿佐海岸鉄道は1年前から鉄道の運行を取りやめ、DMVに合わせて2駅のホームを低くするなどの改修を進めていた。車両3台の導入も含め、費用は16億円。同社の井原豊喜専務は「やっとスタートラインに立てた」と笑顔を見せる。
⚫︎構想十余年
同社がDMVの検討を始めたのは2009年頃。国鉄時代には徳島から室戸方面に路線を延ばす構想があったが、過疎化で利用者は減り続け、現実味は乏しかった。そんな中浮上したのが、JR北海道が02年から検討し、その後中断したDMVの導入だ。
延伸区間は公道を走るため、新たに線路や踏切など鉄道に不可欠な基盤を整備する必要がなく、維持コストも低く抑えられる。
一方、技術的には課題もあった。JR北海道では、鉄道に比べて車体が軽いため、線路に雪が積もると乗り上げて脱線する恐れが浮上した。今回の車両は、国の技術評価検討会が車輪を支える部品について、「長期耐久性は引き続き検証が必要」と指摘。本来なら4年に1度の検査を当面は毎年行う。
⚫︎定員大幅減
地元では観光資源としても期待が高まる。
阿佐海岸鉄道の年間利用者数は、沿線自治体などが出資する3セクとして開業した直後の1992年度の約18万人から、近年は5万人前後に低迷。1便あたり平均4、5人だ。DMV導入で年1万4000人の利用者増を見込み、地域への経済波及効果は約2億1400万円と試算。海陽町の三浦茂貴町長は「新型コロナの影響で観光業が落ち込んだ沿線が盛り上がるはず」と期待する。
しかし、これまでの鉄道が定員約100人(1両)だったのに対し、DMVは約20人と大幅に少ない。当面、地元住民の利用を想定した5人分以外は予約制で、観光シーズンは乗車できない事態が想定される。鉄道部分の運賃もこれまでより4割ほど上がり、利用者の負担となりそうだ。
利用客が増えれば、収支の赤字幅は2020年度の約9100万円から約5400万円に圧縮されるものの、黒字化する見通しは立たない。関係自治体が積み立てた基金からの 補填 ほてん は続く。
営業開始を前に行われた10日の試乗会。地元住民らを乗せ、下りの起点・阿波海南文化村から道路を走ってきたDMVは、阿波海南駅(徳島県海陽町)で車両の底に収納した金属製の車輪を下ろし、「バスモード」から「鉄道モード」にチェンジ。運転士がアクセルペダルを踏み込むと、線路の上を滑るように進み出した。
試乗した阿南市の公務員の女性(59)は「鉄道より揺れが少なくて快適。DMVが話題になって、世界中の人が来てくれたら」と話した。
車両(全長8メートル、幅2メートル)は、トヨタ自動車のマイクロバスを改造。鉄道用の車輪のほか、車両の位置を知らせるシステムや自動列車停止装置(ATS)に相当するブレーキも備える。
主なルートは徳島、高知県境の約15キロ。うち10キロは線路だ。平日は上下26本、土日祝日は30本運行し、土日祝日の1往復のみ、高知・室戸岬まで約50キロを走る。
阿佐海岸鉄道は1年前から鉄道の運行を取りやめ、DMVに合わせて2駅のホームを低くするなどの改修を進めていた。車両3台の導入も含め、費用は16億円。同社の井原豊喜専務は「やっとスタートラインに立てた」と笑顔を見せる。
⚫︎構想十余年
同社がDMVの検討を始めたのは2009年頃。国鉄時代には徳島から室戸方面に路線を延ばす構想があったが、過疎化で利用者は減り続け、現実味は乏しかった。そんな中浮上したのが、JR北海道が02年から検討し、その後中断したDMVの導入だ。
延伸区間は公道を走るため、新たに線路や踏切など鉄道に不可欠な基盤を整備する必要がなく、維持コストも低く抑えられる。
一方、技術的には課題もあった。JR北海道では、鉄道に比べて車体が軽いため、線路に雪が積もると乗り上げて脱線する恐れが浮上した。今回の車両は、国の技術評価検討会が車輪を支える部品について、「長期耐久性は引き続き検証が必要」と指摘。本来なら4年に1度の検査を当面は毎年行う。
⚫︎定員大幅減
地元では観光資源としても期待が高まる。
阿佐海岸鉄道の年間利用者数は、沿線自治体などが出資する3セクとして開業した直後の1992年度の約18万人から、近年は5万人前後に低迷。1便あたり平均4、5人だ。DMV導入で年1万4000人の利用者増を見込み、地域への経済波及効果は約2億1400万円と試算。海陽町の三浦茂貴町長は「新型コロナの影響で観光業が落ち込んだ沿線が盛り上がるはず」と期待する。
しかし、これまでの鉄道が定員約100人(1両)だったのに対し、DMVは約20人と大幅に少ない。当面、地元住民の利用を想定した5人分以外は予約制で、観光シーズンは乗車できない事態が想定される。鉄道部分の運賃もこれまでより4割ほど上がり、利用者の負担となりそうだ。
利用客が増えれば、収支の赤字幅は2020年度の約9100万円から約5400万円に圧縮されるものの、黒字化する見通しは立たない。関係自治体が積み立てた基金からの 補填 ほてん は続く。