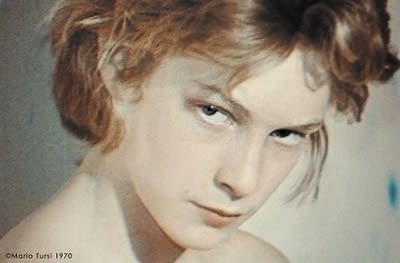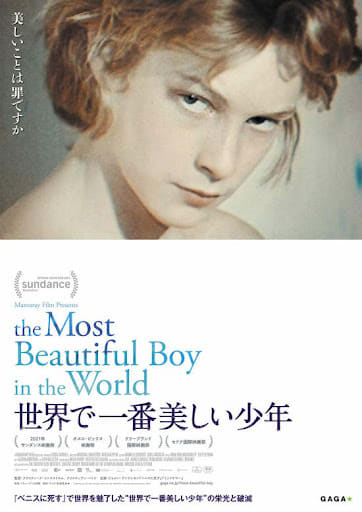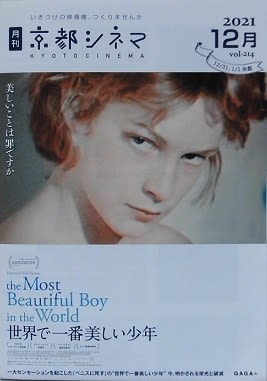黒澤明監督作品「羅生門」(1950)の映画公開70周年と、
黒澤明監督の生誕110年を記念して、京都文化博物館で、
映画「羅生門」展が開かれた。
会期中、4日だけ映画の上映もあった。
映画の上映に合わせて「羅生門展」へ行き、映画も見て来た。

京都文化博物館
https://www.bunpaku.or.jp/
https://www.bunpaku.or.jp/exhi_shibun_post/rashomon/
公開70周年記念 映画『羅生門』展
2021年2月6日(土)〜3月14日(日)
会 場:京都文化博物館 2階総合展示室「京の至宝と文化」
開催趣旨
「ヴェネチア国際映画祭での金獅子賞受賞などにより
黒澤明の名を世界に知らしめた、
日本映画史上の傑作『羅生門』が劇場公開から70年、
監督生誕110年になります。
それを記念し、作品の魅力を様々な視点で感じていただきます。」
+++
「羅生門」はテレビで見た記憶もあるが、はっきりしない(>_<)。
むつかしい映画、あまり面白くない映画、という印象だったかも…。
そこで、撮影監督の宮川一夫のカメラだけ見るためと思い、
見ることにした。
フィルムシアターは文化博物館の3階にあり、
コロナで密を避けるため、席を78人限定で満席としていた。
普段なら160人くらい収容できるようだ。
それでも早くから満席になっていた。
映画「羅生門」のストーリーは誰でも知っていると思い、
詳細は控えるが、芥川の原作で橋本忍の脚本を黒澤が仕上げた。
大映京都で撮影が行われた。
劇場公開当初、日本ではあまり評判にはならず、
ベネチア映画祭で金獅子賞を受賞して、初めて日本でも脚光を浴び、
逆輸入の形で日本でも認められた、
のも誰もが知るとおり。
今回映画を改めて見て、公開当初、評判が良くなかった理由がよく分かる。
戦後まもなく、まだ人々の心が癒えていないころ、
このような人間心理の複雑さ、人間性の真実、
人の心の深層を抉った不条理劇のようなものは、
高尚すぎて受け入れられなかったのではないだろうか。
最後まで見ても真相は分からなくなってしまう。
まるでカフカの不条理劇のような、
「2001年宇宙の旅」のような不可解さ、難解さである。
(志村喬の真相も果たして真実なのか、と思ってしまうのだが…)
ベネチア国際映画祭で金獅子賞を獲得したのも、なぜなのか、
始めは理解出来なかった。
どこが評価されたのだろうか?と。
おそらく、俳優たちの熱演、人間心理の深層に迫るストーリー、
緊迫感を醸成した映画技術が普遍的なものだと認められたからではなかろうか。
この脚本を良しとして、
ゴーサインを出したプロデューサーはえらいと思った。
本木荘二郎という人だ。
製作・配給会社の大映は文芸路線も手がけていたので、
このような作品でもオーケーだったのだろう。
「羅生門展」は京都文化博物館の2階のフロアの一角で、
さほど広くないスペースでの展示だったが、
カメラマン・宮川一夫、俳優の三船敏郎、京マチ子などの
それぞれの撮影台本を展示、
当時の関係者が祇園で酒を飲んだ、などの日記も展示。
撮影時には、羅生門に雨を降らせるため、消防車3台を借りて
土砂降りの雨を再現した、
水に墨汁を混ぜて雨がよく見えるようにした、等の説明。
「羅生門」の撮影の様子を紹介している当時の映画雑誌もあった。
それなりに期待されていたのだろう。
特に目を引いたのは、黒澤明の、ファンからのファンレター(?)
に返事を書いた黒澤直筆の手紙で、
ラストが甘い、と指摘されたらしい。
「羅生門」より「白痴」の方が好きだという興味深い一文も。
もうひとつ、黒澤の言葉が展示されていて、それには
「日本人は日本がきらいだ。
日本人は西欧が好きで、自分たちの国はきらいらしい」
という意味のことが書かれていた。
敗戦で自国に自信をなくしていた日本人が、
自分たちの国の文化を誇れないという、
敗戦直後の日本人の心情を、黒澤は敏感に感じ取っていたのだ。
「羅生門」も日本本国ではあまり認められず、
外国で認められて初めて日本人は、それに目を向けた。
外国に評価されなければ自分たちを認めることが出来ないという、
敗戦直後の日本人の、
自信を喪失した不甲斐なさに喝を入れたかったのかもしれない。
そして「羅生門」がベネチアで賞を取ったことは、
湯川秀樹のノーベル賞受賞のように、日本人に自信を与えた。
戦後、日本映画の質の高さを改めて日本人自身に知らしめることになり、
日本文化の再評価の象徴のようにもなり、
黒澤明の名は戦後日本に鳴り響いた。
「羅生門」はその映画の内容そのものよりも、
外国で評価されたことによる、戦後日本人の自信の拠り所として
名を残すことになったのだと思う。
外国でも沢山の国で上映され、
展示室には各国の映画ポスターが展示されていたが、
外国にも、日本映画の芸術性が
この映画を通して認められたということだろう。

映画は宮川一夫のカメラを見ているうち、
俳優の熱演に引き込まれた。
カメラは直接太陽を映したとして評判になったが、
森の中の木々の葉が、俳優の顔にチラチラと反映するさま、
どのようにカメラを動かしているのか分からないワンカットシーンなど、
白黒のコントラストを強調した宮川のカメラはやはりすごい。
森のシーンからいきなり白洲の場面に変わり、
カメラに向かって俳優がモノローグする場面は、衝撃的でさえある。
まるで実験映画のようで、映画文法を存分に生かしている。
京マチ子のパートでボレロの音楽が流れ、
それが彼女の心理を表すように緊迫感を強調し、印象的だ。
展示によれば、
音楽は、パートごとにまったく違う傾向のものを意識して使ったという。
始め、顔を見せずに登場し、淑やかな風情だった京マチ子が、
白洲での独り芝居をはじめ、パートごとに狂乱する女を熱演、
三船敏郎の荒々しさ、殺陣のリアリティ、
見ているうちに俳優の演技に圧倒されて、退屈はしなかった。
が、退屈はしないが、かと言ってものすごく面白い、
とも言えないとは思う。
人間のエゴの本質を問うた難解な作品であることには
変わりがないと思うからだ。
ただ、戦後わずか5年でこのような人間の本質に迫る格式の高い映画を、
撮影、音楽、ロケ、セット、演技に至るまで妥協なしに
ここまでの完成度で作り上げた演出力には脱帽せざるを得ない。

なぜかオープンスペースにいたまゆまろ( ゚Д゚)
 美術館・ギャラリーランキング
美術館・ギャラリーランキング
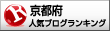 京都府ランキング
京都府ランキング
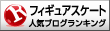 フィギュアスケートランキング
フィギュアスケートランキング
↓ブログ村もよろしくお願いします!
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村