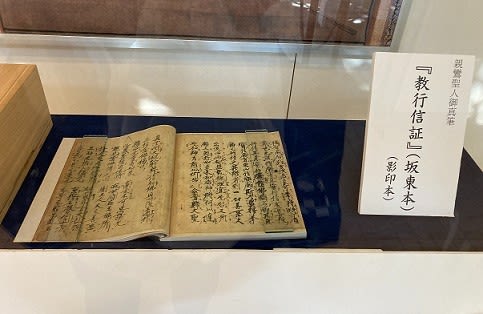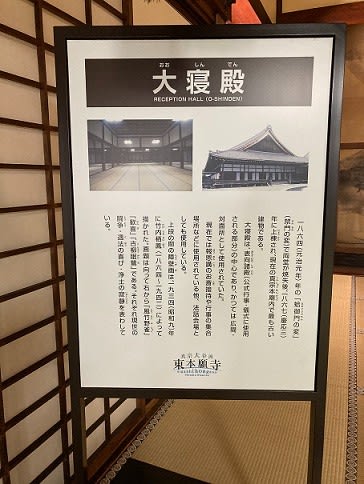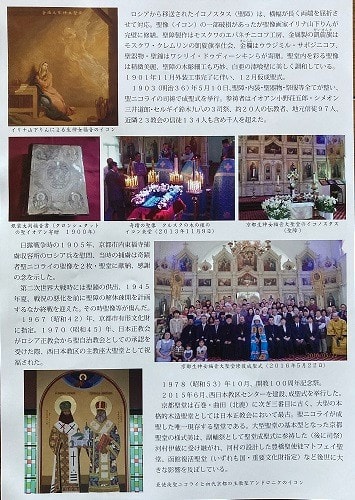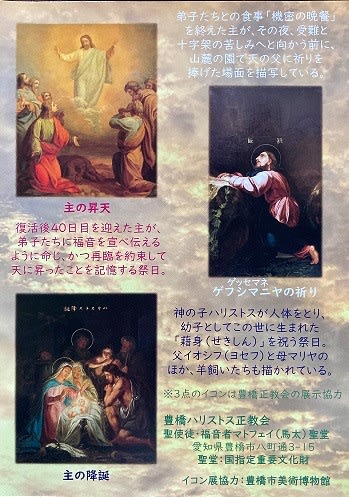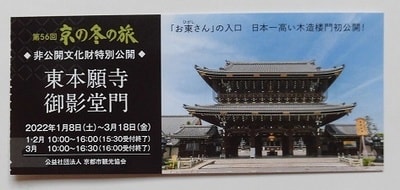毎年行われている「京の冬の旅」の非公開文化財特別公開で、
今年はなんと、近くにあるお寺、上徳寺が含まれていた。
京都市下京区富小路五条下ルにある上徳寺は、
小さいお寺だが、近所ではよつぎ地蔵として知られている。
「京の冬の旅」で初公開されているというので行って来た。


よく前を通るが、中へは入ったことがない。
富小路通を歩いているととても小さいお寺に見えるので、
自由に入れる雰囲気でもなかった。
ただ子授け祈願・安産祈願のお寺なので、
子どもが欲しい人が参拝に来るのだろう。

寺の前には「阿茶の局墓所」という石碑が建っている。
阿茶の局、とは誰だろう、といつも前を通りながら考えていた。
徳川家康の側室の一人だそうである。
上徳寺は阿茶の局を開基として創建された。
家康ゆかりの寺だった。
パンフレットによれば1603年、何と家康によって建立されたとか。
浄土宗のお寺のようだ。
富小路通には浄土宗のお寺が多い。
ここもその一つなのだった。
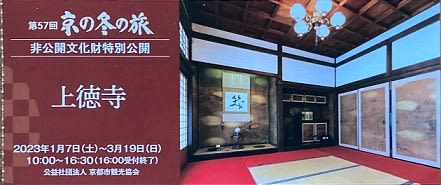
内部はいずれもどこも撮影可能だった。

本堂の中へ入るとそこそこ大きくて、立派な厨子があり、
本尊の阿弥陀如来が祀られていた。

阿弥陀様は2022年11月、重要文化財に指定されたそうで、
現在は東京へその監査のために出張中(?)で、
今あるのはお前立だった。
写真でその姿を見せているだけだった。
見られないのは残念だったが、
近所の小さなお寺に重要文化財の仏像があるのは、
何だかすごいことだと思った。
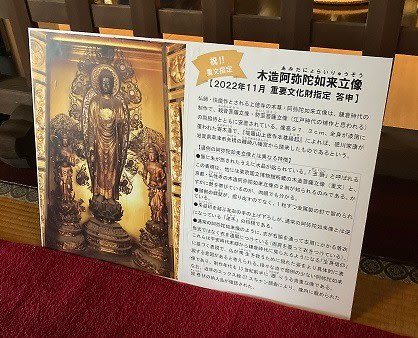
富小路通にはこのような小さなお寺が沢山あり、
その中に重文指定の仏像もあったと思う。
富小路通は秘かにお寺のゴールデンストリートなのだ。
この本堂には今回の特別公開に合わせて、
寺宝が公開されていた。
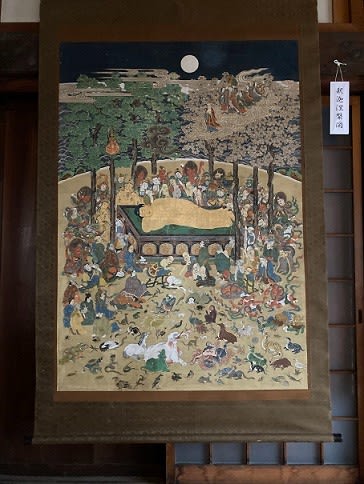
釈迦涅槃図は細い線描が丁寧で、
恐らく江戸時代のものかな、と。

そしてその横には真ん中に阿茶の局、
両脇に家康、秀忠の三幅対の肖像画があった。


次に客殿へ行く。
外から見る限り狭いお寺に見えたが、
案外奥行きがあり、立派な客殿が備えられていた。
案内の人が客殿を見てくれと言っていたが、
なるほどこのような客殿があるとは思わなかった。
見てほしくなるのも無理はないと思った。

庭もとても立派な枯山水庭園だった。
町の中のお寺なので、背景が住宅なのは仕方がない。

そして世継地蔵が安置されている地蔵堂へ。

通常はお地蔵さんは、お堂の前で拝むだけだそうだが、
今回の特別公開ではお堂の内部まで入れ、
地蔵菩薩を横から拝観することが出来た。
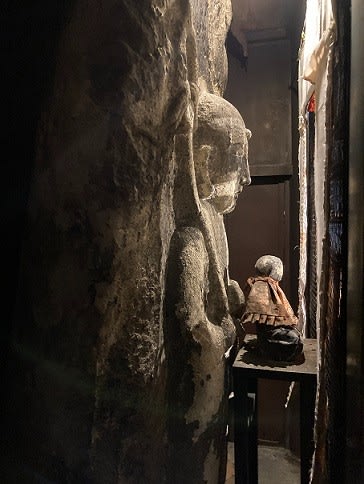
全長2mほどもある大きな地蔵菩薩で、
間近に横顔が見られて感動した。
とても安らかな、穏やかなお顔をしておられた。
このお地蔵さまはこの寺の本尊を信仰していた清水という人が、
世継を失い、子が恵まれるようにと念じて堂に参籠した。
夢中に地蔵が現れ祈念するようにと告げられ、
その尊像を石に刻んで寺内に一宇を建立して世継を祈念した。
願いが叶い、子孫は繁栄、
以来「世継地蔵」として知られるようになった、とか。
(パンフレットより)
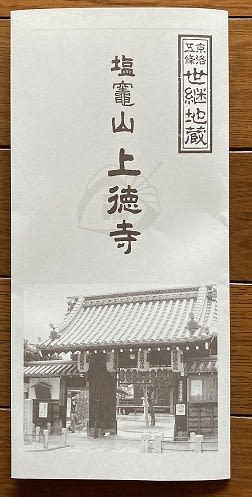
ほんの近所にこのような由来のあるお寺があるとは思わなかった。
というか、思ったより立派な客殿があったのに驚いた。
そして寺宝も沢山所持していることにも驚いた。
前を通るだけでは分からなかった詳しいことが分かり、
たとえ近所の小さいお寺、と思っていても
立派な謂れのある由緒あるお寺だということも分かった。
非公開文化財特別公開のこの機会に内部を見られて
良かったと思った。
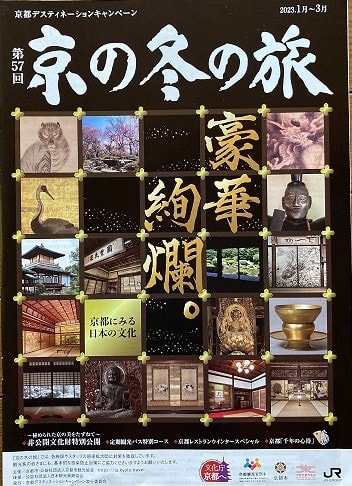
非公開文化財特別公開特別公開は3月19日まで、
料金は1ヶ所800円。
京の冬の旅のキャンペーン期間は3月27日まで─
↓ブログ村もよろしくお願いします!