6/29,30は銀細工で羽織紐・根付を作るワークショップ&家紋講座
https://jizaiya.shop/workshop20190629-inoie/
応援クリックお願いいたしますm(__)m
上のバナーか にほんブログ村の文字をクリック!
なんだか季節がひと月引き戻されたようで寒いです。
旦那がストーブ点けてました。
昨日も結城紬の地機体験にたくさんのご参加ありがとうございます。
小雨模様の中、お着物での方も。
織は楽しいですね。それを仕事にするのは大変だけど・・・
織職人の小柳さんとお話ししていて
本場結城紬について あれこれ教えて頂いたのですが
その中で 衝撃的な事実が!
これ、本場結城紬の八寸帯です。
証紙の条件を満たす 経糸緯糸すべて手引きの真綿糸、地機で織られています。
絣ではないので手による括り、という条件はありません。
見たまんま、太い横糸で織られた ガッシリした帯です。
もちろん本場結城ですから軽いですが 九寸のような羽毛みたい!?という軽さではありません。
八寸ですから お太鼓が自立しなくちゃ意味ないですからね。
緯糸、手で太く引くのだから楽なのかな、下手な人が引いて着物に出来ないのを使うのかな、と
思っていました。
これが 八寸帯用の糸です。
わかりますか?
細い、着物用の糸を12~15本、撚り合わせた糸を緯糸にしているのだそうです。
経糸は着物用の糸そのままです。(100亀甲ほど細くはなく60~80亀甲位)
緯糸に多くの糸を撚り合わせることで
八寸帯1本いは なんと 本場結城紬1反分とほぼ同じ量の糸が使われているのだそうです。
いや、驚きました~~ そりゃ大変な価値ですよ。
それを考えれば お値段的にはお得です。
そしてこれは小柳さんが負った100亀甲の本場結城紬です。

広幅なので 反物の幅の中に114の亀甲が並んでいます。
この亀甲の経糸がこちら。
比較物を入れ忘れたのでサイズが分かりにくいかもしれませんが
ものすっごく細い糸が縞々の絣になっています。
本場結城紬は無撚りの真綿糸なので とてもとても切れやすいのです。
切れてしまったら 絣の柄が狂わないように この補修用の絣糸を使い柄を見極めて繋ぐのです。
亀甲は規則正しく並んでいるの細かいけどまだ繋ぎやすいですが
飛び柄で色が入ってるものなど 繋ぐ糸を間違えると柄がくるってしまいますから
糸を選んで繋ぐのは とても慎重で気の張る仕事です。
本場結城は小麦粉糊を使うのですが
その糊付けは織職人さんが自分が織りやすいように調整してやります。
気温や湿度によって糊の濃度を変え、お鍋で煮て糊を作ります。
この時の糊を煮る温度も 師匠から口伝で伝れたのだそうです。
まだまだ奥が深い紬の世界です。
お客様から綿の種をいただきました。国産の綿です。
3粒入り、今がぎりぎり播き時だそうです。
種の周りに綿が付いてますので水に濡らして植えてください。植木鉢やプランターでも可能です
4名様に差し上げます。できれば店で手渡しできる方・・・
地方の方はご相談ください。
https://www.instagram.com/sakurako_jizaiya/
フォローよろしくお願いいたします
目指せ!フォロワー1000人!!
下の「着物・和装・業者」というバナーか、「にほんブログ村」という文字をクリックして下さい。
ブログ村ランキングページへ飛びますので、そうしたら1ポイント入ります。(inポイント)
次にブログ村の「きものがたり」じざいやブログのところをクリックしてこのページに戻りますと、outポイントが付きます。











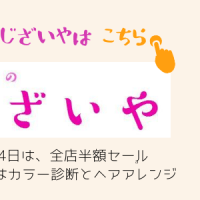











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます