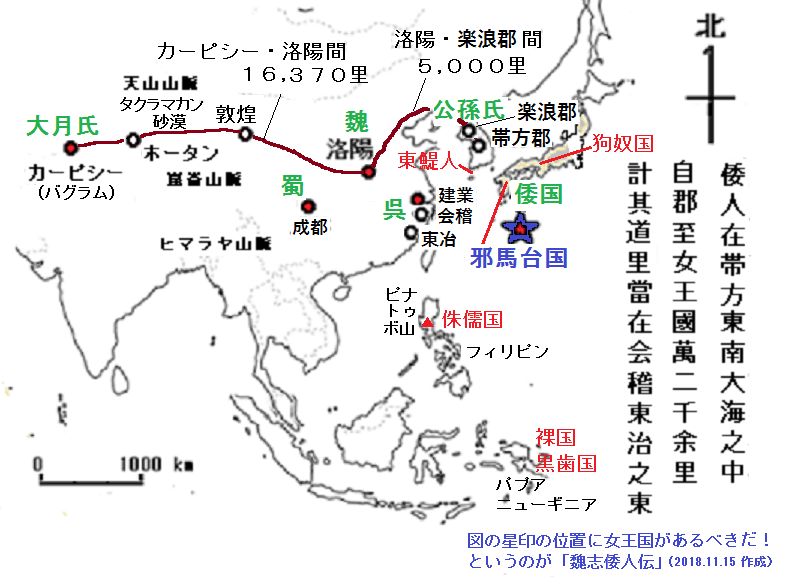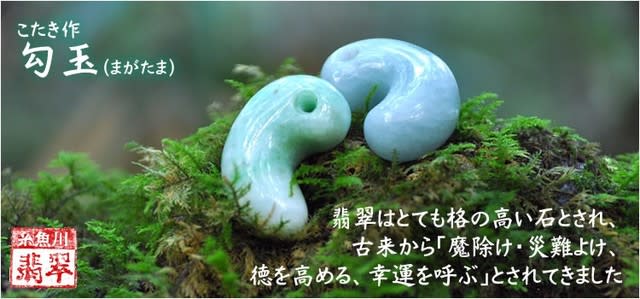いつも応援ありがとうございます。
よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
現代日本に残る古い民間信仰の原初的なもののひとつは前回見た道祖神信仰ですが、ご存知のように道教と習合した庚申信仰というのがあり、とても面白いです。道端に「庚申」と彫られた石塔などいろいろなものが全国で見られますね。今日はこの話です。最後までお付き合い下さい( ^)o(^ )

庚申(かのえさる、こうしん)は、 陰陽五行説では、十干の庚は陽の金、十二支の申は陽の金で、比和(同気が重なる)とされている。干支であるので、年(西暦年を60で割り切れる年)を始め、月(西暦年の下1桁が3・8(十干が癸・戊)の年の7月)、さらに日(60日ごと)がそれぞれに相当する。庚申の年・日は金気が天地に充満して、人の心が冷酷になりやすいとされた。
この庚申の日に禁忌(きんき)行事を中心とする信仰があり、日本には古く上代に体系的ではないが移入されたとされている。とあります。さらに、
青面金剛と呼ばれる独特の神体を本尊とするが、これは南方熊楠によればインドのヴィシュヌ神が転化したものではないかという[4][5]。 石田英一郎によれば青面金剛にはまた馬頭観音(インドのハヤグリーヴァ)との関連性も見られるという[6]。
庚申信仰はまた神道の猿田彦神とも結びついているが、これは「猿」の字が「庚申」の「申」に通じたことと、猿田彦が塞の神とも同一視され、これを「幸神」と書いて「こうしん」とも読み得たことが原因になっているという[7]。
また庚申信仰では猿が庚申の使いとされ、青面金剛像や庚申塔には「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が添え描かれることが多かった。とあります。

道祖神もサルタヒコを表に出して、本当の神の正体である大国主狗古智卑狗(久々遅彦)を隠していますが、庚申信仰ではさらに道教だけでなく密教や修験道などの考え方を取り入れて神霊を鎮魂することにより、ご利益が得られると信じたのだと思われます。
また、Wikiに依れば庚申信仰の起源となるものとしては、平安時代の貴族が行った庚申の日の行事が記録に見られます。この夜を過ごす際に、碁・詩歌・管弦の遊びを催す「庚申御遊(こうしんぎょゆう)」と称する宴をはるのが貴族の習いであった。最も早い記録では清和天皇の代に貞観5年(863年)11月1日の庚申に宮中で宴がもたれ、音楽が奏せられている[2]。9世紀末から10世紀の頃には、庚申の御遊は恒例化していた。やがて「庚申御遊」と呼ばれた平安時代末期には、酒なども振る舞われるようになり、庚申本来の趣旨からは外れた遊興的な要素が強くなった[3]。
<中略>
やがて守庚申は、庚申待(こうしんまち)と名を変え、一般の夜待と同じように会食談義を行って徹宵する風習として伝わった。庚申待とは、“庚申祭”あるいは“庚申を守る”の訛ったものとか、当時流行していた“日待・月待”といった行事と同じく、夜明かしで神仏を祀ることから「待」といったのではないかと推測される(いにしえのカミ祀りは夜に行うものであった)。
庚申待が一般に広まったのがいつ頃かは不明だが、15世紀の後半になると、守庚申の際の勤行や功徳を説いた『庚申縁起』が僧侶の手で作られ、庚申信仰は仏教と結びついた。仏教と結びついた信仰では、諸仏が本尊視され始めることになり、行いを共にする「庚申講」が組織され、講の成果として「庚申塔」の前身にあたる「庚申板碑」が造立され出した。また「日吉(ひえ)山王信仰」とも習合することにより、室町時代の後期から建立が始まる「庚申(供養)塔」や「碑」には、「申待(さるまち)」と記したり、山王の神使である猿を描くものが著しくなる。
飛鳥・奈良時代に秦河勝によって始められたと言われる申楽(さるがく)が同じ室町時代に観阿弥・世阿弥によって集大成されました。ということは、仏教と結びついたのはその時期と一致しますので、この時代にその形が完成したということでしょうか。比叡山の麓の日吉大社が全国の日枝神社の総本社で、その御祭神は、西本宮:大己貴神(大物主に同じ)東本宮:大山咋神となっています。大山咋神は京都嵐山にある秦氏の松尾大社の御祭神で、『秦氏本系帳』によると、上賀茂神社(賀茂別雷神社)の賀茂別雷大神です。伊勢神宮と賀茂神社だけに斎宮制度があり、両社は同格なのだと分かります。つまり、伊勢神宮の御祭神の正体が大山咋神であり大己貴神であり、すべて大国主狗古智卑狗だったと分かります。
ヤマトに国譲りをした神ですから。神々の中で最も崇りの怖ろしい神として、貴族から庶民までが色々な神名やお姿で丁重に祀っているのですね。地震や火山噴火や津波や疫病まで、ありとあらゆる災難を起こすと考えられていたからです!現代人は科学が発達しているので、そんなのは迷信だと思っている方が多いのかも知れませんが、ご存知のとおり科学は万能ではないです。日本列島では大国主を代表とする数多くの神々がいます。大国主は奴国の最後の大王スサノヲの子孫です。スサノヲの父はイザナギでその祖先はアメノミナカヌシです。また、スサノヲの母はイザナミですが、卑弥呼や台与とも血が繋がっています。これらの神々はわたしたち日本人とすべて霊的に繋がっていますので、わたしたちの運命のカギを握っていると考えた方が無難ですよ( ^)o(^ )
【関連記事】
「神」はサルタヒコを示す暗号文字だった?!
道祖神もやっぱり(^_-)-☆
能楽「翁」は大国主のサンバだった?(*^。^*)
能楽が建国の真相を伝える?(^_-)-☆
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
応援をしていただき、感謝します。
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング
よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング現代日本に残る古い民間信仰の原初的なもののひとつは前回見た道祖神信仰ですが、ご存知のように道教と習合した庚申信仰というのがあり、とても面白いです。道端に「庚申」と彫られた石塔などいろいろなものが全国で見られますね。今日はこの話です。最後までお付き合い下さい( ^)o(^ )

庚申(かのえさる、こうしん)は、 陰陽五行説では、十干の庚は陽の金、十二支の申は陽の金で、比和(同気が重なる)とされている。干支であるので、年(西暦年を60で割り切れる年)を始め、月(西暦年の下1桁が3・8(十干が癸・戊)の年の7月)、さらに日(60日ごと)がそれぞれに相当する。庚申の年・日は金気が天地に充満して、人の心が冷酷になりやすいとされた。
この庚申の日に禁忌(きんき)行事を中心とする信仰があり、日本には古く上代に体系的ではないが移入されたとされている。とあります。さらに、
青面金剛と呼ばれる独特の神体を本尊とするが、これは南方熊楠によればインドのヴィシュヌ神が転化したものではないかという[4][5]。 石田英一郎によれば青面金剛にはまた馬頭観音(インドのハヤグリーヴァ)との関連性も見られるという[6]。
庚申信仰はまた神道の猿田彦神とも結びついているが、これは「猿」の字が「庚申」の「申」に通じたことと、猿田彦が塞の神とも同一視され、これを「幸神」と書いて「こうしん」とも読み得たことが原因になっているという[7]。
また庚申信仰では猿が庚申の使いとされ、青面金剛像や庚申塔には「見ざる、言わざる、聞かざる」の三猿が添え描かれることが多かった。とあります。

道祖神もサルタヒコを表に出して、本当の神の正体である大国主狗古智卑狗(久々遅彦)を隠していますが、庚申信仰ではさらに道教だけでなく密教や修験道などの考え方を取り入れて神霊を鎮魂することにより、ご利益が得られると信じたのだと思われます。
また、Wikiに依れば庚申信仰の起源となるものとしては、平安時代の貴族が行った庚申の日の行事が記録に見られます。この夜を過ごす際に、碁・詩歌・管弦の遊びを催す「庚申御遊(こうしんぎょゆう)」と称する宴をはるのが貴族の習いであった。最も早い記録では清和天皇の代に貞観5年(863年)11月1日の庚申に宮中で宴がもたれ、音楽が奏せられている[2]。9世紀末から10世紀の頃には、庚申の御遊は恒例化していた。やがて「庚申御遊」と呼ばれた平安時代末期には、酒なども振る舞われるようになり、庚申本来の趣旨からは外れた遊興的な要素が強くなった[3]。
<中略>
やがて守庚申は、庚申待(こうしんまち)と名を変え、一般の夜待と同じように会食談義を行って徹宵する風習として伝わった。庚申待とは、“庚申祭”あるいは“庚申を守る”の訛ったものとか、当時流行していた“日待・月待”といった行事と同じく、夜明かしで神仏を祀ることから「待」といったのではないかと推測される(いにしえのカミ祀りは夜に行うものであった)。
庚申待が一般に広まったのがいつ頃かは不明だが、15世紀の後半になると、守庚申の際の勤行や功徳を説いた『庚申縁起』が僧侶の手で作られ、庚申信仰は仏教と結びついた。仏教と結びついた信仰では、諸仏が本尊視され始めることになり、行いを共にする「庚申講」が組織され、講の成果として「庚申塔」の前身にあたる「庚申板碑」が造立され出した。また「日吉(ひえ)山王信仰」とも習合することにより、室町時代の後期から建立が始まる「庚申(供養)塔」や「碑」には、「申待(さるまち)」と記したり、山王の神使である猿を描くものが著しくなる。
飛鳥・奈良時代に秦河勝によって始められたと言われる申楽(さるがく)が同じ室町時代に観阿弥・世阿弥によって集大成されました。ということは、仏教と結びついたのはその時期と一致しますので、この時代にその形が完成したということでしょうか。比叡山の麓の日吉大社が全国の日枝神社の総本社で、その御祭神は、西本宮:大己貴神(大物主に同じ)東本宮:大山咋神となっています。大山咋神は京都嵐山にある秦氏の松尾大社の御祭神で、『秦氏本系帳』によると、上賀茂神社(賀茂別雷神社)の賀茂別雷大神です。伊勢神宮と賀茂神社だけに斎宮制度があり、両社は同格なのだと分かります。つまり、伊勢神宮の御祭神の正体が大山咋神であり大己貴神であり、すべて大国主狗古智卑狗だったと分かります。
ヤマトに国譲りをした神ですから。神々の中で最も崇りの怖ろしい神として、貴族から庶民までが色々な神名やお姿で丁重に祀っているのですね。地震や火山噴火や津波や疫病まで、ありとあらゆる災難を起こすと考えられていたからです!現代人は科学が発達しているので、そんなのは迷信だと思っている方が多いのかも知れませんが、ご存知のとおり科学は万能ではないです。日本列島では大国主を代表とする数多くの神々がいます。大国主は奴国の最後の大王スサノヲの子孫です。スサノヲの父はイザナギでその祖先はアメノミナカヌシです。また、スサノヲの母はイザナミですが、卑弥呼や台与とも血が繋がっています。これらの神々はわたしたち日本人とすべて霊的に繋がっていますので、わたしたちの運命のカギを握っていると考えた方が無難ですよ( ^)o(^ )
【関連記事】
「神」はサルタヒコを示す暗号文字だった?!
道祖神もやっぱり(^_-)-☆
能楽「翁」は大国主のサンバだった?(*^。^*)
能楽が建国の真相を伝える?(^_-)-☆
通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)
応援をしていただき、感謝します。
よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )
 古代史ランキング
古代史ランキング