
3月3日(木曜日)
 であったが北西の風冷たし。
であったが北西の風冷たし。午前中は定期通院。
午後父親のでた本家の畑に蕗のトウが
出たよとのことで採って貰って天麩羅にした。
苦みがあって美味しい。初物だ良いこと有るかな!
未だ出始めたところ!又貰いに行こう。

春を感じますねえ!
カミさんの奥秩父の実家は、まだまだ蕗のトウはでない。
今月下旬になるだろう。お彼岸に行ったらチェックしてみよう。
秩父方言では”フキッタマ”という。
いっぱい出るので楽しみだ!
3時~昨日に続いて畑に石灰をふって耕運機をかける。
風が強くて石灰が飛び散った。まあこれでジャガイモの床作りの準備ができそうだ!
モリタネで”男爵 北あかり トウヤ”の3種類を買ってきた。
畑を耕運をするとカラスやいろんな鳥が表れて虫やミミズをついばむ。
良いこともしてるんだと思う。
今日は雛祭り
当家は女の子がいないので華やかさに欠ける。
******************************************

ちょっと調べてみました。
意外と知らないひな祭りの豆知識
ひな祭りといえば、お雛様
3月3日は桃の節句・ひな祭り。女の子のすこやかな成長を祈る節句です。
女の子のいるご家庭なら、お雛様を飾ったり、パーティを開いたりして、
お祝いをするでしょうか。
なんでひな祭りには雛人形を飾るの?
雛人形の雛壇が赤いのはどうして?
お雛様、お内裏様、三人官女、五人囃子、その下にいる人たちは誰? などなど、
子どもに聞かれることもあると思います。
そんなときに役に立つ、ひな祭りの由来と初節句についてお伝えします。
雛人形の豆知識については秀光人形工房の女流人形師の土屋むつみさんにお話を伺いました。
ひな祭りの由来
ひな祭り=桃の節句の起源は、平安時代までさかのぼります。
昔の日本には五つの節句がありました。
この節句という行事が、貴族の間では季節の節目の身の汚れを祓う大切なものでした。
人日(じんじつ) → 1月7日「七草がゆ」
上巳(じょうし) → 3月3日「桃の節句」
端午(たんご) → 5月5日「端午の節句」
七夕(たなばた) → 7月7日「七夕祭り」
重陽(ちょうよう)→ 9月9日「菊の節句」
(※「菊の節句」は現在はなくなっています)
上の日にちからもわかるように、「上巳の節句」が、
現在の「ひな祭り(桃の節句)」になっています。
平安時代、上巳の節句の日は薬草を摘んで、
その薬草で体のけがれを祓って健康・厄除けを願いました。
雛人形の由来
厄と一緒に人形を流す「流し雛」
平安時代には、出産の際の死亡率が高かったので、
命を持っていかれないよう、枕元に身代わりの人形を置く風習がありました。
人形(ひとがた)とは、身代わりという意味。
この風習は、自分の災厄を引き受けてくれた人形を流す「流し雛」へと発展し、
今も残っています。
また、雛人形のひな(ひいな)とは、小さくてかわいいものという意味があります。
平安時代、宮中では「紙の着せ替え人形」で遊ぶ「ひいな遊び」が行われていました。
室町時代になると、上巳の節句が3月3日に定着。紙の雛から、
豪華なお雛様を飾るようになり、宮中で盛大にお祝いをするようになったのです。
それが宮中から、武家社会・裕福な家庭や名主の家庭へと広がっていき、
今のひな祭りの原型が完成しました。
段飾りが飾られるようになったのは、江戸中期のこと。
昭和に入ってから、今のような雛人形の形になりました。
******と有りました。
















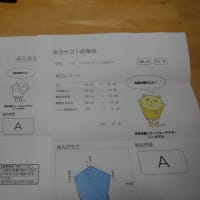



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます