
関西のお笑い芸人が、多額の年収がありながら、母親に生活保護を受けさせていたことを批判されている。
去年200万世帯だった生活保護者が、1年間で209万人(うち60歳以上52%、子ども15%、世帯数では15万)に増え、3兆円近くの歳出となっており、危機的な国家財政をますます圧迫している。(2012年国と地方の予算3.7兆円、うち医療扶助が半分)
バブル破綻後の90年代から2000年ミレニアム・ショック時の大量リストラ、2008年米初リーマンショックなど、失業・非正規社員化が進み、最低限の生活ができない人たちが急増し,とくに、若者の保護受給が増え続けている。
今、この生活保護が、なぜこんなに大きな問題になっているのか?
①高収入の子が、親の面倒を見ないで税金を無駄にしている。(不正受給:厚労省2010年調べ2.5万件、128億円で全体の0.5%未満)
②国民年金だけの高齢者の収入(40年満額でも月7万弱)の方が、生活保護手当より少ない。
③最低賃金であくせく働いても、月12-13万円しかならないなら、生活保護のほうが得という風潮
209万のうち、現役世代80万、このうちの40万人は働ける(就労支援を受けている人7万人にすぎない)
生活保護制度の法的な根拠を確認してみたい。
生活保護法(S25.5.4法第144号):
憲法第25条(生存権、国の社会保障的義務)「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
という理念に基づき、「生活に困窮する国民に、その程度に応じて、必要な保護をにより裁定限度のj生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」
保護の要件として、
まず、資産(預貯金・不動産など)、能力その他あらゆるものを活用しているか。
次に、民法(M29法第89号)に定める扶養義務者による扶養が優先して行われているか。
民法第877条(扶養義務者):①直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。
②家庭裁判所は、特別な事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法730条でも、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と規定する。
なお、夫婦については、民法第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と別に規定。
扶養には私的扶養(民法による扶養)と公的扶養(社会的・国家的な扶養)の二種類があるが、私的扶養が困難な場合のみ公的扶養が開始されるというのが法の原則である(親族扶養優先の原則、私的扶養優先の原則、公的扶助の補充性)
つまり、民法では、個人が世帯主であっても、生活困窮した場合には、親族が扶養すべきだ、という基本的な考え方。
しかも、状況によっては、甥・姪、叔父・おばまで、その扶養義務を負う、としている。
これには、正直言って驚いた。
まるで、戦前の家族制度のまんまではないか!
そこで、戦前の旧民法(M31年制定)とは、どんなものだったのか?
「家」は、戸主と家族から構成され、戸主は家の統率者で、家族に対する扶養義務を負う一方、以下の戸主権を持つ。
・家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(旧民法750条)
・家族の入籍・去家に対する同意権(同735/737/738条)
・家族の居所指定権(同749条)
・家籍から排除する権利(戸主に従わない場合の離積、入籍拒否など)
戦中、戦前の親の話に、親代わりとか家督相続、離縁・勘当、隠居とかいう言葉がよく出てきていたが、家族の掟とも言える慣習が、ちゃんと法律で定められていた訳だ。戸主が「隠居」するとは、家督を子などに譲る代わりに、財産権や扶養義務と同時に戸主権も手放すことだった。
ちなみに、通常、隠居のできる条件に一つとして、満60歳以上(同752条)といったものもあった。
財産権は、すべてが家督相続人(新戸主)に単独相続となり、現在の民法(複数)と大きく違っていた。
新戸主は、家族の中から、男女・嫡出子庶子・長幼の順での上位の者、旧戸主の指定者、その父母や親族会により選定された者などで決められたが、通常長男が家督相続人として承継した。
つまり、長男だけが大切にされ、次男以下は身一つで家を出なければならない、女は戸主の一存で嫁がされる、という過酷な面もあった。
この制度は、江戸時代の武士階級の家父長制的な家族制度を基にしていると言われ、国家⇒地域社会⇒家族という封建制の強固な基盤となっていた。
とくに、女性の権利は認められず、「女三界に家なし」と言われ、「幼い時は親に従い、嫁に行っては夫に従い、老いては子に従わなければならない」という過酷な運命を強いられた。今の80代の母親世代は、ほとんどそうだったのではないだろうか。
戦後の「女性参政権」と「日本国憲法」の施行(1947.5.3)に合わせて、新民法の大規模改正が行われ、親族権・相続権が根本的に変更され、「家制度」は廃止された。
ところが、この旧民法「家族の扶養義務」の一部が新民法にも引き継がれ、先の扶養義務として現在も生きている、という訳だ。
国家による個人単位の社会保障と家族・親族や地域の”キヅナ”の関係を、どう考えるべきだろうか?
戦前の家族・地域の”タスケアイ”’キヅナ’は、人間生活の美徳である反面、窮屈な監視社会、村八分など個人の自由を束縛する一面がある。
国家が、財政支出削減とか統治しやすさという意図で、家族の扶養義務を強化するような動きが感じられてならない。
(小宮山厚労大臣も、生活保護の支給要件の厳格化を言及、マスコミも不正受給のキュンペーン?)
海外の扶養制度では、私的扶養は極めて限定的で、社会保障などの公的扶養が中心という。
ドイツ:「直系血族間においてのみ、親族間の扶養義務を認める(ドイツ民法第160条第1項)」
イタリア:「一親等の直系姻族までに限って、親族間の扶養義務を認める(イタリア民法第434条)」
イギリス・フランス・スエーデン:夫婦、未婚のカップルと未成年の子に扶養義務を限定
(そもそも、扶養義務が保護に優先するという考え方自体がない)
アメリカ:夫婦間と未成年のみ扶養義務(カリフォルニアは成人した子にも拡大)
去年200万世帯だった生活保護者が、1年間で209万人(うち60歳以上52%、子ども15%、世帯数では15万)に増え、3兆円近くの歳出となっており、危機的な国家財政をますます圧迫している。(2012年国と地方の予算3.7兆円、うち医療扶助が半分)
バブル破綻後の90年代から2000年ミレニアム・ショック時の大量リストラ、2008年米初リーマンショックなど、失業・非正規社員化が進み、最低限の生活ができない人たちが急増し,とくに、若者の保護受給が増え続けている。
今、この生活保護が、なぜこんなに大きな問題になっているのか?
①高収入の子が、親の面倒を見ないで税金を無駄にしている。(不正受給:厚労省2010年調べ2.5万件、128億円で全体の0.5%未満)
②国民年金だけの高齢者の収入(40年満額でも月7万弱)の方が、生活保護手当より少ない。
③最低賃金であくせく働いても、月12-13万円しかならないなら、生活保護のほうが得という風潮
209万のうち、現役世代80万、このうちの40万人は働ける(就労支援を受けている人7万人にすぎない)
生活保護制度の法的な根拠を確認してみたい。
生活保護法(S25.5.4法第144号):
憲法第25条(生存権、国の社会保障的義務)「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
という理念に基づき、「生活に困窮する国民に、その程度に応じて、必要な保護をにより裁定限度のj生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的」
保護の要件として、
まず、資産(預貯金・不動産など)、能力その他あらゆるものを活用しているか。
次に、民法(M29法第89号)に定める扶養義務者による扶養が優先して行われているか。
民法第877条(扶養義務者):①直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。
②家庭裁判所は、特別な事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
民法730条でも、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」と規定する。
なお、夫婦については、民法第752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と別に規定。
扶養には私的扶養(民法による扶養)と公的扶養(社会的・国家的な扶養)の二種類があるが、私的扶養が困難な場合のみ公的扶養が開始されるというのが法の原則である(親族扶養優先の原則、私的扶養優先の原則、公的扶助の補充性)
つまり、民法では、個人が世帯主であっても、生活困窮した場合には、親族が扶養すべきだ、という基本的な考え方。
しかも、状況によっては、甥・姪、叔父・おばまで、その扶養義務を負う、としている。
これには、正直言って驚いた。
まるで、戦前の家族制度のまんまではないか!
そこで、戦前の旧民法(M31年制定)とは、どんなものだったのか?
「家」は、戸主と家族から構成され、戸主は家の統率者で、家族に対する扶養義務を負う一方、以下の戸主権を持つ。
・家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(旧民法750条)
・家族の入籍・去家に対する同意権(同735/737/738条)
・家族の居所指定権(同749条)
・家籍から排除する権利(戸主に従わない場合の離積、入籍拒否など)
戦中、戦前の親の話に、親代わりとか家督相続、離縁・勘当、隠居とかいう言葉がよく出てきていたが、家族の掟とも言える慣習が、ちゃんと法律で定められていた訳だ。戸主が「隠居」するとは、家督を子などに譲る代わりに、財産権や扶養義務と同時に戸主権も手放すことだった。
ちなみに、通常、隠居のできる条件に一つとして、満60歳以上(同752条)といったものもあった。
財産権は、すべてが家督相続人(新戸主)に単独相続となり、現在の民法(複数)と大きく違っていた。
新戸主は、家族の中から、男女・嫡出子庶子・長幼の順での上位の者、旧戸主の指定者、その父母や親族会により選定された者などで決められたが、通常長男が家督相続人として承継した。
つまり、長男だけが大切にされ、次男以下は身一つで家を出なければならない、女は戸主の一存で嫁がされる、という過酷な面もあった。
この制度は、江戸時代の武士階級の家父長制的な家族制度を基にしていると言われ、国家⇒地域社会⇒家族という封建制の強固な基盤となっていた。
とくに、女性の権利は認められず、「女三界に家なし」と言われ、「幼い時は親に従い、嫁に行っては夫に従い、老いては子に従わなければならない」という過酷な運命を強いられた。今の80代の母親世代は、ほとんどそうだったのではないだろうか。
戦後の「女性参政権」と「日本国憲法」の施行(1947.5.3)に合わせて、新民法の大規模改正が行われ、親族権・相続権が根本的に変更され、「家制度」は廃止された。
ところが、この旧民法「家族の扶養義務」の一部が新民法にも引き継がれ、先の扶養義務として現在も生きている、という訳だ。
国家による個人単位の社会保障と家族・親族や地域の”キヅナ”の関係を、どう考えるべきだろうか?
戦前の家族・地域の”タスケアイ”’キヅナ’は、人間生活の美徳である反面、窮屈な監視社会、村八分など個人の自由を束縛する一面がある。
国家が、財政支出削減とか統治しやすさという意図で、家族の扶養義務を強化するような動きが感じられてならない。
(小宮山厚労大臣も、生活保護の支給要件の厳格化を言及、マスコミも不正受給のキュンペーン?)
海外の扶養制度では、私的扶養は極めて限定的で、社会保障などの公的扶養が中心という。
ドイツ:「直系血族間においてのみ、親族間の扶養義務を認める(ドイツ民法第160条第1項)」
イタリア:「一親等の直系姻族までに限って、親族間の扶養義務を認める(イタリア民法第434条)」
イギリス・フランス・スエーデン:夫婦、未婚のカップルと未成年の子に扶養義務を限定
(そもそも、扶養義務が保護に優先するという考え方自体がない)
アメリカ:夫婦間と未成年のみ扶養義務(カリフォルニアは成人した子にも拡大)










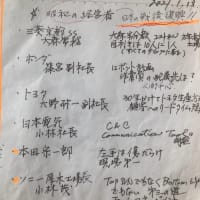
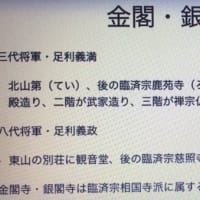
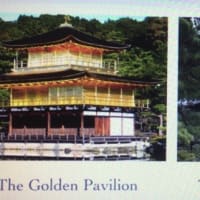
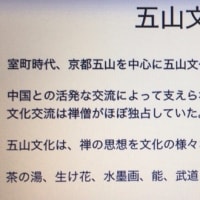
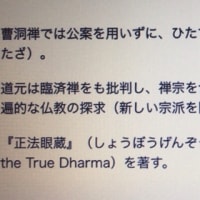
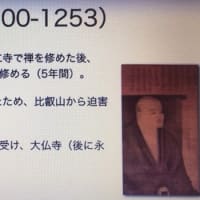
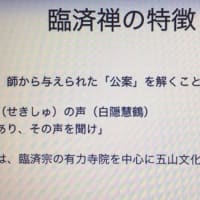
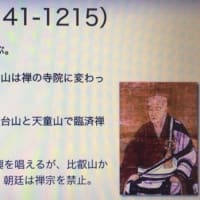
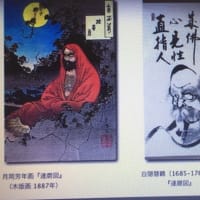
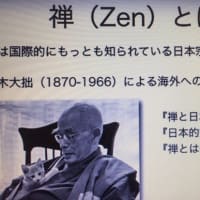






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます