
館岸山のハイキングコースの案内板。
今回、反時計回りで回ったワケですが、城址だけを目指すのであれば、逆回りの方が距離的には近そうです。
ただし、傾斜が半端なくきついので、お薦めできません。
また、道に迷うことが考えられますので、慣れている人と、一緒に行くことをお薦めします。
館岸山の頂上から、少し下ると・・・
 土塁が見えてきます。
土塁が見えてきます。
 土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・
土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・
 こんな看板が道々に立っています。
こんな看板が道々に立っています。
「小山氏の乱」(1380~1397)の際の書状に、「朝日山御陣」とあるのが館岸城と推測されているので、「朝日城」と書かれているんでしょうね。
 空堀。
空堀。
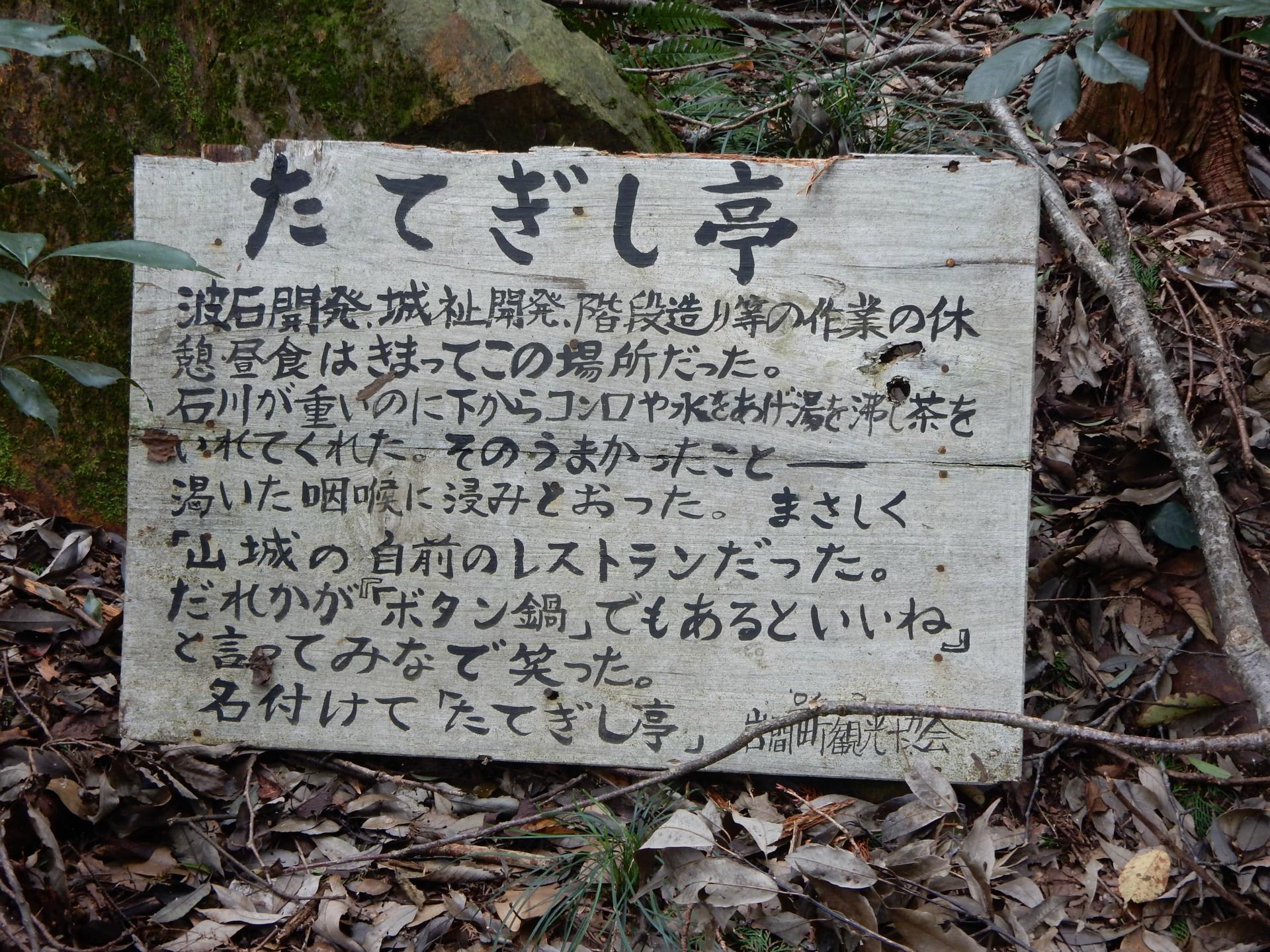 途中、城址開発の名残、
途中、城址開発の名残、
 「たてぎし亭」を通り・・・
「たてぎし亭」を通り・・・
 「堀障子」に至る。
「堀障子」に至る。
え?
「障子堀」じゃないの? って思ったんだけど。
後北条氏の城なんかに見られるものとは、ちょっと違うみたい。
「障子掘り」は、水堀の中に、障子の桟(さん)のような凹凸を設ける防御施設。
敵が堀を越えようとして、凹凸に足をとられている間に、弓矢などで攻撃する、というシロモノ。
 で、これが館岸城の「堀障子」。
で、これが館岸城の「堀障子」。
 写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。
写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。
「低」の文字が堀底。
向こうの堀底との間に、一段、高くなった仕切りが設けられています。

んで、ここに何か、落ちてるんですよ。
 解説だった(笑)
解説だった(笑)
(全文)
堀(濠)障子
地面を掘って水を通したものを堀という。
しかし、館岸城の場合、空堀(濠)である。
土塁と土塁の間に堀(濠)を造り、空堀の底は通路としている。
土塁は敵の浸入を防ぐ防禦敷設としたものであるが、
堀(濠)障子とは、土塁下の堀を敵が浸入して来た時に、堀障子の土壁に兵士が隠れて、敵を迎え撃った。
(攻めてくる敵を待ち受けて攻撃した。)
障子は和風建築の屏障具(へいしょうぐ)の総称であるが、その防禦壁を障子にたとえ、堀障子と称した。
・・なるほど、ここに兵が身を伏せて、敵を攻撃するワケですか。
空堀ならではの使い方ですな。
 土塁が続く。
土塁が続く。
 そして・・・
そして・・・
 ここが城址。
ここが城址。
と言っても、何か上屋があったワケではないらしい。
戦となれば、ここに兵を集めて戦った、というモノなのだとか。
 すぐ近くにあった看板。
すぐ近くにあった看板。
しかし、実際にここで戦闘があったかどうかも、確たる証拠はなく、疑わしいようだ。
 そして、少し下ったところに、こんな看板が。
そして、少し下ったところに、こんな看板が。
 相変わらず、土塁が続いている。
相変わらず、土塁が続いている。
先ほどの城址を600mにわたって、取り巻いているんだとか。
 土塁から、下を覗いてみる。
土塁から、下を覗いてみる。
うわお!
中々の高さですな。
さらに下って・・・
 水場に至る。
水場に至る。
今年は台風の影響もあって、雨が多かったから、水量も多い。
この辺りは、沢などがなく、水の確保は切実だったようです。
 城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。
城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。
城址よりは、ずっと麓に近い場所です。
 今も周りに瓦が散乱しています。
今も周りに瓦が散乱しています。
後に持ち込まれたものも含むそうですが。
もう少し下の地点では、円面硯(えんめんけん)が出土し、市指定の文化財になっています。
さて、ざっと観てきました。
今回は、あくまでも自然観察がメインなので、城址関係は、ついでなので、あんまり詳しいレポートではありません。
他の方の記事を見ると、他にも遺構がありそうですが、自然の地形と見分けがつきません。
掲載した写真にも、誤りがあるかも知れません。
その際には、ご指摘下さい。
伝承によると、館岸城は・・・
「小山氏の乱」(1380~1397)の際、南朝に味方した小田藤綱は、難台山城に立て籠もった。
場所はこの辺↓
この際、上杉朝宗が率いる北朝側が築いたのが館岸城と言われる。
しかし、近年の専門家の調査によると、館岸城は一線防御・佐竹様式であることのことで、戦国末期の築城との見立てだ、とか。
少なくとも、戦国末期に手が加えられたことは間違いないようです。
地元の人々にとっては、ここは悲劇の場所であり、遠き南北朝の世に、思いを馳せる場所でもあります。
遺構があることで、その思いが、現実味をもって感じられたのではないでしょうか?
参考:笠間市HP
余湖くんのホームページ
春の夜の夢

今回、反時計回りで回ったワケですが、城址だけを目指すのであれば、逆回りの方が距離的には近そうです。
ただし、傾斜が半端なくきついので、お薦めできません。
また、道に迷うことが考えられますので、慣れている人と、一緒に行くことをお薦めします。
館岸山の頂上から、少し下ると・・・
 土塁が見えてきます。
土塁が見えてきます。 土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・
土塁に作られた、きつい階段を昇ると・・・ こんな看板が道々に立っています。
こんな看板が道々に立っています。「小山氏の乱」(1380~1397)の際の書状に、「朝日山御陣」とあるのが館岸城と推測されているので、「朝日城」と書かれているんでしょうね。
 空堀。
空堀。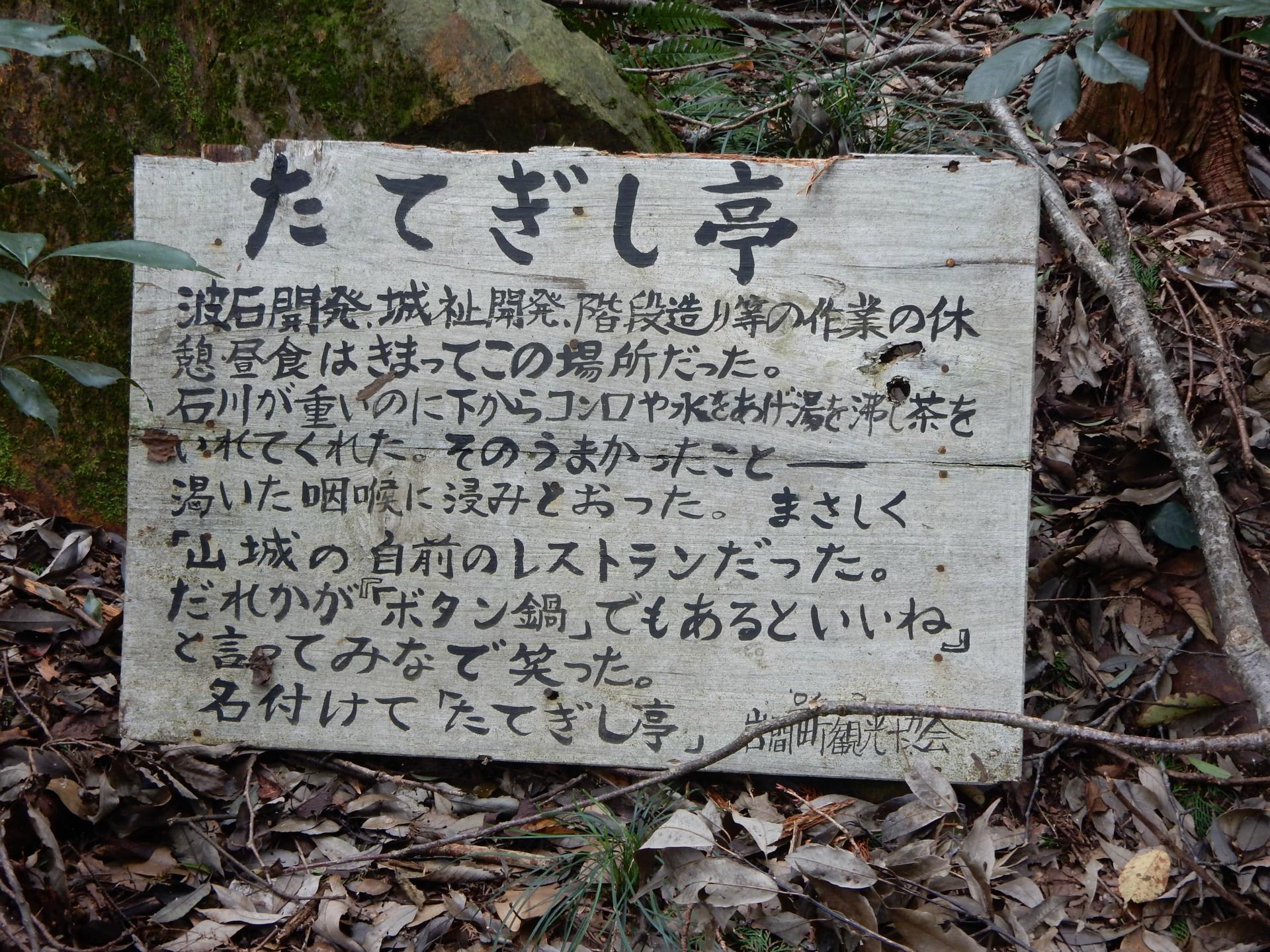 途中、城址開発の名残、
途中、城址開発の名残、 「たてぎし亭」を通り・・・
「たてぎし亭」を通り・・・ 「堀障子」に至る。
「堀障子」に至る。え?
「障子堀」じゃないの? って思ったんだけど。
後北条氏の城なんかに見られるものとは、ちょっと違うみたい。
「障子掘り」は、水堀の中に、障子の桟(さん)のような凹凸を設ける防御施設。
敵が堀を越えようとして、凹凸に足をとられている間に、弓矢などで攻撃する、というシロモノ。
 で、これが館岸城の「堀障子」。
で、これが館岸城の「堀障子」。 写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。
写真では凹凸がわかりづらいので、ちょっとラクガキしてみました。「低」の文字が堀底。
向こうの堀底との間に、一段、高くなった仕切りが設けられています。

んで、ここに何か、落ちてるんですよ。
 解説だった(笑)
解説だった(笑)(全文)
堀(濠)障子
地面を掘って水を通したものを堀という。
しかし、館岸城の場合、空堀(濠)である。
土塁と土塁の間に堀(濠)を造り、空堀の底は通路としている。
土塁は敵の浸入を防ぐ防禦敷設としたものであるが、
堀(濠)障子とは、土塁下の堀を敵が浸入して来た時に、堀障子の土壁に兵士が隠れて、敵を迎え撃った。
(攻めてくる敵を待ち受けて攻撃した。)
障子は和風建築の屏障具(へいしょうぐ)の総称であるが、その防禦壁を障子にたとえ、堀障子と称した。
・・なるほど、ここに兵が身を伏せて、敵を攻撃するワケですか。
空堀ならではの使い方ですな。
 土塁が続く。
土塁が続く。 そして・・・
そして・・・ ここが城址。
ここが城址。と言っても、何か上屋があったワケではないらしい。
戦となれば、ここに兵を集めて戦った、というモノなのだとか。
 すぐ近くにあった看板。
すぐ近くにあった看板。しかし、実際にここで戦闘があったかどうかも、確たる証拠はなく、疑わしいようだ。
 そして、少し下ったところに、こんな看板が。
そして、少し下ったところに、こんな看板が。 相変わらず、土塁が続いている。
相変わらず、土塁が続いている。先ほどの城址を600mにわたって、取り巻いているんだとか。
 土塁から、下を覗いてみる。
土塁から、下を覗いてみる。うわお!
中々の高さですな。
さらに下って・・・
 水場に至る。
水場に至る。今年は台風の影響もあって、雨が多かったから、水量も多い。
この辺りは、沢などがなく、水の確保は切実だったようです。
 城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。
城とは直接、関係ありませんが、西寺(にしでら)のあと。城址よりは、ずっと麓に近い場所です。
 今も周りに瓦が散乱しています。
今も周りに瓦が散乱しています。後に持ち込まれたものも含むそうですが。
もう少し下の地点では、円面硯(えんめんけん)が出土し、市指定の文化財になっています。
さて、ざっと観てきました。
今回は、あくまでも自然観察がメインなので、城址関係は、ついでなので、あんまり詳しいレポートではありません。
他の方の記事を見ると、他にも遺構がありそうですが、自然の地形と見分けがつきません。
掲載した写真にも、誤りがあるかも知れません。
その際には、ご指摘下さい。
伝承によると、館岸城は・・・
「小山氏の乱」(1380~1397)の際、南朝に味方した小田藤綱は、難台山城に立て籠もった。
場所はこの辺↓
この際、上杉朝宗が率いる北朝側が築いたのが館岸城と言われる。
しかし、近年の専門家の調査によると、館岸城は一線防御・佐竹様式であることのことで、戦国末期の築城との見立てだ、とか。
少なくとも、戦国末期に手が加えられたことは間違いないようです。
地元の人々にとっては、ここは悲劇の場所であり、遠き南北朝の世に、思いを馳せる場所でもあります。
遺構があることで、その思いが、現実味をもって感じられたのではないでしょうか?
参考:笠間市HP
余湖くんのホームページ
春の夜の夢




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます