下期にかけて、認知症関係の講座を開催する可能性があるので、認知症や高齢者ケアについて、にわか勉強中。
友達に勧められて、六車由美さんの『驚きの介護民俗学』医学書院を読んだ。
六車さんは、もともと民俗学の研究者で、フィールドワークもしていたが、大學の研究に疑問を感じて、故郷静岡の介護施設で働き始めた。
それまで認知症で徘徊するなど施設では「迷惑」な人として見られていた人でも、「教えて!」と、お話を聞こうとすると、それまで予想もしてなかったほど、饒舌に自分の人生を語り出すのに遭遇する。もちろん、断片的、繰り返しの多いなかからその人の人生を探り出すので、大変ではあるのだが、とても喜んでくれるのだという。
日経新聞の書評で「本書はさながら宮本常一『忘れられた日本人』の現代版」と書かれているがそんな感じだ。
***
その人が生きてきた時代の「空気感」のようなものは、なかなか残りにくい。
先日も、体操のお仲間で私より5~6才くらい上の方とおしゃべりをした折、早くに父親が亡くなり、ちょうど父親の実家に疎開して終戦となったため、母親は農業をし、彼女は近くの繊維工場に働きに出て、弟や妹を高校に行かせたと言われていた。「だから私は中卒なのよ」という。苦労だったとは思っていなかったようなのだが、知的好奇心を満たすため、図書館に行っては、片っ端から本を読んだとのことだ。
彼女のような人は多かったと思うが、馬鹿でも大学に入れる今の時代、こうした空気感を私もすっかり忘れていた。この空気感を思い出せるのも、せいぜい私の年代くらいまでだろう。
私も、男女雇用平等法が出来る前の女子行員で、寿退社までのお茶汲みが仕事だった時代に、職場環境に恵まれ、男性並みの仕事を得ていったのだが、そうした「空気感」は、後からの時代の人には、分からないだろうなぁと思う。
歴史上の人物が何をしたというような事実は、歴史となって残っていくのだろうが、市井の人々のその当時は当たり前だった生活の「空気感」の歴史を残すのは難しい。
***
その後、認知症講座関連の講座を開催した。永田久美子さん(認知症介護研究・研修東京センター研究部長)の講演「これからを楽に、楽しく-認知症に備え、よりよい日々を-」は、とても刺激的だった。
認知症になると、何も分からなくなる、何もできないと思いがちだが、認知症になっても、やりたいこと、やれることは、いろいろあるのだという。
ただ、叱られると萎縮し、不安、屈辱を感じ、自信喪失になる。気持ちを理解してもらえないと、暴力をふるったり、徘徊したりするが、これはある意味二次障害なのだそうだ。周りが良かれと思って考えたことが本人には、押し付けに思われがち。やりたいことを良く聞いてあげる、それを叶えてあげることが大事なのだそうだ。
最も目からうろこだったのは、いつも世話をされ、「有難う」ばかり言うのは嫌だということ。自分も、何かをやって喜ばれたいし、感謝されたいと思っている。だから、そういう機会を作るべきだという。地域によっては、「たまねぎの皮をむいてお小遣いをかせぐ」「防犯パトロール」「ご近所の掃除」といった簡単なことから、仕事をしてもらうようにしているところもあるという。
六車さんの「お話を聴かせてもらう」でもよいし、何か仕事をしてもらうでもよい。要は、尊厳のある人間として扱われるようにすることが何より大事ということだ。
***
そういえば、東日本大震災の被災地でも、いつまでも「可愛そう」「支援しましょう」とされるのは、有難迷惑と聞いたことがある。むしろ、「有難う」と言われたいのだと。
(この文章は、最初に書き始めてから、半年くらいして追加したものです。)










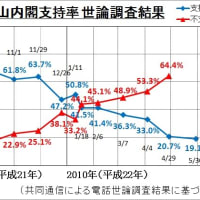
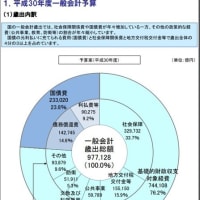
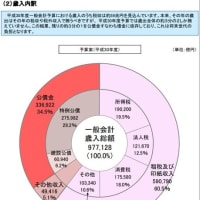
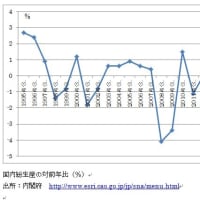
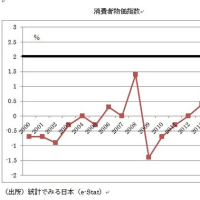



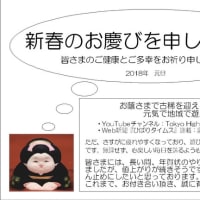


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます