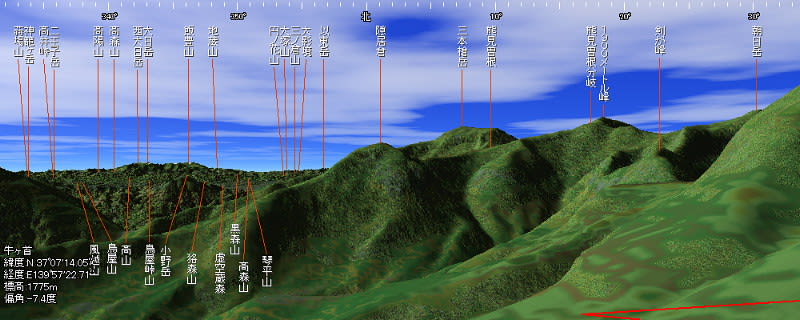笠間市佐白山公園の銀杏
あたり一面銀杏の葉とぎんなんが散らばっていた。

同じく佐白山公園の紅葉
人影も少なく午後の日差しが優しい城山である。
撮影中に巡り会った観光客に、何故笠間に赤穂の大石家の
跡が有るのか尋ねられた。
笠間藩は江戸時代にたびたび藩主が替わっているが、赤穂の
浅野家との関わりは、浅野長政の時代にさかのぼる。
豊臣秀吉の盟友であった長政は、最初は若狭国小浜8万石に
任じられ、後に甲斐国府中21万5千石に移封されて東国の
太閤検地などを行う
関ヶ原の時に家康の味方をして、長男幸長に戦功があり
紀伊国和歌山37万石に移封される。
関ヶ原後、長政に常陸国真壁5万石を隠居料として与えられる
長政の死後、三男長重が真岡藩2万石から真壁藩5万石の藩主と
なり跡を継ぐ。(長重はこのとき真岡藩を返上している)
のちに笠間藩に移封され、真壁藩は廃藩となり笠間藩に併合される
この長重が真岡藩の頃、浪人していた大石良勝を小姓として雇った
のが浅野家の家老大石の始まりである。
長重と共に関ヶ原で武功が有った為、大石良勝は1500石を賜り
永代家老の家柄となったのである。
付け加えると長重の子、長直の時に播磨の国赤穂に転封になった
のが赤穂藩の始まりである。
このような事情で、真壁の天目山伝正寺にも浅野家の墓所があり
笠間の佐白山公園近くに大石家の邸宅跡がある
赤穂事件の時の藩主長矩は、初代藩主長直の孫である
また家老大石良雄は、大石良勝の孫に当たる。
また長政の長男幸長に嫡子が無かったため、幸長の死後
長政の次男長晟が備中国足守藩から移って和歌山藩の跡を継いだが
後に安芸国広島藩に加増転封となり、幕末まで続いだ
======================================================
以下 おまけ画像 (笑)

月待の滝、滝の裏側から撮影、恨みの滝ではない「裏見の滝」だよ

同じく月待の滝にて撮影した紅葉、(墓地の脇)

同上
何故「月待の滝」と呼ばれるかはこちらをご覧ください。