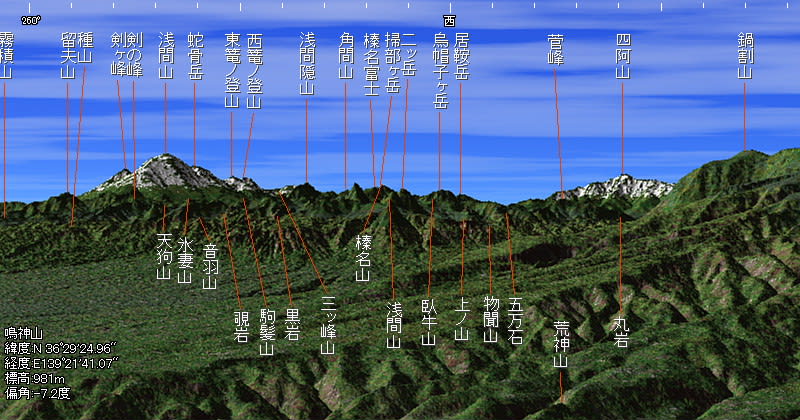レブンアツモリソウ・ラン科アツモリソウ属
北海道の礼文島の特産種、アツモリソウに似るが
花色は淡黄色。
側花弁は卵形で先は短く尖る。花期は6月
現在、茨城県自然博物館では、第54回企画展「植物たちのSOS
-レッドデータブックからの警告-」を開催していますが
その一環として、北大植物園からお借りした「礼文アツモリソウ」が
公開されました。
19時間の長旅で空輸されたレブンアツモリソウ、おそらく
本州で公開されるのは初めてではないでしょうか。
自生の礼文アツモリソウは、礼文島でしか見ることが出ない
貴重な花です。
この機会に是非見て欲しいと思います。
開花した花が昨日から公開されてますが、見頃は今週末までと
思われます。
受付で写真撮影が可能か確かめましたら、撮影しても良いと許可を
得ました。
但し、三脚の使用は遠慮して欲しいとの事です。
(それは、他のお客様のじゃまになるためと思われます)

実際の展示品はガラスケースに入っています

この日は全株展示されてましたが、数日で展示する株は
減らすそうです。
===========================================================
同時に展示されているアツモリソウ属の花を紹介します。

アツモリソウ・ラン科アツモリソウ属
花の形を平敦盛の母衣に見立てた名前
山地の草原などに生える。
茎は高さ20~40センチ、葉と共に毛が有る
花は淡紅紫色で直径が3~5センチ
唇弁は袋状。花期5~7月

アツモリソウは、茨城県では絶滅した。

チョウセンキバナアツモリソウ・ラン科アツモリソウ属
自生している数が数十株という絶滅寸前の花
自生地は秋田県地方のみ
草丈は20センチくらい、花の色は白に赤い斑が入る

この花も北大植物園から借りたもので
展示が終われば北大に返される。
見るなら今の内だよ。

後ろ姿を拝見、握り拳を広げたような形が可愛い
===============================================
自然博物館の野外を歩いていたら、池の畔でこんな花を
見つけました

近寄りたいけど近寄れない場所なので、これが精一杯

もしかするとこれってコウホネ?
花期は6月だったような
=================================================
本日のお買い物

今回の絶滅危惧種の展示解説書 売店で600円

これも今回の企画展の記念グッツのストラップ
これはミヤマスカシユリのデザイン 売店で350円
他に2種類有ったが、これが気に入った
解説書とストラップを買っても、千円でおつりが来るよ
おすすめ!!
6月2日からは、筑波実験植物園でも絶滅危惧種の
イベントが開かれます
このブログのブックマークにそれぞれのリンクがあります
ご利用ください。