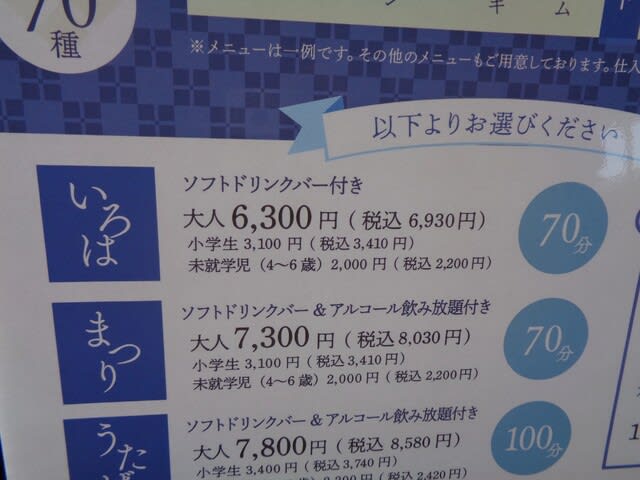野党と与党の一部によって
「選択的夫婦別姓」の法案が国会に提出されようとしている。
日本においては、現在、民法750条で夫婦の同氏が規定されており、
戸籍法第74条で、夫婦が称する氏を記載して届けることになっている。
国際結婚の場合を除き、
婚姻を望む当事者のいずれか一方が
氏を変えない限り法律婚は認められていない。
夫婦、子供を含む家族は同姓であるべきだというのが基本だ。
それに対して、法律を改正して、
結婚後も夫婦が別姓であることを可能にする制度を、
「選択的夫婦別姓」(又は「選択的夫婦別氏」) と呼ぶ。
どうして夫婦を別姓にする必要性があるかというと、
結婚して名字を変えると
会社等でいろいろ不都合が生ずるというのが最初だった。
続いて、
姓を変えることが強制されると、
アイデンティティ喪失、間接差別、精神的な負担などと話を拡大。
訴訟も起きている。
憲法違反だというのである。
夫婦を同姓とする法規定が違憲かどうか争われた訴訟では、
最高裁大法廷は、
平成27年、
「夫婦や子供が同じ姓を名乗ることには合理性がある」と判断し、
「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、
その呼称を一つにするのは合理的」と続けており、
この判例は令和3年の大法廷決定でも維持された。
妥当な判決だろう。

「時代の要請」だという意見もある。
現在法的に夫婦同氏が規定されているのは
世界で日本だけであるので、
時代遅れだというのである。
だが、何も諸外国に合わせる必要はない。
日本には、世界に冠たる戸籍制度があり、
一つの家族が同じ姓を名乗ることで
社会の最小単位、「家族」を中心とした社会が出来ている。
戸籍は「家族の一体性」と「家名・家系の一系性」を表す。
夫婦別姓・家族別姓は、
我が国が長年維持してきた戸籍制度の解体につながる。
つまり、夫婦別姓の問題は、
日本の社会の在り方に関わる重大な問題なのである。
便利か不便かという問題ではない。
「選択的夫婦別姓」の「選択的」が隠れ蓑で、
結婚する時、同姓にするか別姓にするかを
選択できるから、
選択肢が多い方がいいという、
多様性への対応だという。
しかし、その「選択」は夫婦によるものでしかなく、
子供にとっては「選択制」ではなく、「強制的」だ。
夫婦の姓が異なる場合、
子供が生まれたらどうするか。
どちらの姓を名乗ったらいいのか。
兄は鈴木姓、弟は山田姓などという事態も起こる。
同じ家に住む同じ家族でありながら、
姓が異なる。
しかも、どちらの姓を選ぶかは
生まれたばかりの子どもは関与できない。
つまり、「強制的親子別姓」なのだ。
そう考えると、
「選択的夫婦別姓」の呼称も、
「選択的夫婦別姓・家族別姓」と改めたら、
問題はもっとはっきりするだろう。
夫婦別姓を唱える人々の思考が足りないと思われるのは、
子供の姓の問題に考えが至っていない点だ。
子供の姓はどうなるのか。
提出予定の法案では、
「出生の際に父母の協議で定める」のだという。
では、どちらの姓を子供につけるかで
夫婦が争った場合はどうする。
その時は、
「家庭裁判所は、
父又は母の請求によって、
協議に代わる審判をすることができる」
としている。
はて、家庭裁判所はどのような基準で判断するのか。
離婚の場合の親権では、
親の経済力などが判断の材料となるが、
姓の場合では、何を材料とするのか。
委ねられた家庭裁判所は困るだろう。
更に、その審判に不服の場合はどうするのか。
裁判が長引いた場合、
子供の姓の届け出はどうするのか。
この問題は、夫婦だけではすまない。
孫の名字をめぐって
双方の祖父母が争いになる可能性もある。
本来幸せな出産直後に、
子の姓を巡って親族間で争いが起こるのだ。
なにより、この問題について、
子供の意思は全く反映されない。
「選択的」というが、
選択できるのは誰か。
生まれてくる子供にとっては
親の意向で強制的に「親子別姓」「家族別姓」となる。
ファミリーネームが喪失するという事態を
「選択者」である親は一体どこまで想定しているのか。
子供の問題一つ取っても、
選択性夫婦別姓は暗礁に乗り上げ、
新たな問題を生ずると分かるだろう。
世論も賛成・反対半々で、
まだ国民的合意があるわけではない。
そんな段階で、
今まで守ってきた制度を変えることが良いことなのか。
不便に対する解決策として、姓は従来通り一つで、
通称使用という案がある。
あるどころか、既に実施されている。
旧姓をそのまま使用することは大部分の企業で認められ、
会社勤めの人が呼称を変更することの不便さは改善されている。
住民票やマイナンバーカードで旧姓併記が可能。
旧姓での各種契約や本人確認も可能になっている。
免許証や銀行口座も旧姓で作ることが可能だ。
パスポートも旧姓併記が認められている。
これで十分で、
わざわざ夫婦別姓を導入して、
あらたな火種を起こすことはないのだ。
内閣府が令和4年3月に発表した世論調査では、
「別姓導入」は28.9%、
「現状維持」が27%、
「旧姓使用の法整備」が42.2%。
つまり、導入に否定的な回答が71.1%だ。
それなのに、
なぜ導入を無理やりしようとするのか。
ごく最近の産経新聞の小中学生に対する調査で、
「新しい法律で家族が違う名字になる」ことに対して
「反対」が49.4%、
「賛成」が16.4%、
「親が決めたのなら仕方ないので賛成」が18.8%。
続いて、
「法律が変わった場合、将来自分が別姓を選択するか」については、
「家族で同じ名字がよいので別々にはしたくない」が59.9%、
「自分の名字を大切にしたいので、別々にしたい」が13.6%。
維新の吉村氏は、
「同一戸籍・同一氏の原則を維持し、
旧姓に法的拘束力を認めるやり方が現実的だ」
と語っているが、
それこそ現実的対処というものだろう。
導入に熱心な立憲民主党の野田佳彦代表は、
子供の姓の選択に関しては
「家族で決めればいいことで、
政府が決めることではない。
そういうことも含めて選択的であるべきだ」
という。
ここで「政府」を持ち出して反感を募らせようとしている。
政府が決めるのではない。
国の在り方が問われているのだ。
野田さんは立派な政治家だとは思うが、
野田さんともあろうお方が、
なぜこの問題に対しては血迷っているのか。
産経新聞がインタビューをしているが、
この問題の含む体質が現れている。
選択的夫婦別姓の意義は
「選べるという点ではないか。
同姓で不都合を感じる人がいるならば選択できるようにする、
改善するのは合理的な考え方ではないか。
それだけのことだ」
と軽い。
ことは国の在り方にまで拡大するまで思考が至っていない。
小中学生約2千人を対象に行った本紙調査で、
両親が別姓を選択した場合、
同じ家族で名字が別になることに「反対」が49.4%、
「賛成」が16.4%だった
と知ると、
「賛成が16.4%いるのでしょう?」
と言ってのけた。
もし、「反対」が16.4%だったら、
「反対は16.4%しかいないじゃないか」
と言っただろう。
これは、選挙結果が自分の思い通りになると「民意が表れた」と言い、
選挙結果が自分の思い通りにならなかった時には、
「民意と乖離している」と言うのと同じだ。
そして、
「なぜそこまで強く反対する人たちがいるのか。
よく分からない」
と言う。
ここに左翼的な体質がよく表れている。
自分の信条が正しいという視点からの物言いだ。
選択的夫婦別姓の法制化を望む人たちに
「国民の70%が賛成」という声があるが、
その根拠は2択のアンケートだ。
「旧姓使用の拡大」を法的に整備するという選択肢は
このアンケート当時はなかった。
3択を加えた令和3年12月の内閣府の世論調査では
「同姓維持」27%、
「別姓導入」28.9%、
「旧姓使用拡大」42.2%、という結果になった。
産経・FNN 合同世論調査も以前は
2択で賛成66.6%、反対25.5%だったが、
昨年9月に3択目を加えたところ、
賛成38.9%、反対12%、旧姓使用拡大46.5%と大きく変わった。
なのに、野党と与党の一部は、
遮二無二法案を通過させようとする。
もし自民党の一部が通過に加担したら、
今度こそ自民党岩盤支持層は
完全に自民党を見放すだろう。
共産党の田村智子委員長は選択的夫婦別姓の導入に
「もう実現するしかない」と強い意欲を示し、
「ジェンダー平等を進めていく上で不可欠だ。
国会の中での議論を求めたい」
と、はやりのジェンダー平等まで持ち出している。
やはり「多様性」の問題だ。
私はこのブログで、
「日本を弱くしたいメンタリティーの人々」のことを度々書いたが、
これもその一つではないかと思う。
日本の社会が長年培ってきた「家族」という、麗しい最小単位を
バラバラにして、日本の良さを崩壊させようとする、
その動きの一つではないのかと思えてならない。