福見教会は現在、浜串小教区の巡回教会だが、本家浜串教会より有名かとおもわれる。
福見(ふくみ)天主堂
大正2年(1913)4月29日献堂式


旅行ガイドなどに載っている写真はこんな感じだろうか。

僕がブログで新上五島町の教会群を紹介するにあたり、困ってしまったのがここ福見。資料ごとに教会を建てた年代が違うのだ。
この看板が正解なのだろうか。
福見のキリシタンがカトリックに帰依したのは明治11年(1878)。ある資料によると明治11年4月10日に最初の教会建設とあるが、設立の間違いかと思われる。(元々教会とは共同体を意味し、建物の事ではなかった。)
また、明治36年3月25日大改築と記された資料もある。

前側はレンガだが、

後ろ側はコンクリートに赤いペンキを塗っただけ。

レンガ造りの教会には珍しい折上天井だが、

オリジナルはコウモリ天井だったというのが、専門家の大方の見解。
とにかく謎の多い天主堂なのだ。

テレビの時代劇で、「おぬしも悪(わる)よのー」と悪代官がよく登場するが、五島列島にも悪代官はいたようである。

弾圧時代、福見を仕切っていた代官は地下者(ジゲモン-先住民)と結託し
「明日、パッタリン(キリシタンの事)を捕らえに役人がやってくるから逃げたほうがいい」
と、デマを流した。

拷問の凄まじさを伝え聞いていた福見のキリシタン達は、慌てふためき着の身着のまま時化た海へ舟を漕ぎ出した。

ジゲモン達はもぬけの殻になったキリシタンの家屋、農耕器具、牛、田畑全てを強奪し、代官は彼等から賄賂を受け取った。

旧若松町と旧奈良尾町のキリシタンへの拷問、弾圧、差別は凄まじく、あまりの酷さに耐えかねて神道祭(しんとうさい)に改宗した者が多いが、
福見のキリシタン達は、デウスやサンタマリアを捨てられない理由が出来てしまった。
時化た海へ舟を出したキリシタン達は転覆遭難し、行方不明者多数。

犠牲になった同胞の為に、祈りを捧げなければ・・・。
人気blogランキングへ⇒ ![]()

新上五島町(長崎県)の教会





















福見天主堂 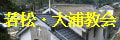


 鯛ノ浦天主堂
鯛ノ浦天主堂

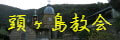
廃墟になった教会














