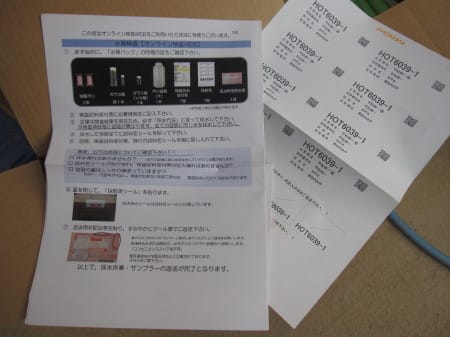ちょっとマニアックな実験に走っているので、根を快適に・・・の冠をはずしました(笑
前回とちょっと話は逸れますが同じ時期、気になっている事が他にもありました。
それは、冷水を循環させているラジエターの循環水のことでした。
昨年は井戸を掘ったばかりで、どういう風に水耕栽培の養液を冷やしていくか決めてなかったので、とりあえず実験的に色んな事をしていました。
その中でも、
1、各養液漕にラジエターを配置してホースで接続し、汲んだ井戸水を直接ポンプで循環させる。
2、全く反対に、養液をポンプでラジエター内を循環させ、その行程内に井戸水を汲み上げたタンクで冷やす。
の二つがホントにみるみるうちに温度が下がります。
5℃ 6℃は一気です。(笑
ただ、この頃は今年の今と同じように、非常にカナケがきつく、水質検査もしてませんでしたので、この水に一体何が混ざっているかも解らない恐ろしい状況でした。
よって、ラジエターの漏水試験、ホースの接続には細心の注意を払い、何回も試験をした後、使用すると言う事を繰り返してました。
上の冷却方法での問題点として
1の方法
何日か井戸水を循環させていると、ラジエターとホース内に溢れるほどの錆が溜まり、掃除が大変です。
おまけに、溶解している物によってはラジエターを腐食させかねません。
2の方法
水耕栽培をされている方は知っていると思いますが、栽培していると養液の中に根の老廃物などのゴミが混ざります。
あと、温度変化に弱い養液中の物質(特にカルシウムなど)がこの冷やされるラジエターやホースに付着して、ヌルヌルの被膜を作ります。
こういった物が、パイプ内に沢山付着する事になります。
そしてなんといっても試験しているとはいえ、養液と井戸水が隣同士で居る事が精神衛生上よくない!(笑
そういう事を踏まえ、今年はその辺の問題を解消する為に冷却効率はグッと下がりますが、養液と井戸水の間に真水をカマす方法でやる事にしました。
※参考・・・
根を快適にしてあげたい!2014 配管編
さて、以上の事を踏まえての話です。
ある日のメンテ

前回の記事と同じ7月4日撮影
ラジエターに繋いでいるホースは安物を使っていた為、中が見えます。
これはこれで良いのですが、少し経つと藻が繁殖してきます。
定期的に水を交換、ホースを掃除します。
いつもそんな時、頭をよぎる不安・・

上のラジエター画像で解るように、ラジエターにはバイクと接続するセンサーやホースと接続するような不安定な接続部分があります。

おまけに、これはあくまでバイク用のラジエター、ホースの規格が一般の水やりホースとは規格が合いません。
この画像の接続部分は内径25mmのホースをホットガンで伸ばして、無理矢理接続してます。
ただ、その分しっかり噛み込んではいます。
あと、止水と抜け防止の為のホースバンドは、ワンシーズンで養液と井戸水の酸で溶けて無くなるくらい腐食します。
もしかしたら、ここから井戸水が混入しないとは言い切れません。
綺麗な水の頃はあまり気にも止めませんでしたが、この季節のカナケが沢山混じった水の頃は非常に気になります。
ということで
精神衛生向上作戦開始です(笑