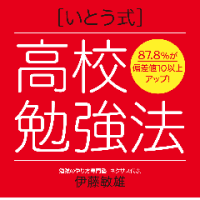自由進度学習は「ただの自学自習」じゃないです。
こう一言で言うのは簡単だけど、このニュアンスを伝えるのは容易ではない。
特に学校の先生に対しては、、、。
これが塾の先生なら一言でわかってもらえる。
なぜかというと、
教えるということが何なのかよくわかっているから。
とはいえ、少なからず学校の先生の中にもそういう方はいるようです。
風越学園という、高い理念を掲げた学校があるのですが、
こちらの学校の先生ですら、自由進度学習の難しさを語っています。
■自由進度学習をやめてみて、何を始めようか(佐々木 陽平 2023年1月25日)
https://kazakoshi.ed.jp/kazenote/now/27929/
僕が2022年4月にここにきたとき、子どもたちは開校1年目にはAIドリル、2年目には教科書や問題集に基づいた自由進度学習を経験してきていた。僕はAIドリル、教科書や問題集に基づいた学習では、数学の知識及び技能を習得したり、その知識及び技能を習得する方法について学ぶことはできるだろうけど、数学的にものを深く考えることについては学べないと考えている(略)。
確かに、ただの知識技能なら、自学形式でも身につくでしょう。
でも実際はそんな単純な話じゃないんです。
まずはその学習スタイルを変えたいと思ったが、それを変えるには少なくとも、思考を表現するような学習パッケージ(子どもたちが取り組むプリントのセット)をつくる必要がある(中略)。7年生については僕がえいやっと勢いで学習パッケージに基づいた自由進度学習を進める場をつくり、8年生・9年生についてはこれまで通り教科書や問題集に基づいた自由進度学習を進める場をつくった。
学習パッケージは、全員が期間内に終えてほしい基礎編と進んでいる子がやってもいい発展編に分けて作った。しかし、やってみると予め決めた期間に基礎編が終わらない子どもたちが続出した(略)。
この先生は、子どもたちの学習の進み具合をよく見ていると思います。
自由進度学習でなくたって問題に対して何を考えているかということはわかりにくいが、自由進度学習だと子どもが向き合っている問題が一人一人違うので、どこに躓いているのかどこで何を考えているのか、どんな方法でアプローチしているのかがより一層捉えづらく、僕の頭では追い切れないのである。
そう、そうなりますよね。
つまり、一斉授業より大変なんですよ。
子どもたちが問題について考えていることや今ここで起きていることがわからないと、授業を改善することもできない。授業をうまくつくっていくための情報が得られないのである(中略)。この学習パッケージを使った自由進度学習では、それができない。
教える側は、常に教わる側(生徒)の理解度などから指導法を微調整するものなのです。
だから、自由進度学習に限らず、子どもたちに学習が成立しているか、指導者は常にチェックしなければいけません。
そう思って、自由進度学習をやめてみることにした。そして、2つのことを始めてみた。何を始めたかというと、1つは計算技能の反復練習である。数学の問題を考えるために必要な計算技能を習得するために、毎時間の最初に10分間の計算練習の時間を取ることにした。もう1つは、1時間に1問だけ考える問題を提示して、それを子どもたちなりに考える場をつくった。子どもたちが自分たちの判断で友だちと話し合い、道具を用いながら問題を考える場である。
最終的にはこういうことになるでしょう。
つまり、教師がきちんと教えるべきことは教え、最低限の知識・技能を身につけさせること。
その上で、子どもたちに考えさせたり判断させたりする。
こうすることで学習者(子ども)は学び方というスキルを身につけることができるからです。
ロールプレイングゲームで言えば、
普通は、武器や防具をそろえてからフィールドに出ますよね。
こうした方が、これから先、
強敵(=高校受験を迎えたり高校へ進学したりしても)に出会っても負けない強さを身につけることできるからです。
(風越学園はそれをねらっているわけではないですが)
しかし、今、ちまたで流行っている自由進度学習は
武器も防具も持たせずに、子どもをフィールドに放り出すようなものです。
一見、自由度が高く、子どもの主体性に任せる素晴らしい教育に思えますが、
冷静になって考えてみるとこれほど残酷な教育はありません。
確かに、最初の頃の弱いモンスター相手ならそこそこ健闘できるでしょう。
しかし、相手が強くなったとたん、太刀打ちできなくなるのは明らかです。
それではただの我流でやる勉強と変わりません。
教育ってそういうものじゃないはずですよね。
7年生の授業の取り組みを経て、8年生と9年生も一度自由進度学習をやめ「考える場」をつくりはじめた。それぞれ深く考える姿が少しずつ見えてきている。
私はこの先生に会ったこともありませんし、
今、どのような授業をやっているかは正直わかりませんが、
少なくとも
・子どもたちの様子
から、自分の指導の仕方に課題を見つけ、
大幅修正したり微調整をしたりしながら
授業を改善している点には大変共感できます。
本来、教えるとはこういうことだからです。
みなさんの学校の先生はどうでしょうか?
ここまで深く考えて、自由進度学習に切り換えた先生がどれだけいますか?
■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓
勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)
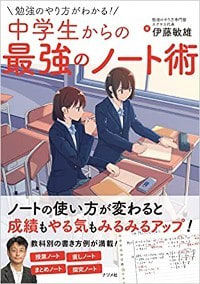
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます
こう一言で言うのは簡単だけど、このニュアンスを伝えるのは容易ではない。
特に学校の先生に対しては、、、。
これが塾の先生なら一言でわかってもらえる。
なぜかというと、
教えるということが何なのかよくわかっているから。
とはいえ、少なからず学校の先生の中にもそういう方はいるようです。
風越学園という、高い理念を掲げた学校があるのですが、
こちらの学校の先生ですら、自由進度学習の難しさを語っています。
■自由進度学習をやめてみて、何を始めようか(佐々木 陽平 2023年1月25日)
https://kazakoshi.ed.jp/kazenote/now/27929/
僕が2022年4月にここにきたとき、子どもたちは開校1年目にはAIドリル、2年目には教科書や問題集に基づいた自由進度学習を経験してきていた。僕はAIドリル、教科書や問題集に基づいた学習では、数学の知識及び技能を習得したり、その知識及び技能を習得する方法について学ぶことはできるだろうけど、数学的にものを深く考えることについては学べないと考えている(略)。
確かに、ただの知識技能なら、自学形式でも身につくでしょう。
でも実際はそんな単純な話じゃないんです。
まずはその学習スタイルを変えたいと思ったが、それを変えるには少なくとも、思考を表現するような学習パッケージ(子どもたちが取り組むプリントのセット)をつくる必要がある(中略)。7年生については僕がえいやっと勢いで学習パッケージに基づいた自由進度学習を進める場をつくり、8年生・9年生についてはこれまで通り教科書や問題集に基づいた自由進度学習を進める場をつくった。
学習パッケージは、全員が期間内に終えてほしい基礎編と進んでいる子がやってもいい発展編に分けて作った。しかし、やってみると予め決めた期間に基礎編が終わらない子どもたちが続出した(略)。
この先生は、子どもたちの学習の進み具合をよく見ていると思います。
自由進度学習でなくたって問題に対して何を考えているかということはわかりにくいが、自由進度学習だと子どもが向き合っている問題が一人一人違うので、どこに躓いているのかどこで何を考えているのか、どんな方法でアプローチしているのかがより一層捉えづらく、僕の頭では追い切れないのである。
そう、そうなりますよね。
つまり、一斉授業より大変なんですよ。
子どもたちが問題について考えていることや今ここで起きていることがわからないと、授業を改善することもできない。授業をうまくつくっていくための情報が得られないのである(中略)。この学習パッケージを使った自由進度学習では、それができない。
教える側は、常に教わる側(生徒)の理解度などから指導法を微調整するものなのです。
だから、自由進度学習に限らず、子どもたちに学習が成立しているか、指導者は常にチェックしなければいけません。
そう思って、自由進度学習をやめてみることにした。そして、2つのことを始めてみた。何を始めたかというと、1つは計算技能の反復練習である。数学の問題を考えるために必要な計算技能を習得するために、毎時間の最初に10分間の計算練習の時間を取ることにした。もう1つは、1時間に1問だけ考える問題を提示して、それを子どもたちなりに考える場をつくった。子どもたちが自分たちの判断で友だちと話し合い、道具を用いながら問題を考える場である。
最終的にはこういうことになるでしょう。
つまり、教師がきちんと教えるべきことは教え、最低限の知識・技能を身につけさせること。
その上で、子どもたちに考えさせたり判断させたりする。
こうすることで学習者(子ども)は学び方というスキルを身につけることができるからです。
ロールプレイングゲームで言えば、
普通は、武器や防具をそろえてからフィールドに出ますよね。
こうした方が、これから先、
強敵(=高校受験を迎えたり高校へ進学したりしても)に出会っても負けない強さを身につけることできるからです。
(風越学園はそれをねらっているわけではないですが)
しかし、今、ちまたで流行っている自由進度学習は
武器も防具も持たせずに、子どもをフィールドに放り出すようなものです。
一見、自由度が高く、子どもの主体性に任せる素晴らしい教育に思えますが、
冷静になって考えてみるとこれほど残酷な教育はありません。
確かに、最初の頃の弱いモンスター相手ならそこそこ健闘できるでしょう。
しかし、相手が強くなったとたん、太刀打ちできなくなるのは明らかです。
それではただの我流でやる勉強と変わりません。
教育ってそういうものじゃないはずですよね。
7年生の授業の取り組みを経て、8年生と9年生も一度自由進度学習をやめ「考える場」をつくりはじめた。それぞれ深く考える姿が少しずつ見えてきている。
私はこの先生に会ったこともありませんし、
今、どのような授業をやっているかは正直わかりませんが、
少なくとも
・子どもたちの様子
から、自分の指導の仕方に課題を見つけ、
大幅修正したり微調整をしたりしながら
授業を改善している点には大変共感できます。
本来、教えるとはこういうことだからです。
みなさんの学校の先生はどうでしょうか?
ここまで深く考えて、自由進度学習に切り換えた先生がどれだけいますか?
■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓
勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)
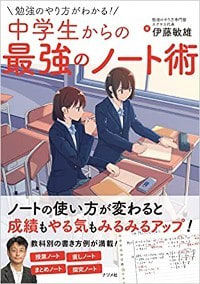
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます