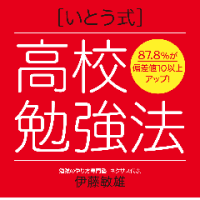今日は国語特講の2回目
国語の読解問題でよく問われるのが、言いかえ(例示)、対比、因果です。

それを記号で表すと
「=」言いかえ(例示)
「⇔」対比
「⇆」因果
*機種依存文字の場合は見られません
ってなるなって、ふと思いました。
論理もだいたいこの3つに集約されます。
っで、
今日の特講は、この3つを意識して問題を解いてもらいました(正確には今日「も」ですが)。
題材は、「ひこにゃん」や「うどん県」の生みの親、
殿村美樹「ブームをつくる 人がみずから動く仕組み」から。
数学でもそうなのですが、
国語でも
A→B
は正しくても
逆:B→A
は必ずしも正しくありません。
例えば、
A:現代のブランドの価値に必要なのは、本物のストーリーにある「信頼」である
B:本物のストーリーにある「信頼」は、現代のブランド価値に必要である
この2つの文章、全く同じに見えますがそうではありません。
本文では、
現代のブランド価値に必要なのは「信頼」と「共感」の2つである
といった主旨が述べられています。
そういう意味では、AもBも説明としては不十分かもしれません。
しかし、この2つが選択肢にあった場合は話は別です。
まず、
A:現代のブランドの価値に必要なのは、本物のストーリーにある「信頼」である・・・△
だと、もう一つの条件である「共感」が含まれないので、少なくとも「正」とは言えません。
一方、
B:本物のストーリーにある「信頼」は、現代のブランド価値に必要である・・・○
は、こちらも内容的には十分ではないですが、論理的には間違っていないので、「誤」とするわけにはいきません。
もう一つ、このような正誤判断問題の選択肢でこんなのがあります。
A:企業は商品の世界観を伝えるため動画を作成する。このような消費形態を「物語消費」と言う。
(改編して引用:ルールズ現代文)
このような書き方になっていると、本文の内容につられて多くの受験生が「正」とまちがえてしまいます。
細部を読まず、なんとなく雰囲気で読んでいるからです。
「たぶん正しい」
と
「正しい」
とでは、雲泥の差があります。
内容的には、一見「正しい」ように見えますが、
実は日本語がおかしいってことに気がつきましたか?
「物語消費」は消費なので、主語は消費者です。
ところが、この選択肢では、
動画を作成する主体は企業なのに、2文目では「このような消費形態」となっています。
これだと、消費形態の「消費」が何を指しているのかわかりません。
「動画を作成する=消費」ではないからです。
国語の問題をなんとなーく読んでいる子は、こういうトリッキーな書き方に見事にひっかかります。
国語の論説文では、「言いかえ」がほとんどと言っても過言ではありません。
本文中では間違った言いかえは「ない」のですが、
選択肢中には、このような「誤答に導くための言いかえ」が巧妙にちりばめられています。
国語で点数が伸びない子は、十中八九
このようななんとなく読みをしています。
では、どういう風に言いかえられていたら正解なのか。
例えば、
B:企業は商品の世界観を伝える動画を作成することで「物語消費」を促している。
とあるなら、これは「正」でしょう。
まあ、それが国語力なのか?って異論はありますが、
少なくとも「正しく読めている」かどうかの判定はできます。
国語の読解問題で点数を伸ばすには、こういう「正しく読む」という練習が必要です。
ただ、残念ながら学校では教えてもらえないですね。
■↓高校生のテスト勉強の仕方は↓
87.8%が偏差値10以上アップ! [いとう式]高校勉強法(大和出版)
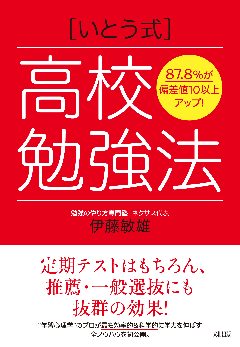
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます
国語の読解問題でよく問われるのが、言いかえ(例示)、対比、因果です。

それを記号で表すと
「=」言いかえ(例示)
「⇔」対比
「⇆」因果
*機種依存文字の場合は見られません
ってなるなって、ふと思いました。
論理もだいたいこの3つに集約されます。
っで、
今日の特講は、この3つを意識して問題を解いてもらいました(正確には今日「も」ですが)。
題材は、「ひこにゃん」や「うどん県」の生みの親、
殿村美樹「ブームをつくる 人がみずから動く仕組み」から。
数学でもそうなのですが、
国語でも
A→B
は正しくても
逆:B→A
は必ずしも正しくありません。
例えば、
A:現代のブランドの価値に必要なのは、本物のストーリーにある「信頼」である
B:本物のストーリーにある「信頼」は、現代のブランド価値に必要である
この2つの文章、全く同じに見えますがそうではありません。
本文では、
現代のブランド価値に必要なのは「信頼」と「共感」の2つである
といった主旨が述べられています。
そういう意味では、AもBも説明としては不十分かもしれません。
しかし、この2つが選択肢にあった場合は話は別です。
まず、
A:現代のブランドの価値に必要なのは、本物のストーリーにある「信頼」である・・・△
だと、もう一つの条件である「共感」が含まれないので、少なくとも「正」とは言えません。
一方、
B:本物のストーリーにある「信頼」は、現代のブランド価値に必要である・・・○
は、こちらも内容的には十分ではないですが、論理的には間違っていないので、「誤」とするわけにはいきません。
もう一つ、このような正誤判断問題の選択肢でこんなのがあります。
A:企業は商品の世界観を伝えるため動画を作成する。このような消費形態を「物語消費」と言う。
(改編して引用:ルールズ現代文)
このような書き方になっていると、本文の内容につられて多くの受験生が「正」とまちがえてしまいます。
細部を読まず、なんとなく雰囲気で読んでいるからです。
「たぶん正しい」
と
「正しい」
とでは、雲泥の差があります。
内容的には、一見「正しい」ように見えますが、
実は日本語がおかしいってことに気がつきましたか?
「物語消費」は消費なので、主語は消費者です。
ところが、この選択肢では、
動画を作成する主体は企業なのに、2文目では「このような消費形態」となっています。
これだと、消費形態の「消費」が何を指しているのかわかりません。
「動画を作成する=消費」ではないからです。
国語の問題をなんとなーく読んでいる子は、こういうトリッキーな書き方に見事にひっかかります。
国語の論説文では、「言いかえ」がほとんどと言っても過言ではありません。
本文中では間違った言いかえは「ない」のですが、
選択肢中には、このような「誤答に導くための言いかえ」が巧妙にちりばめられています。
国語で点数が伸びない子は、十中八九
このようななんとなく読みをしています。
では、どういう風に言いかえられていたら正解なのか。
例えば、
B:企業は商品の世界観を伝える動画を作成することで「物語消費」を促している。
とあるなら、これは「正」でしょう。
まあ、それが国語力なのか?って異論はありますが、
少なくとも「正しく読めている」かどうかの判定はできます。
国語の読解問題で点数を伸ばすには、こういう「正しく読む」という練習が必要です。
ただ、残念ながら学校では教えてもらえないですね。
■↓高校生のテスト勉強の仕方は↓
87.8%が偏差値10以上アップ! [いとう式]高校勉強法(大和出版)
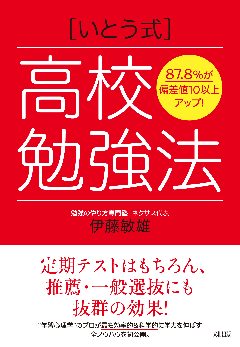
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます