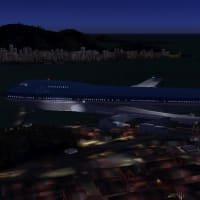常々思うけど、因果という物は廻ってくるものだ。
時間が立つと悪い行いが、よい行いになったり...
その逆もある。
日常でも、長く生きていると、気がつくことが多い。
若気の至り というけど、まさに 知らぬが花 なのかも知れない。
さて、今から40年前の航空製造メーカーの話だ。
その頃というと、ジェットは707ゃDC-8が全盛の頃だった。
中距離は、やっと727がでてきたかなぁ... という頃だ。
しかも、中距離国際線ですら、プロペラ機が大活躍の頃だった。
そんな中で、お客の立場から、仕様書を製造メーカーに送った会社がある。
アメリカン航空。
今日まで、アメリカの上位会社で倒産して無いのは、ここと
サウスウエスト だけ。
どっちも 南部は テキサス州 ダラス出身の会社だ。
やっていることは、正反対な事が多い両者が、最後に生き残った所に、
おらは、感慨深いものがあるし、アメリカ化した日本の経済の秘策を
観てしまう。
ところで、この仕様書は、こんな物がほしいというプラン程度の物だったらしい。
ということで、応じたのが、ロッキード社とダグラス社。
ロッキード社は、今は旅客機部門から撤退しているが、ここ日本では、
40過ぎのおばさんでも知っている、別の意味で有名になった会社だ。
そんなメーカー側からの最初の回答提案は、どっちもエンジン2発機だった。
この頃は、お互い明らかに形状が異なっていて、ダグラス機は小型ジャンボ
みたいな形状で提案されていたみたいだ。
このアメリカン航空の仕様書は..この2社の運命をここで決めた様な気がする。
一方...同じ頃にヨーロッパでは、ヨーロッパ域内を200人から 300人ほど乗せて
移動できる機体の模索をしていた。 (俗に エアバス構想 というものだ。)
この頃は、欧米で似た仕様で個性的な2発エンジンエンジン機体を、
3社3様で模索していたのだった。
しかし、結果はアメリカの2社は3発機の道に行った。
洋上飛行や高温高地対策などの対応のためだった。
このようにして、欧米の両者の道は分かれた。
ヨーロッパ側は出遅れたけど..
エアバス計画は、その後本格化
A300 という機体ができたのだ。
しかし、A300 は全然売れなかった。
その当時はロッキードとダグラスの熾烈販売線に巻き込まれ大不況も襲った。
仕方なく、苦渋の策でアメリカのイースタン航空に無償レンタルを実施。
運行結果が良好だったので、購入してくれることになった。
その後、他の航空会社も見方を変え、この機体の改良型である
A300-600R型を最初に作ってくれと頼んだのは、なんとアメリカン航空だった。
アメリカンは仕様に基づいて作った..両方買ったのではなく..DC-10を購入した。
実はDC-10の購入がアメリカンのA300につながる..のは後述する。
その後のエアバス社の躍進劇は、ご周知のとうりである。
とりあえず先行組みの...
ロッキードL-1011 トライスター と ダグラス DC-10 は
3発機として、似たような時期に似たような機体が出来てしまったわけは
この客からの仕様書に、ラガーディア空港の運用が可能なこと。
という条件があったためらしい。....
結局、狭小の空港であるため、機体サイズありきの設計に自由度は
少なかったわけだ。
この似たもの3発エンジン機の勝敗だけど、ダグラス社の勝ちと観ている方が多い。
最大の理由は...2年の時間差..発売ベースで9ヶ月...
ロッキードは最新技術てんこ盛りの機体は先行して出来たけど、
そんな技術を..前面に出して新型採用した、ロールスロイス-エンジンの
無理な技術開発の失敗が元で..ロールスロイスが倒産になり..
その影響で開発が遅れてしまい.
結局...技術屋重視の高性能機体はダグラスより先に余裕で完成していたのに...
試験飛行が予定より2年遅れ.
これが、この国でも歴史に残る無理な営業の元になったとも言われる。
ちなみにダグラス側は技術より、その当時用意できるエンジンと機体の組み合わせで
無難な機体を先行して作り上げ、実績重視で営業で機体販売に挑んだ。
しかし、そんな一時期は成功したDC10シリーズも時間変化には勝てなかった。
その後、ダグラスは合併し、DC-10の派生型のMD-11を開発。
この機体の時代状況が変わり、米国は2発エンジン機長距離洋上飛行を認めた。
すると経済性の優位から2発機の台頭という結果になった。
こう言う流れを視ると、開発当初は主導権を営業が技術を勉強して握り
販売が乗れば...今度は技術が営業を勉強して握るという...
販売成功の..切替え定石パターンがあるのかな..とか思うのだが....
ちなみにエアバスの基を作った 2発エンジン機のA-300 は
開発当初から エアバス構想の目標機体であり、後年合流して
ワイドボティーエアバス構想機なんて..3発エンジン米国機とゴチャ混の言葉に翻弄されても
作った当時は新参者で売れないし評価も最低だったが..そんな一時的に運が悪くても、
後年はエアバス構想の目的道理の、大変評価されている機体になった。
ちなみに..A300の改良版A300-600Rと派生の胴体短縮したA310は
現在主力のB767-200/300ERとサイズ性能も瓜2つの機体である。
ということで..
時代の先を進みすぎて売れない時期と..後年は競争相手の時代遅れの部分の露呈という
時間変化に絶妙のタイミングで歩調が合った。
偶々と言う人もいるけど..本当に航空機の発売のタイミングは
めちゃくちゃな技術力よりも..販売上では現在でも最大重要要素なのだ。
ちなみに後年の相手..ボーイング767の大成功は..そんなマーケティングを
かなり短い周期間隔で視ており..単にあそこが作って売れたからではない..
大体..5年前のデーターを信用するのもどうかと思うのだ。
これが一番基本的な営業施策だ...
基本に忠実にやって..ボーイング社も成功ともいえたのではないかと思う。
.とにかく開発経費も馬鹿にならない新参者で一番最初に成功した機体でもあった。
更におまけだが
この当時に、現在にも受け継がれているエアバス思想ともいえる、
機体装備品の共通化が図られていた。
たった1機種しか作ってなかった当時に共通化を図ろうとしたのは、
他社機だったダグラス社の3発機のDC-10 の装備品だった。
購入部品代は高くてもDC-10と保守性を考え他社営業成功機の使用部材の共通化に乗った。
でも..
航空機販売営業力が弱いとコレが一番有効なまともな営業手法みたいで、
たとえばフォツカー100なんかはボーイングからフラップを買っていた。
自社で作れば安く性能アップも容易なのに、高い他社部品を性能ダウン覚悟で
買って付けたのは737の部品なら全世界で手に入りやすいためである。
ついでだが..倒産しても...現役で飛べる理由は..主要な保守部品は他社が作っていたため...
飛ぶ鳥は跡を濁さない...はずなのだ...
某国の新型機は技術技術と馬鹿の...で騒いでいるけど..
VHS とβで散々な顧客保護をウタッタ通産省が..一番ボケているみたいである。
1回羽田の航空会社の小学生用の見学コースでも行って..
部品倉庫でも見に行けば..すぐに..かも。.
A300はこんな策を講じたおかげで、国内のJASも逆パターン営業で同時運用した会社。
他にも結構あったみたいだ..これが本位の航空機営業のような気がする..
さて..最終的には無理な営業を強いられたロッキード は
開発当初は誰が視ても..一番売れること間違いない..
そんな時代もあった..それくらい開発の出だしの速さと..高度な技術一直線で
ウサギさんだった。
一方..ダグラスは本当に亀さん状態..開発の出だしは非常に遅れるし..
完成予想もジャンボを3発中型にしただけろうと、ありきたり飛行機なんて下馬評..
でも..
そんなロッキードは.あとから考えてみると..
たった1つの技術の開発失敗が元で..こんな結果になったのだ。
さてさて...
エアバスは今では当たり前の2発エンジン300人機の先駆け機種なのに
その当時では..エンジンの片方が止まったらどうする..の意見が多くて..
しかも石油ショックの大不況。
今では当たり前の双発エンジン機を作っても...全く売れなくて途方にくれた。
後年..A340が4発エンジンなのは..こんな営業マーケティング話の教訓もあったらしい。
でも最終的には..売れなくてアリさんラベルだった弱小エアバスが一番最後に台頭した。
なんとルール改定...2発エンジン機の運用規定を改定して洋上飛行も可能になり、
ボーイング社という大メーカーが新型機として
B767/777機の2発エンジン機の信頼を提供したのである。
ちなみにA300とA300-600の最大の違いは3人乗務か2人乗務か..
コツクピットも切り替わりの時期で300人クラス以上の機体で
2人乗務を世界で始めて達成したのもエアバスA300の特別仕様機であった。
こんな状態についていけなかった3発エンジン機で
燃費保守の悪い亀さんは営業的に兵糧攻めで..餓死状態
最後はボーイングと合併...今日に至っている。
この戦い..一般的にはダグラスとロッキードで区切ってある。
だけど..今日から見ると...ウサギと亀とアリの戦い..
ウサギと亀は競争で勝ったけど..亀とアリは亀さんの一方的な餓死で不戦勝...
とにかく..勝ったのはアリさんだったのだね...
営業的な話もしたが..皆さんは胡散臭いと思う人も多いかもしれないけど..
残念ながら..そっちも正解..営業は馬鹿でもてきる。
と言われるが..おらに言わせれば..本当に頭の悪い馬鹿じゃないと出来ない..
出来ないような気がする。
と同時に..
本当の販売営業は..かなり日々の学習能力が高い..頭が良い人でないと出来ない。
基本的な段取りを最初にやってないので..胡散臭くなるわけだ..ここだけは把握してもらいたい。
こんな話だが、
おらは営業と技術の噛み合い方の教訓として、整理しているけど、
今でも、いろんな分野の製品で似たようなことが発生しているんだろうなぁ..
と思っているのだった。
(今は、市場で勝っていても、弱物がいつ這い上がってくるか分からないのだ...
逆の立場でも、耐え忍べばチャンスもある...)