

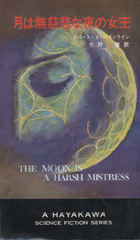

ロバート・A・ハインライン/著 矢野徹/訳
『月は無慈悲な夜の女王』
早川書房 1969年
ハヤカワ文庫 1976年、2010年
|
〈ヒューゴー賞受賞〉 |
| 2076年7月4日、圧政に苦しむ月世界植民地は、地球政府に対し独立を宣言した! 流刑地として、また資源豊かな植民地として、月は地球から一方的に搾取され続けきてきた。革命の先頭に立ったのはコンピュータ技術者マニーと、自意識を持つ巨大コンピュータのマイク。だが、一隻の宇宙船も、一発のミサイルも持たぬ月世界人が、強大な地球に立ち向かうためには……ヒューゴー賞受賞に輝くハインライン渾身の傑作SF巨篇。 |
<ハヤカワ文庫>
=例会レポート=
課題本を決める例会の2日前に小松左京氏が亡くなり、まだ1作も読んだことのない彼の作品を何か読みたいと考えたけれど見当が付かず、代わりにせめてSFを…ということで思い付いた推薦本でした。
こちらも読んだことのない作品でしたが、『夏への扉』で感じた読み物としてのクオリティやインターネット上の評価等でそれなりに内容に期待をして推薦したところ、参加者から「長い」「読んだけど好きじゃない」等とネガティブ情報を付加され、それでも多数決で課題本に決まり嬉しく思っていたところ、帰り際の講師から「ハインラインって面白いか?」という衝撃発言が飛び出し、私は密かに大荒れの例会の再来を覚悟していました。
しかし、予想に反して結果は思ったよりは悪くなかったように思います。
参加者18名と講師の内、最後まで読み終えた人は14名。
自分も含めて読み終えた人からは、面白かったという評価を比較的多く頂きました。
<肯定的な意見>
・構成が上手
・登場人物(マイクも含めて)が魅力的
・訳者が好き、訳が上手い
・宇宙の革命や戦争がテーマの作品は戦闘シーンに集中しがちな印象だが、民意の扇動や外交等、政治的なアプローチも詳しく描かれている
・月世界が独裁政権になることも想像させるような終わり方が興味深い
・革命の成り立ちの描写が面白い
・文章に古いなりのユーモアがあって読み易い
・ハードなSFではなくファンタジー寄りで読み易い
・現実にはないSFならでは設定が楽しめる
・世代が替わることを感じさせる終わり方が良い
・冷戦時代の影響が強く、各国の扱われ方が興味深い
・最後まで読めたことに対する満足感が感じられる
ただし、やはり当然厳しい意見も。
<否定的な意見>
・SF初心者にお薦めのような紹介をされているが初心者には向かないと思う
・設定やユーモアが古く、いかにもアメリカ的
・長過ぎる(約600ページ)
・期待した程ではなかった
・地球に行った辺りで中だるみし、退屈した
・婚姻制度の説明が多かったが不要だと思う
・物語に起伏が少ない
・古い作品の為、設定の面白さが弱くなってしまっている
・作家の意図や寓意がわからない
・人物が魅力的でない
・タイトル自体は詩的だが作品と結びつかない
・『夏への扉』は良かったが、本作は面白くなかった
・理解できなかった
約50年前の作品だということについても色々と意見を頂きました。
<作品の古さについての意見>
・61年にケネディ大統領が10年以内に月面着陸を成功させると宣言し、世界中が月に注目していた中で書かれた作品(着陸成功は1969年)なので、月に対しての知識や関心が現在と非常にギャップがあり、それがノスタルジーを感じさせて淋しい
・『夏への扉』で使われたコールドスリープによるタイムトラベルの設定は現在もまだ実現できていないのに比べ、本策では現在既に月面着陸をし終わっているということが『夏への扉』に比べて古さを感じさせるのかもしれない
・当時としては画期的だったはずだが、この後多くの作品で同じような設定が繰り返し使われたことによって新鮮味が薄れている
・訳の言葉の古さを解消する為に、そろそろ新訳を出しても良いのではないか
・50年前に描かれた100年後の世界の鮮度の限界を感じる
また、マイクについては、超高性能のコンピューターという設定から、『2001年宇宙の旅』(1968年)のハル、『スーパーマンIII/電子の要塞』(1983年)のスーパー・コンピューター、手塚治虫『火の鳥-未来編』のハレルヤを思い出したという人もそれぞれ居られました。
その他にも、本作に関する左右翼の思想や7月4日をキーワードとした移民の物語として捉え方、更には大阪万博の月の石や矢野徹『ウィザードリィ日記』の思い出等についても話が及びました。
<講師から>
・エンターテイメントに徹しているアメリカの良い作品
・革命をSFという舞台装置の中で書いたらどうなるか、というのも一つのテーマではないか
・人物とコンピューターとの関係の発展の書き方(特に導入部)や設定が上手
・SFは伝奇である、という面白さがある
・「教授」はチェ・ゲバラではないか
・SFは風俗小説でもあるので時代が過ぎると読み辛くなる傾向はあるが、人物の内面等、普遍的な部分の描写がしっかりしていれば読み続けられる
・作者は、冷戦時代の制約を超越した設定の作品にさせたかったのではないかと思うが、それが逆に冷戦時代の空気を感じさせてしまい、残念
・アメリカの独立記念日を扱っているが、原住民については一切書かれていない
※講師からは、いかにしてSFが苦手になったのかという話もたっぷりして頂き、更に、SFは未来を、ミステリーは現在から過去を、時代小説は過去を書いているという、とても興味深いお話もして頂きましたが、諸事情により割愛させて頂きました…すみません!
今回は今まで自分で推薦した課題本の中では、一番満足しました。先ずは、自分が非常に気に入る作品だったということ。次に、苦手な人も好きな人もはっきりしていて、それぞれの意見を聞くことができたこと。正に読書会の醍醐味です。皆さん、長くて古い小説に付き合ってくださり、ありがとうございました!



















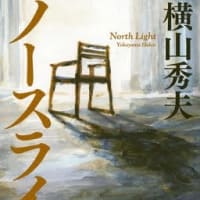






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます