
 今年のベスト本ですよ!
今年のベスト本ですよ!先日の例会で7月の課題本として推薦しましたが、3,000円という価格のせいで、(Sさん以外からは)一顧だにされなかった、あの本です。新潮クレスト文庫で630ページの超大作ですが、途中からぐいぐい一気読み。昨日1日朝から晩までで読んじゃいました。
舞台はイギリスの占領が始まる直前のビルマの街マンダレーで始まり、アウンサンスーチー女史が登場するほぼ現代のヤンゴンまで。ビルマ、インド、マレーシアの3つの国、4家族4代にわたる大河小説です。だれが主人公ってわけでもなく、登場人物のだれかに特に思い入れているわけでもなく、時代とその中で流され、いろいろあって生きていく人々の物語です。ストーリーてリングの巧みさ、ゆるがない世界観、物語と適度な距離を保った語り口など、すべてすてきでした。tadeせんせいの好みじゃないかなあ、と思います。
けっこうブレイクしている本らしく、図書館では予約待ちになっているので、粘り強く待てる方、お金の余裕のある方は、ぜひぜひ、読んでみてください。(ジェフィー23)



















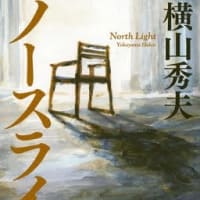






英語文学でインドを、中国語で中国を描いた大河小説を探すのは難しくないだろうと思いますが、ビルマとインド、マラヤを舞台に、さまざまな血のルーツを持つさまざまな階級の人々が、絶えずこれらの地域を移動しながら紡ぎだす物語を、部屋にいて日本語で読める、この幸せ。
"新潮クレストブックス"シリーズは、この大著に印象的な写真を用いた美しい装丁を施し、優しく手になじむ紙の質感もあって、本読みの幸福感をいや増してくれますね。
ビルマ近代史に極めて大きな負の影響を与えたにもかかわらず、かの国について我々日本人が知っていることはとても限られていると思いますが、この本を読むことによって、ビルマ王家の没落、東西への人の活発な移動、大英帝国及びインドの影響などを、登場人物たちと一緒に見つめる貴重な経験をした気持ちです。
それにしても、日本の侵略戦争の罪の深さを考えると、改めて暗澹たる思いにさせられます。
大英帝国におけるインド人士官の最初の世代となったアルジャンの苦悩は、列強の圧力と祖国の独立運動の板ばさみとなった人々の象徴のようで、マイケル・オンダーチェの「イギリス人の患者」に出てくる、英国軍人と固い信頼の絆で結ばれたインド人将校を思い出しました。
一方、ビルマ最後の王妃の侍女であった、血筋すら不明なドリーの前近代的ともいえる人物像は、南アジアの濃い空気の中にたちこめる霧のようにつかみどころがなく、アルジャンの論理的なそれとは対をなすように見えます。
この両名が、それぞれの形で生を全うするその姿が、私には最も心に残るものとなりました。